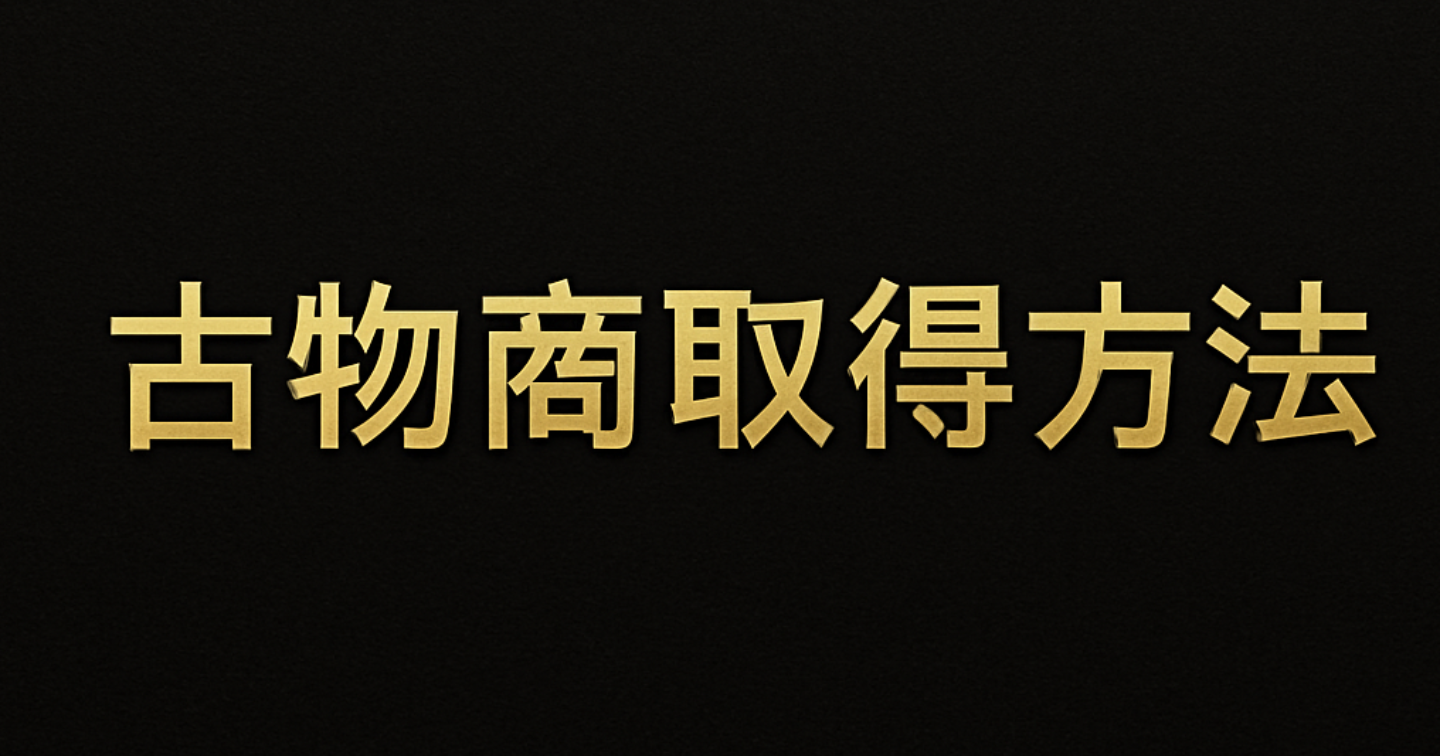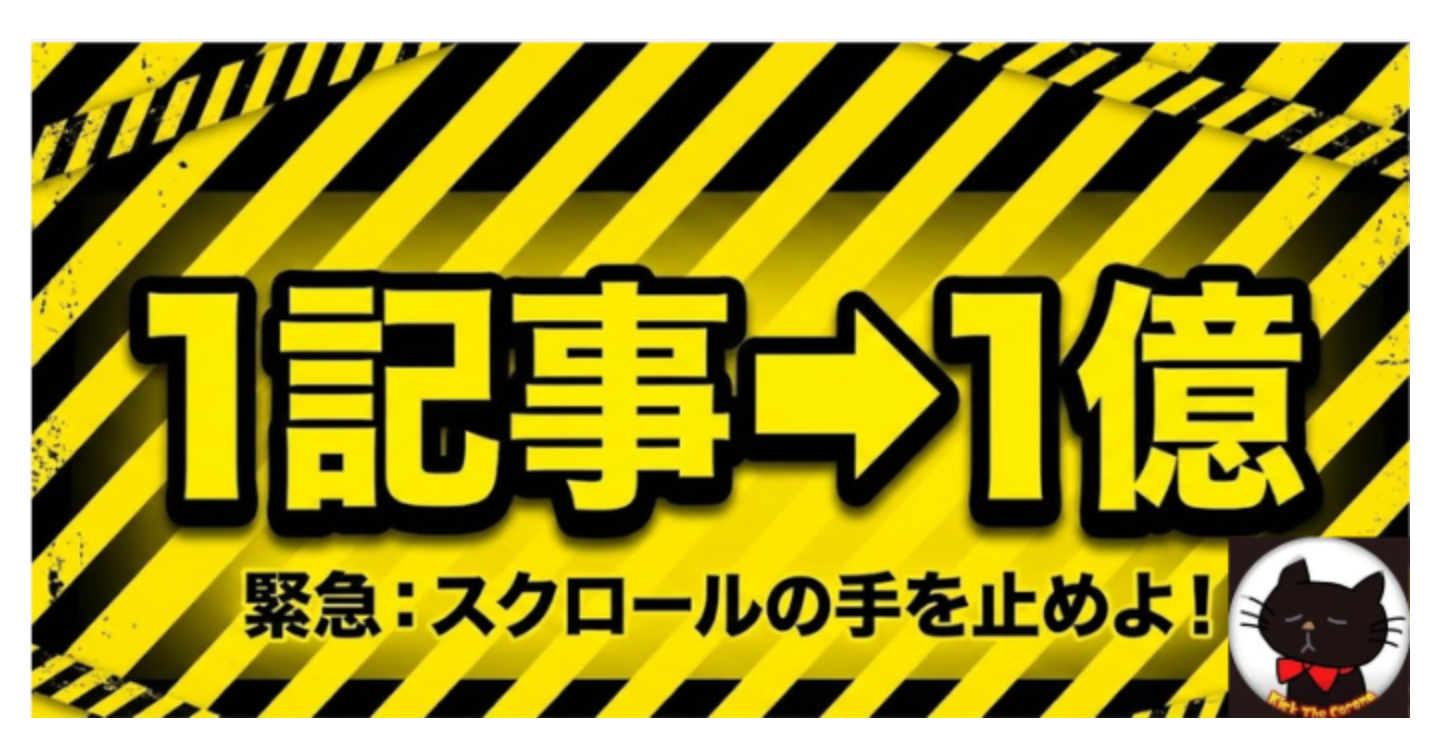はじめに|古物商免許は物販副業の基盤となる国家許可
中古品の販売や仕入れを行うにあたり
✅ 法的に必要になるのが「古物商許可」
しかしネット上の情報は断片的で「ざっくりした手順しか載っていない」「警察署で何を聞かれるか分からない」「落ちる場合があるのか不安」
そう感じたことはないでしょうか
実際のところ古物商免許の申請には非常に細かなルールや地域差が存在します
✅ どの警察署に提出するか
✅ ホームページのURLを求められるかどうか
✅ 写真サイズ・証明書の細かな条件
✅ 添付書類の表記ミスや不備
これらを正しく理解していなければせっかく準備した書類が「差し戻し」されることもあります
✅ 本記事の目的は “具体と正確” の両立
この記事では単なる手順解説ではなく
✅ 書類の中身
✅ 提出時の注意点
✅ 対応フロー
✅ 取得後の届出まで
実務レベルで必要な情報をすべて詰め込みます
ポイントは以下の通りです👇
✅ この記事で得られることは次の通りです:
🔹 古物商許可の取得手順と全体像が理解できる
🔹 提出すべき書類・写真・費用がすべて分かる
🔹 警察署で聞かれる内容と“詰まるポイント”が分かる
🔹 免許取得後の届出や営業表示義務が把握できる
🔹 自身の副業モデルにどう活かせるかが明確になる
副業として物販を始めたい方ネット販売の規模を拡大したい方法人化や古物市場参加を視野に入れている方にとってこの「古物商許可」はただの通過点ではありません
✅ あなたの物販事業に“信用”と“合法性”を与える基盤です
次章からは「古物商とは何か?」の基本から始め実際の申請・取得・活用・運用の全プロセスを順に解説していきます
📌 本記事には返金・注意事項も末尾に明記しています法令順守・トラブル防止の観点から必ずご確認ください
第1章|古物商免許とは何か?副業に必要な理由
🔹 古物営業法の基本と免許の必要性
「古物商免許」とは中古品を買い取って販売するために必要な国家レベルの営業許可です
根拠法は「古物営業法」
この法律では「古物」を次のように定義しています👇
一度使用された物品使用されずに取引された物品これらの物品に“手入れ”や“加工”を加えたもの
つまり
✅ 新品でも一度誰かの手を通った品
✅ 未使用であっても中古として取引されるもの
✅ 修理品・リユース品・再販売品
これらを反復して売買するには免許が必要です
🔹 ネット物販における該当行為の範囲
誤解されがちですが「メルカリで1回売る」程度では免許は不要
ただし以下のようなケースでは完全に古物営業の範囲に該当します👇
✅ 利益目的で中古品を仕入れて売る
✅ 継続的・反復的に中古品を転売する
✅ ネットショップを構えて中古品を販売する
✅ 他人から預かった中古品を販売して報酬を得る
たとえヤフオクやラクマであっても「利益を得るための継続行為」であれば無許可=違法営業にあたる可能性があります
🔹 免許がなくてもできること・ダメなこと
できること:
✅ 不要品を一時的に処分(私物処分)
✅ 家族や友人への個人的な譲渡
✅ 新品のみの販売(メーカー仕入れ)
ダメなこと:
⛔ 中古を仕入れて再販
⛔ 委託販売で報酬を得る
⛔ 古物を分解・加工して販売
特に「メルカリせどり」「フリマアプリ転売」などを継続する場合知らずに違反している事例もあります
🔹 古物商許可を持つメリットと実務面の強み
✅ 古物市場(業者オークション)に参加できる
✅ 警察への届出済みで信用力が上がる
✅ プラットフォームでの本人確認がスムーズ
✅ 古物を扱う副業に安心感と合法性を持たせられる
✅ BtoB交渉や外注管理にも有効な「資格扱い」になる
また法人が取得することで企業間取引(BtoB)の際にも“信頼と実績”を担保しやすくなります
🔹 まとめ:副業物販の出発点としての古物商許可
現代の副業やスモールビジネスでは
✅ メルカリ
✅ ヤフオク
✅ eBay
✅ BASE
✅ 自社ECサイト
こうしたツールを活用して収益を上げていくことが常識になっています
しかしその中で「中古品を扱うモデル」を選ぶなら古物商免許の取得は避けて通れません
✅ 収益性
✅ 初期費用の低さ
✅ 在庫回転の速さ
こうした利点がある中古ビジネスを安心して進めるためにまずはこの免許から取得していくのが正攻法です
第2章|取得に必要な書類・費用・写真の完全一覧
🔹 個人・法人によって提出書類は異なる
古物商免許は
✅ 個人
✅ 法人
どちらでも取得できますが必要書類には一部違いがあります
【共通で必要になる主な書類】
✅ 古物商許可申請書(警察署で配布または都道府県HPでDL)
✅ 誓約書(犯罪歴や破産歴の確認)
✅ 略歴書(過去5年分の職歴など)
✅ 住民票の写し(マイナンバー記載なしのもの)
✅ 身分証明書(本籍地の市区町村で発行/運転免許証では不可)
✅ 登記事項証明書(法人のみ)
✅ 定款(法人のみ)
【追加で求められることがある資料】
✅ 事務所使用承諾書(賃貸物件の場合)
✅ 土地建物登記簿謄本(自己所有の場合)
✅ ホームページURL(ネット販売を行う予定の者)
✅ 利用予定プラットフォーム(例:メルカリ・eBayなど)
✅ 営業所の図面(簡易な間取りでも可)
🔹 証明写真の仕様と注意点
申請書には顔写真の添付が必要です以下の仕様に合致していないと「差し戻し」対象になります👇
✅ 縦3cm × 横2.4cm程度
✅ 背景は白・青・グレーなど単色
✅ 正面・無帽・無背景
✅ 撮影後6ヶ月以内
✅ 顔に影や反射がないこと
コンビニ証明写真機でも問題ありませんが背景が透けたりする場合は再撮影を求められる場合があります
🔹 提出先と費用(収入証紙)
申請先は「営業所の所在地を管轄する警察署」です受付は平日のみで「生活安全課」が担当することが多いです
✅ 申請費用:19,000円
✅ 支払方法:収入証紙(警察署内では買えないこともあり)
【注意】収入印紙ではなく「収入証紙」なので要注意購入場所は都道府県の収入証紙取扱窓口(県庁・法務局・県税事務所など)
🔹 書類作成時に気をつけるポイント
✅ フリクション(消せるボールペン)はNG
✅ 押印が必要な書類があるためシャチハタ不可
✅ 記入内容は黒インク・楷書で明確に
✅ 間違った場合は二重線+訂正印で修正
※ワープロ印字・手書きの混在は原則OKですが、各警察署により取り扱いが異なるため、事前に確認することが無難です
🔹 書類不備で申請できないケースとは?
✅ 氏名や住所が他の書類と一致しない
✅ 書類の日付が未来日・過去すぎる日付になっている
✅ 提出日から3ヶ月以上前に発行された住民票などを添付
✅ 顔写真が規定外のサイズ・仕様
✅ 免許証住所と営業所住所が一致しないケースで説明不足
✅ まとめ:準備にかかるコストと所要期間
【個人申請の場合の目安】
⏳ 準備期間:3日〜7日💰 費用総額:約21,000円前後
内訳👇→ 収入証紙 19,000円→ 証明写真 約800円→ 住民票・身分証明書 約500円~1,000円
書類の整合性と正確さがすべてミスや未提出があると窓口で突き返され、余計な時間とコストが発生します
第3章|警察署での申請フローと注意点
🔹 担当窓口での提出から受理までの流れ
古物商許可の申請は
✅ 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課で行います
受付時間は原則
✅ 平日の午前9時〜午後5時頃(正午〜13時は休憩時間で受付不可のことも)
提出先が分からない場合は「〇〇市 古物商 申請窓口」などで検索するか都道府県警察のHPで確認できます
申請時の基本の流れ👇
1️⃣ 事前に電話で「予約」や「確認」を入れる(必須ではないが推奨)
2️⃣ 書類をすべて揃えて持参
3️⃣ 担当者がその場で内容を確認(30〜60分かかることも)
4️⃣ 記入漏れ・押印漏れがあればその場で修正
5️⃣ 問題がなければ「受理」され、控えが渡される
受理=許可が出るわけではないので注意このあと警察による「審査」に入ります
🔹 所在地管轄の確認と警察署での事前予約
古物商許可の申請は住民票上の住所ではなく営業所(店舗・事務所)の所在地が管轄基準です
【例】・自宅でネット物販をする → 自宅の住所が営業所・賃貸のオフィスを借りている → その住所が営業所
そのため、営業所のある地域の警察署へ提出します
予約については都道府県により違いがあります👇
✅ 予約不要(直接来所)OK:一部地域
✅ 予約必須(Webまたは電話):大都市圏中心(例:東京都)
事前に確認しておくことで、無駄足にならずに済みます
🔹 よくある質問と正しい受け答え例
警察署では以下のようなことを口頭で聞かれる場合があります👇
🟢 「どのような形態で古物営業を行う予定ですか?」→「ネット販売を予定しており、eBay・BASE・メルカリ等を利用します」
🟢 「店舗はどちらですか?」→「自宅兼用で、間取りは添付の図面通りです」
🟢 「取り扱う予定の商品ジャンルは?」→「主に中古ホビー品・家電・衣類などを想定しています」
🟢 「ホームページURLの提出はできますか?」→「まだサイトはありませんが、販売予定プラットフォームのトップページURLを記載しています」
このように具体的かつ簡潔に回答できるように準備しておくことが重要です曖昧な説明や「何も決まっていません」は信頼性を下げる要因になります
🔹 審査期間の目安と進捗確認方法
申請が受理されてから
✅ 許可証が交付されるまでの期間は2週間〜6週間程度
【都道府県ごとの傾向】・東京・大阪などは約30日前後・地方警察署では3週間程度で交付されるケースも
【進捗確認の仕方】
✅ 申請後2〜3週間経過しても連絡がない場合→ 警察署の生活安全課へ電話で確認可能
※受理番号や提出日を伝えられるように控えは保管しておくこと
交付された許可証は警察署で「直接受け取り」に行くのが基本身分証明書の提示が求められることがあります
✅ まとめ:申請時の落とし穴を避けるには?
✅ 書類を「警察署の仕様」に合わせて準備する
✅ フリクション・鉛筆は使用しない
✅ 営業所の図面・用途の説明を明確に
✅ 聞かれそうなことは事前に“台本”を準備しておく
✅ 不安な点は申請前に電話で確認しておく
このひと手間が申請を「一発で通す」最大のコツです
第4章|取得後にやるべき手続きと届出
古物商許可証が交付されたらそれで終わりではありません
✅ 取得後にやるべきこと
✅ 継続して守るべき義務
これを理解しておかないとあとで“無許可営業と同じ”扱いになることもあります
🔹 営業所への掲示義務
古物商許可証を受け取ったら
✅ 営業所の見やすい場所に掲示する義務があります
物理的な事務所がないネット販売のみのケースでも
✅ 自宅の玄関や部屋の壁
✅ 来客が想定されるスペース
に掲示する必要があります
またプラットフォーム上にも記載することが望ましいです👇
✅ BASE・STORESなど:運営者情報に「古物商許可番号」を明記
✅ 自社サイト:特商法表示ページに記載
🔹 ホームページ・ネット販売を行う場合の届け出
ネットで古物を販売する場合
✅ 「URL届出」が必要です
これは「古物営業法第5条の2」に基づくもので
✅ 使用するURL(ドメイン)を警察に提出する必要があります
【対象となるケース】
✅ 自社ECサイトを持つ
✅ BASE・STORES・Shopifyで販売する
✅ メルカリShopsを運営する
eBayやAmazonのような外部マーケットプレイスは必ずしもURL届出の対象ではないとされていますが警察署によって見解が分かれるため、念のため相談するのが安全です
【URL届出の手続き】
✅ 「URL届出書」を記入して営業所管轄の警察署に提出
✅ 変更があれば速やかに再提出
提出方法は郵送でも可能ですが基本的には窓口で直接提出することが推奨されます
🔹 帳簿の記載義務と管理方法
古物商には「帳簿記載義務」がありますこれを怠ると罰則対象です
【記載すべき帳簿内容】
1️⃣ 取引日
2️⃣ 品目・数量・状態
3️⃣ 相手の氏名・住所・職業・本人確認方法
4️⃣ 代金・数量・取引経路
【本人確認が必要なケース】
✅ 買取や委託販売で古物を預かる場合
✅ 法人や個人から仕入れるとき
【帳簿の形式】紙でもExcelでも構いませんが
✅ 「古物台帳」の形式に沿う必要があります
市販の帳簿を使うか警視庁HPなどからExcelフォーマットをダウンロード可能です
🔹 営業の停止・変更・廃止時の届出
古物営業に関して
✅ 営業所を移転する
✅ 営業を一時停止する
✅ 廃業する
これらの場合には変更届や廃止届の提出が必須です
【主な届出事項】
✅ 営業所の住所変更
✅ 氏名・法人名の変更
✅ 責任者の変更
✅ URLの変更
✅ 廃業届の提出(免許の返納)
放置しておくと「虚偽記載・無届け営業」として違法状態になりかねません
🔹 定期的な確認事項とリスク回避
✅ 古物営業法や条例の改正情報を警察署HPで確認
✅ 古物台帳を毎年見直して整合性を保つ
✅ 委託販売・レンタルなどの新規事業を始める前に適法性を確認
✅ メルカリ・ヤフオク・eBay等の規約改定にも対応
【よくあるリスク】
⛔ ホームページURL未届け出での営業
⛔ 委託販売・レンタルで帳簿未記載
⛔ 廃業後の許可証未返納
⛔ 他人名義での営業
こうした事例は軽微に見えても警察からの指導や再申請の対象になる可能性があります
✅ まとめ:許可を「維持」することが信頼につながる
古物商免許は一度取って終わりではありません
✅ 表示義務
✅ 届出義務
✅ 帳簿記録義務
これらを継続して守っていくことであなたの副業ビジネスは「合法・安心・信頼」の三拍子を保てます
第5章|古物商免許を最大活用する副業展開例
古物商免許は単に中古品を売るためだけの免許ではありません
✅ 正しく使えば
✅ 戦略的に組み合わせれば
「仕入れの武器」から「信用力の資産」へと昇華します
この章では免許を最大限活用して収益性を高めるための実践パターンを紹介します👇
🔹 複数プラットフォームを連携させる
eBay・メルカリ・ヤフオクなど複数の販路で同時出品し
✅ 最も利益の出る市場で売却という“分散販売”モデルは、免許によって合法性が担保されます
BASEやShopifyと連携させることで
✅ 自社ブランディング
✅ 顧客の囲い込みも実現可能です
🔹 古物市場への参加で“仕入れ特権”を得る
古物商の免許を保有していれば
✅ 全国の古物市場(業者専用オークション)に参加できます
参加条件は市場ごとに異なりますが原則として以下が求められます👇
✅ 有効な古物商許可証
✅ 営業実態(ネット販売実績などでも可)
✅ 登録料・会費(無料〜年会費数万円)
【市場例】・東京:TAA(東京オートオークション)・大阪:OSAKAネットオークション・地方:地域の骨董市や道具市場など
✅ 相場以下で大量仕入れ
✅ 珍しい一点物を入手など、副業の差別化に直結します
🔹 仕入れ代行・委託販売サービスの提供
自分では売らず
✅ 他人の代わりに仕入れる
✅ 商品を預かって販売してあげる
というモデルも免許を活用すれば合法的に行えます
【例】・SNSで「中古フィギュア仕入れ代行します」・法人相手に「社内備品の在庫整理支援」・副業初心者に「販売代行×コンサル」を提供
仕入れ能力 × 古物免許 = 利益と信頼の両立が可能になります
🔹 免許そのものを“価値化”する
あなた自身が
✅ 免許保持者であること
✅ 古物市場に参加できること
✅ 販売に関する法知識があること
これらを「サービス化」できます👇
【具体例】
✅ 免許を持っていない人向けの“代行出品”
✅ 古物市場へ同行する“コンサル同行サービス”
✅ 初心者向けの“古物物販スクール”の講師
✅ 自分の知識や実績を「教材」として販売
法律的に問題がない範囲で「あなたが持っている権利や知識を“人に貸す”」ことで新しい収益化が可能になります
🔹 他資格や副業と組み合わせる
古物商免許は単体で完結させるより
✅ 他の武器と“組み合わせる”ことで真価を発揮します
【組み合わせ例】
✅ 販売管理・商品撮影ノウハウ → カメラスキル
✅ 税務処理・副業相談 → FP資格
✅ 配送・倉庫活用 → 軽貨物業
✅ 海外販売 → 英語力 × eBay運営
✅ まとめ:古物免許は「転売用の許可」ではなく「事業の土台」
✅ 中古販売のスタート地点であり
✅ 信用構築のベースであり
✅ 自分だけの“収益導線”を広げる鍵です
人と同じ使い方をしている限り免許の価値はただの「許可証」に過ぎません
✅ 他人が気づいていない活用法を見つけたときそれは「合法ビジネスの金脈」になります
おわりに|すべての古物副業は“合法性”を味方につけるところから始まる
古物商の免許は単なる「中古品販売の許可証」ではありません
✅ 信用を生むツールであり
✅ 交渉のカードであり
✅ 収益構造を広げる“免罪符”でもあります
多くの人が取得しただけで終わっているあるいは「なんとなくリスク回避で取っただけ」
それは非常にもったいない話です
この記事で紹介したように
✅ 委託販売や仕入れ代行
✅ 法人向け在庫処分支援
✅ 海外輸出やブランドレンタルなどあらゆる稼ぎ方に活用可能です
重要なのは**“何を売るか”より“どう活かすか”**という視点です
仕入れの強さも、取引先との信頼も、アカウント維持の安心感もすべてはこの免許を正しく使い倒せるかどうかで決まります
これから副業で古物に取り組むなら
✅ 1つのルートに絞って小さく始める
✅ 初期費用を抑えて合法に構築する
✅ 慣れたら仕組み化・委託化で横展開する
この順番がベストです
ビジネスの世界では“許されている行為”が収益のベースになります
そして古物免許はあなたに“許されたこと”を爆発的に増やす法的インフラです
「中古品販売=グレー」と思われている今だからこそ
✅ 免許を持っていることが“最大の差別化”になります
目立つ商品・派手なSNS発信より合法の上に成り立つ仕組みこそが長期的・堅実な副業に育っていきます
「とりあえず取ってみた古物免許」
その価値は使い方次第で“資産”にも“収入源”にもなります
📌 注意事項・免責・返金ポリシー
✅ 本記事は古物営業法などの制度を元に、情報提供・副業支援を目的とした解説です。特定の法的助言・税務アドバイスを提供するものではありません。
✅ 制度・手続きは変更されることがあるため、申請・届出等に関しては必ず最新の管轄警察署または関係機関にご確認ください。
✅ 本記事の内容を基に行動した結果生じた損害・損失等について、著者および販売元は一切の責任を負いません。
✅ ご購入後の返金対応は、運営のガイドラインに沿い「誤購入・重複決済」等の正当な理由がある場合に限り、運営を通じてのみ受付可能です。
📌 本コンテンツは本人が自己成長・ビジネス構築に役立てるためのものです。無断転載・転売・第三者共有は禁止されています。
📌運営のガイドラインに沿った正当な理由による返金申請は受け付けますが、明らかに「情報抜き取り後の返金目的」と判断される場合は運営へ報告し、厳正対応を行う可能性があります。