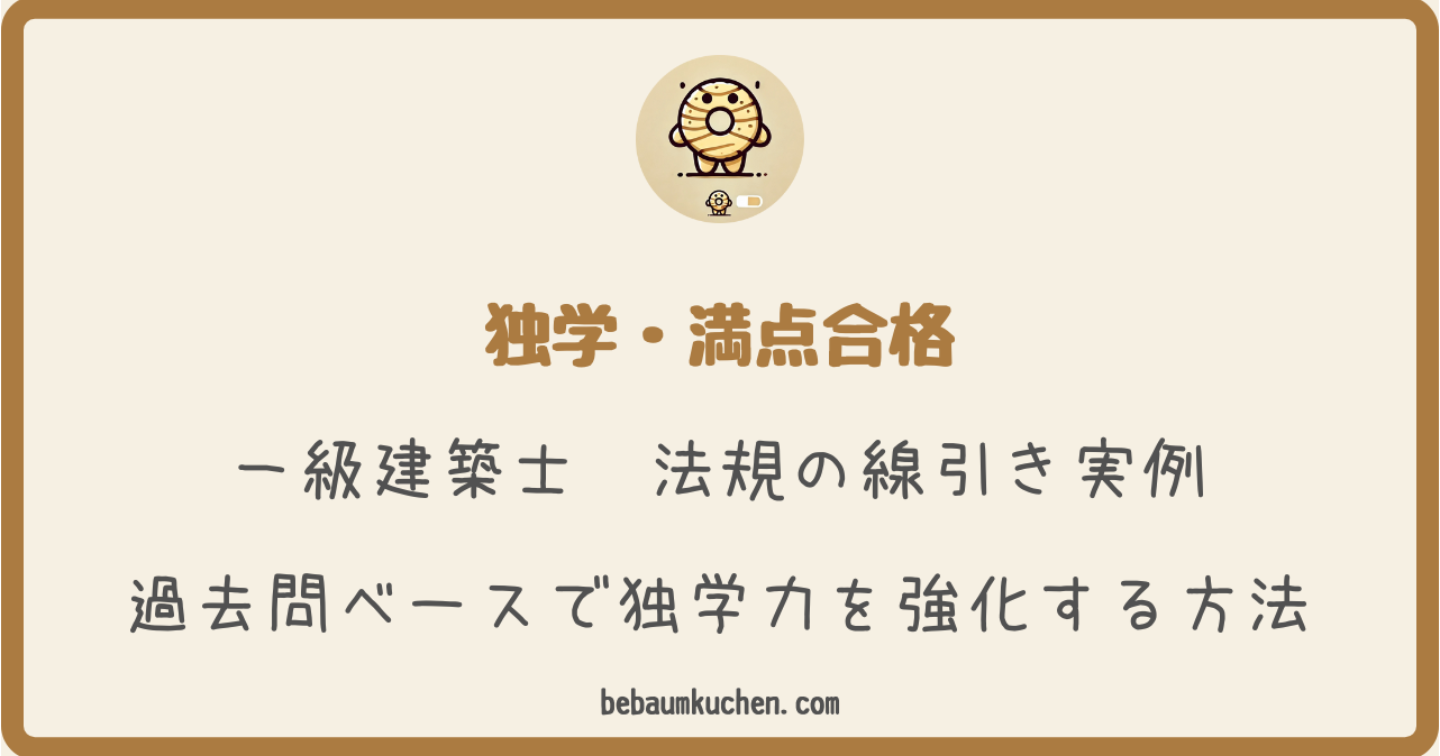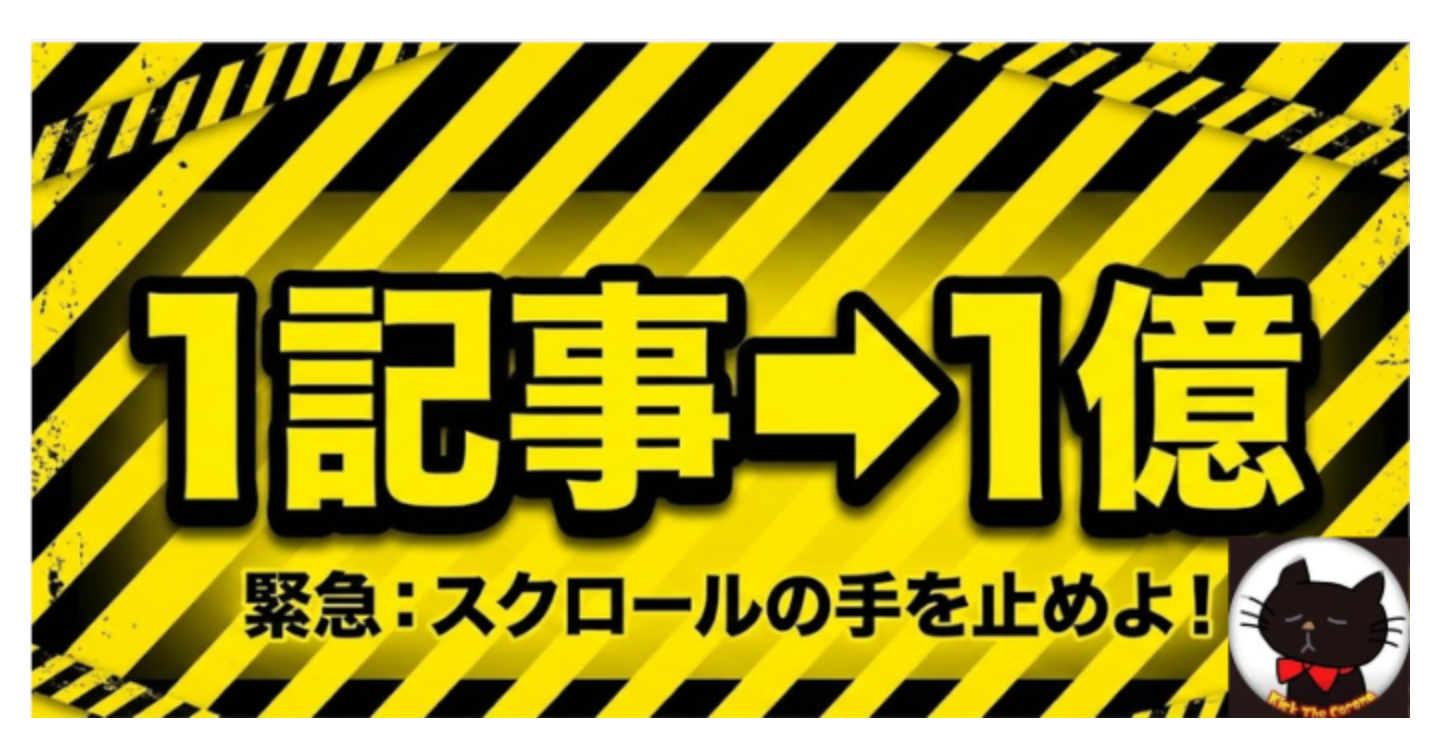「法規の線引き、どこから手をつけたらいいのかわからない…」
これは、独学で一級建築士の学科試験に挑戦する人が最初にぶち当たる悩みだと思います。
以下のnoteでは、「問題を解きながら線引きする(バウム流)」という僕が試験本番で法規30/30点の満点合格を果たすことができた線引きの考え方を紹介しました。
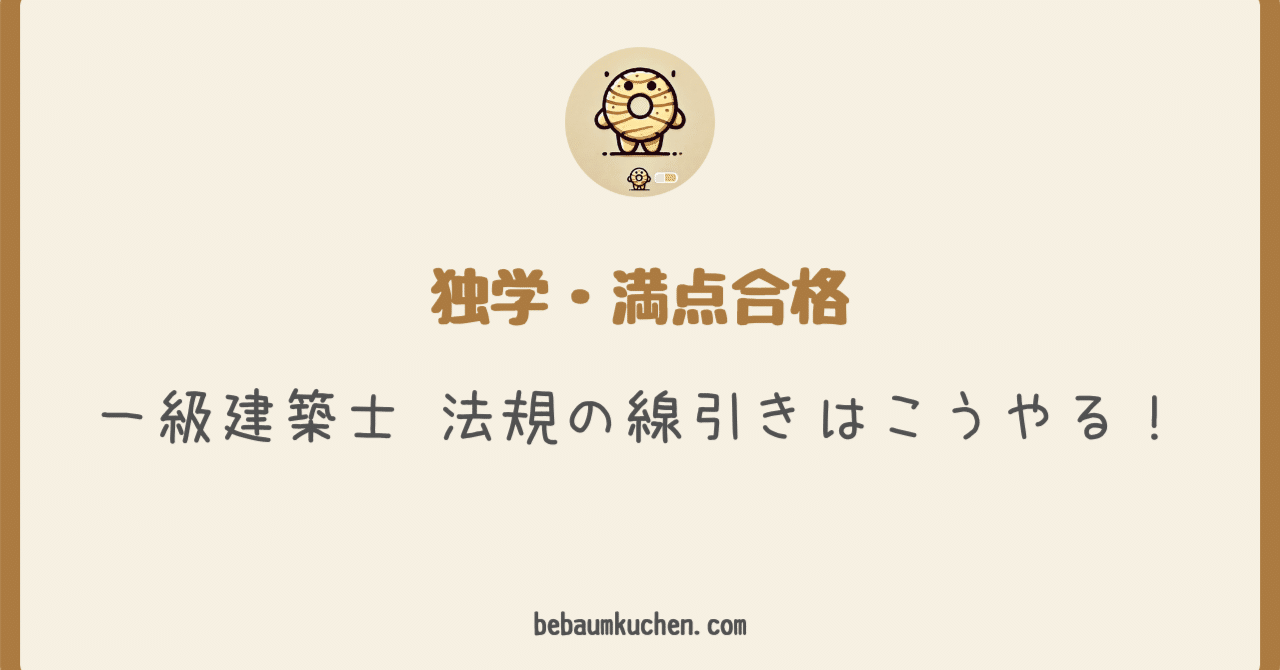
おかげさまで多くの方に読んでいただきましたが、
実際の条文に対して「どこに?」「何色で?」「どんな基準で?」といった具体的な線引き例までは十分にお伝えできませんでした。
そこで今回は、僕が実際にやっていた「線引きの事例」を、
過去問をベースに具体的に紹介していきます。
この記事を読むことで、線引きの「正解」を探すのではなく、
「自分なりの納得と再現性」をもった学習方法へと変えていくヒントが得られるはずです。
線を引くことが目的ではなく、理解して引き、活用して得点につなげること。
この記事が、あなたの法規学習の一助になれば嬉しいです。
線引きの考え方
バウム流・線引きの流れ
まずは、noteでお伝えした「線引きの流れ」をざっと復習しておきましょう。
- 過去問を解く
- 該当条文を法令集で探す(最初は解説から読んでもOK)
- 問題を解くために必要な文言に線を引く
- 関連条文の参照先にも線を引いておく
このときの考え方は、「自分が後から読み返しやすくなるため」に線を引き、
「迷ったときに戻れる目印」としてマーキングする、というものです。
線引きそのものが目的ではなく、思考と記憶の補助線なんですね。
3色フリクションを使用
僕が使っていたのは、一般的な3色のフリクション(赤・青・緑)。
考えながら引いていくとどうしてもミスすることも多いので、
消せるフリクションを選びました。
法令集はびっしり文字が書かれている行間も狭いので、
太さは0.38mmの細字タイプが断然おすすめです。
以下は色ごとのざっくりとした使い分けです。
- 赤:条文の文章部分(主旨)
- 青:用語、ただし書き、カッコの中などの補足要素
- 緑:他条文を案内している部分(参照先など)
基本的には赤と青の2色で完結していました。
赤が続きすぎる場合は青を、逆もまた然り。
文章途中のカッコ内とかは色を変えて線引きしていました。
ちなみに緑は参照先にのみ使っていました。
最初にルールを完璧に決める必要はありません。
途中で使い分けが変わってもOKです。
(実際に僕も途中で微妙に変わっていったような気がします)
大事なのは、「考えながら引くこと」。
これによって自然と情報が頭の中で整理され、復習もしやすくなります。
「次に開いたときにスラスラ読めるか」を意識する
その条文をもう一度読んだときに理解が早まるか?
これを基準に線引きするようにしていました。
読むたびに「あれ?この線、なんで引いたんだっけ?」となるようでは意味がありません。
逆に、線引きが自分の思考と連動していれば、次に読んだときに記憶がよみがえり、得点につながる実戦力になります。
インデックスは使わない
法令集にはインデックスがついているものも多いですが、
僕は一切貼りませんでした。
理由は以下のとおりです:
- 大量に貼ると、むしろ法令集が開きにくくなる
- 貼るだけで「勉強した気」になってしまう
- 貼る作業に時間がかかる割に、実力は伸びない
その代わり、よく使う法令の冒頭(建築基準法・政令・規則・建築士法・消防法)だけに5枚の付箋(粘着力強め)を貼っていました。
そこから目的の条文をめくって探す練習を繰り返していくことで、
自然と構成や条番号の感覚も身についていきます。
たとえば建築基準法の別表は政令の先頭から少し戻ったところを開けば出てきますよね。
インデックス貼りまくるよりかはそのほうが早いような気がしてそうしてました。
きっとそうに違いない。
このように、線引きは「引くこと自体」が目的ではなく、
法令集を自分の思考にフィットした形で“加工”する行為なのです。
線引き実例
ここまで読んでいただきありがとうございます。
では僕が実際に、どの条文に・どんな理由で・どう線を引いたのか?
いよいよここから、
独学で満点合格した僕が行っていた線引き実例を解説していきます。
このnoteの有料部分ではこんな内容が読めます:
- 【実例付き】令和6年の最新過去問を使って、どこにどう線を引くのかを解説
- 【思考の見える化】条文をたどる「順番」や「考え方」もリアルに公開
読み終えるころには:
- 過去問を解いたときに「どこに線引きすればよいか」というつまずきがなくなります
- 自分だけの「わかる法令集」が完成に近づきます
念のため注意点:
- 僕自身の経験に基づく考え方・方法であり、これをやれば必ず合格できるというものではありません
- あくまで個人の成功経験であり、万人に同じ効果があるかは検証されていません
僕が受験したのは平成30年ですが、
実例は最新の過去問を使って紹介していきます。
(令和6年学科Ⅲ(法規)のNo.1を使って実例を紹介します)
以上を踏まえてご検討いただいた結果、
本番で得点に直結する線引きを自分のものにしたい方は、
ぜひ続きを読んでみてください。
早速具体例を紹介していきたいと思います。
あなたの線引きスタイルのヒントになれば幸いです。
「線引きしながら解く」実践解説
実例として、直近の令和6年学科Ⅲ(法規)のNo.1をどのように線引きするか見ていきましょう。
問題文は以下のとおりです。
〔No.1〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」に該当する。
2.建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、屋外階段で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。
3.高さ4mの記念塔の工事用の図面は、「設計図書」に含まれる。
4.同一敷地内に2つの地上2階建て建築物(延べ面積400㎡・200㎡)を新築する場合、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとすると、「延焼のおそれのある部分」を有している。
事前に…
言うまでもないかもしれませんが、まずは問題文をよく読みましょう。
この問題の場合、4つの選択肢の中から誤っているものを回答する必要があります。
明らかに誤っている選択肢がわかれば、ほかの選択肢は飛ばせます。
本番ではまず全体を読み、明らかに誤りとわかる選択肢があれば、
そこをマークして次の問題へ進む判断力も重要です。
次の問題に進んで、飛ばした選択肢は時間が余ったら確認する程度でいいと思います。
ただし、今回は線引きの実例紹介が目的ですので、
全選択肢をじっくり検討しながら、条文を探し・読み・引くという手順で進めていきます。
【選択肢1】
1.建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」に該当する。
関連条文:建築基準法第2条第3号
勉強し始めの段階では、「関連条文どこ?」って状態だと思いますので、
慣れるまではいきなり解説から見て進めてもよいです。
むしろそうしましょう!
慣れてくればだいたいどこの条文を引けばよいかなんとなくわかってきます。
建築設備の定義は法第2条第3号にあります。
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備、又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
問題を解くために必要なところを抜粋すると、
建築設備 建築物に設ける消火の設備をいう。
というところかなと思います。
したがって、以下のように線引きします。