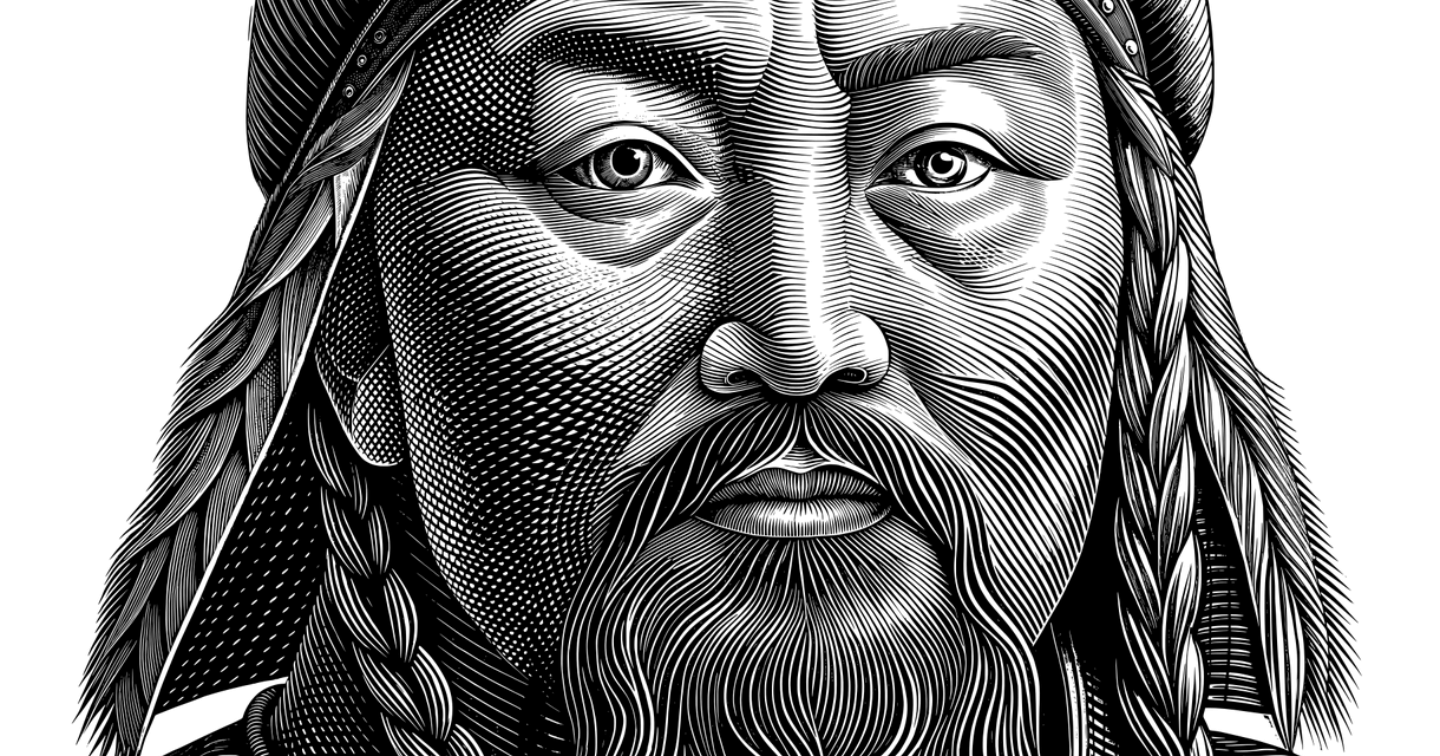理想は、読まれ、理解され、すぐ行動されるコピーです。現実は、時間をかけても反応が伸びず、差し替えの連続です。多くは“伝えたい順”で書き、“読み手の判断順”が欠けています。
さらに、言葉の良し悪しを勘で決めると、改善が止まります。同じ商品でも、見出し一行と第一段落で結果は激変します。しかし、何を変えるかが曖昧だと、労力は数字に化けません。
この記事は「入力→処理→出力→OK/NG判定」を一本化します。読み手の判断順を骨格に置き、差し替え位置を固定します。3日で“回る型”を作り、以後は数字で磨く道筋を示します。
「ありがちな失敗」・自社目線で特徴列挙→抽象語だらけ→行動に結びつかない 根本原因=読者の“直近の不安”に触れず、ズレた順で提示。・修飾語を増やす→強そうに見える→信頼が落ちる 根本原因=証拠不足。事実と数値の欠落で説得が空転。・CTA(行動ボタン)の弱さ→迷いが生まれる→離脱 根本原因=“次の一歩”の具体が書かれていない。・比較対象なし→価値が相対化できない→価格が高く見える 根本原因=代替案との違い提示がない。・A/Bの無計画→差の無い変更→学びがゼロ 根本原因=指標(うまくいっているかを見る数)と仮説不在。
「勘違いの整理と道筋」コピーは“語彙の多さ”ではなく“順番の設計”です。読み手は「自分事化→納得→安心→行動」の順で動きます。各段で役割語を置き、事実と数値で補強すれば反応は上がります。
「本編の予告」このあと「ツール選定/手順の組み方/判断ライン/つまずき対応/続けるコツ」を具体に示します。まずは“順番”を決めましょう。