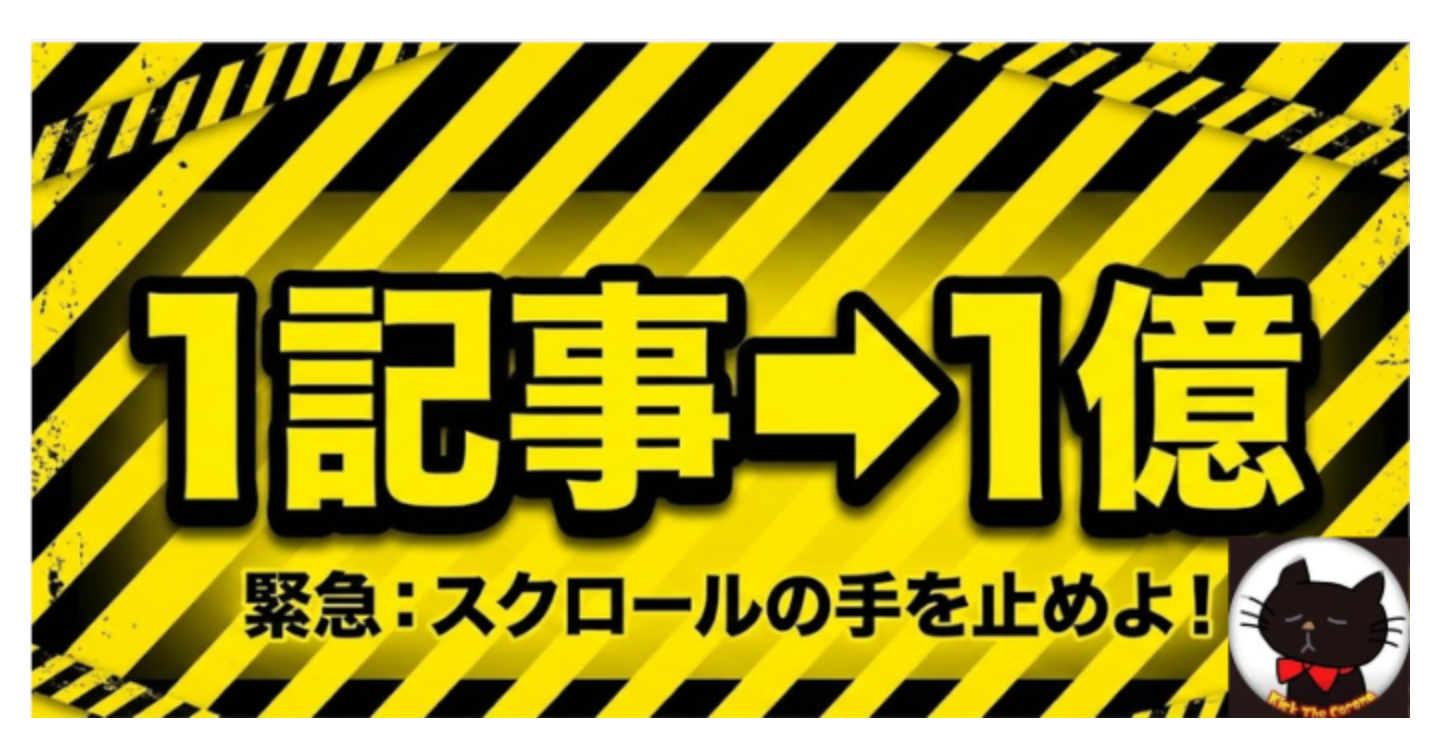「静かな退職」とは
静かな退職(Quiet Quitting)は、2022年ころからアメリカの若者の間で話題となった、働き方のトレンド・価値観です。
日本でも、30代〜40代のビジネスパーソンを中心に、このスタイルを取り入れる人が増えつつあるようです。
例えば、このような働き方を推奨する価値観です。
- 会社では最低限の仕事だけをやる
- 昇進やプロジェクトリーダーなど、責任を伴う役割は基本的に引き受けない
- 残業を避けて、プライベートの時間を優先する
- 愛社精神は持たない
- でも、会社を辞めるつもりはない
僕は約1年前に管理職を降り、その会社で「静かな退職」を実践し続けています。
世間では否定的なイメージを持たれることが多い「静かな退職」ですが、実際に取り組んでみると、多くのメリットがあると感じています。
僕が静かな退職を選んだ経緯
僕は現在30代後半の会社員で、東京都内のWEBサービスを運営する社員50〜100人規模の企業に約10年勤めています。
6年間、管理職として働いていましたが、1年前にその役職を降り、現在はプレイヤーとして業務を続けています。
管理職を降りた理由は、一言で言うと「自分の目指す方向性が変わったから」です。
40代以降もさらなる昇進を目指して管理職を続けることは、会社への依存度を高めることになり、僕にとってはワクワクする未来とは思えませんでした。
そんな中、副業や兼業を通じて、生き生きと働きながら収入を得ている人たちの存在を知りました。
例えば、好きなことを発信してブログやYouTubeで収益化する人、専門性を活かして会社の外でクライアントワークを行う人など、ひとつの会社の給与に頼らず、複数の収入源を持つスタイルに憧れるようになっていきました。
「キャリアは、みんなが同じ階段を登るものではない」と気づきました。
そこで、会社に拘束される時間を減らし、自分のために使う時間を増やしたいと考え、管理職を降りて「静かな退職」を実践することを決めました。

僕なりの静かな退職スタイル
「静かな退職」といっても、その形は人それぞれ異なります。僕が意識しているスタンスは
- 業務範囲外の仕事は避ける
- 責任の重い役割は避ける
- でも自身の業務はしっかりとやり遂げる
- 社内にやりたい仕事があれば積極的に手を挙げる
- 管理職への昇進は目指さないが、昇給は狙う
- 会社の人付き合いは必要最低限にする
- 会社の飲み会などの社交イベントは可能な限り回避
- 自席で雑談はしない
- でも話しかけられた場合はちゃんと対応する
- 会社の同調圧力には屈しない
といったところです。
社内ではできるだけ目立たず、しかし業務はきちんとこなすというバランスを保つことを意識しています。周囲からは「境界線を引きながらも、自分の仕事はきちんとこなしている人」と認識されていると感じます。

1年間実践して感じたメリット
管理職を降りたことも影響していますが、「静かな退職」を始めて最も実感したメリットは「やらなければならない」という受動的な時間が減り、「やりたいこと」に主体的に取り組む時間が増えたことです。
その結果、自己肯定感が向上し、日々を前向きに楽しめるようになりました。具体的には、以下のような変化を感じています。
- 残業が減り、会社を早く退社できるようになった
- 規則正しい生活ができ、体調が良くなった
- 人付き合いが最小限になり、職場の人間関係によるストレスが軽減
- 苦手な人と距離を取りやすくなった
- 雑談しないキャラが定着し、仕事に集中しやすくなった
- 「本当に必要な業務か?」と考える習慣が身につき、無駄な業務を削減できるようになった
- 自分が主体的に使える時間が増えた
これらのメリットにより、「静かな退職」は単なる手抜きではなく、人生をより充実させるための選択肢のひとつだと実感しています。
1年間実践して感じたデメリット
「静かな退職」のデメリットは、その人の目的や状況によって異なります。
例えば、出世を目指す場合は、周囲の期待値が下がることがマイナスになります。
一方で、プライベートの時間を重視する人にとっては、それがメリットになることもあるでしょう。
僕自身が実践して感じたデメリットは、以下のような点です。
- 業務範囲外の仕事をしないため、周囲からの評価や期待値が下がる
- 「仕事を頼んでも断られそう」と思われ、周囲から仕事を振られなくなる
- 貢献意識の高いチームメンバーとの間に温度差が生まれる可能性がある
- 静かな退職からいざ方向転換して出世を目指そうとしても、評価を取り戻すのに時間がかかる
- 中高年になった際、「働かないおじさん(おばさん)」認定される可能性がある
- 同期や後輩が上司になることもあり得る
- 会社のリストラ対象になりやすい
これらのデメリットを受け入れられるかどうかが、「静かな退職」を実践するうえでのポイントになるでしょう。
いま、感じていること
ここまで読んで、「静かな退職に興味はあるけど、デメリットも多そうだしやめておこうかな」と思った方もいるかもしれません。
でも、1年間続けてきた僕は、これからも「静かな退職」を実践していくつもりです。
一見デメリットが多く見えるかもしれませんが、取り組み方や前提条件、コツを押さえれば、心地よく続けることができる働き方です。
「静かな退職」は、働き方の一つの選択肢。もし現状にモヤモヤを抱えているなら、一度考えてみてはいかがでしょう。
以下、次章では僕が静かな退職を実践するうえで、大事だと思う指針や実践のコツについてお伝えできればと思います。よろしければ、ぜひご覧ください。
- 前向きに静かな退職をするための「3つの指針」
- 静かな退職を実践するための「5つのコツ」