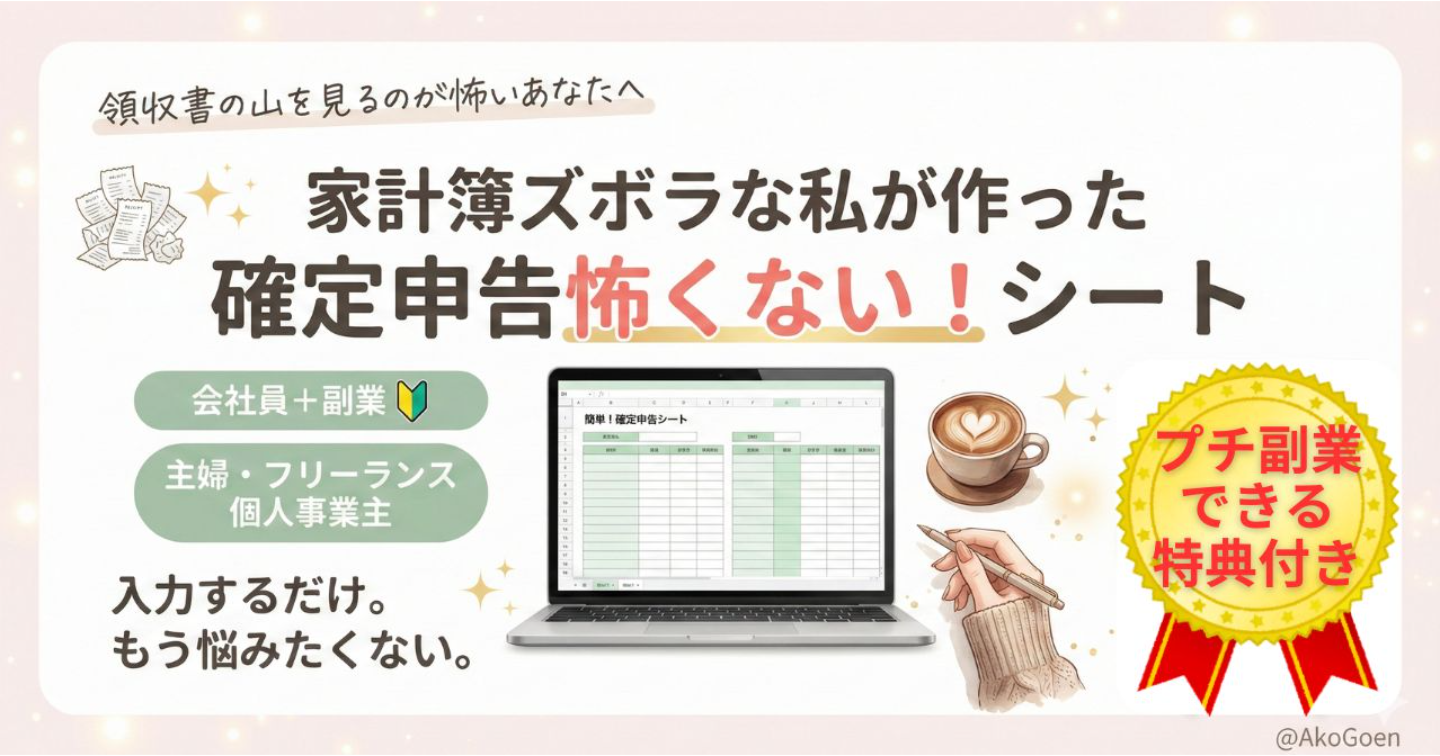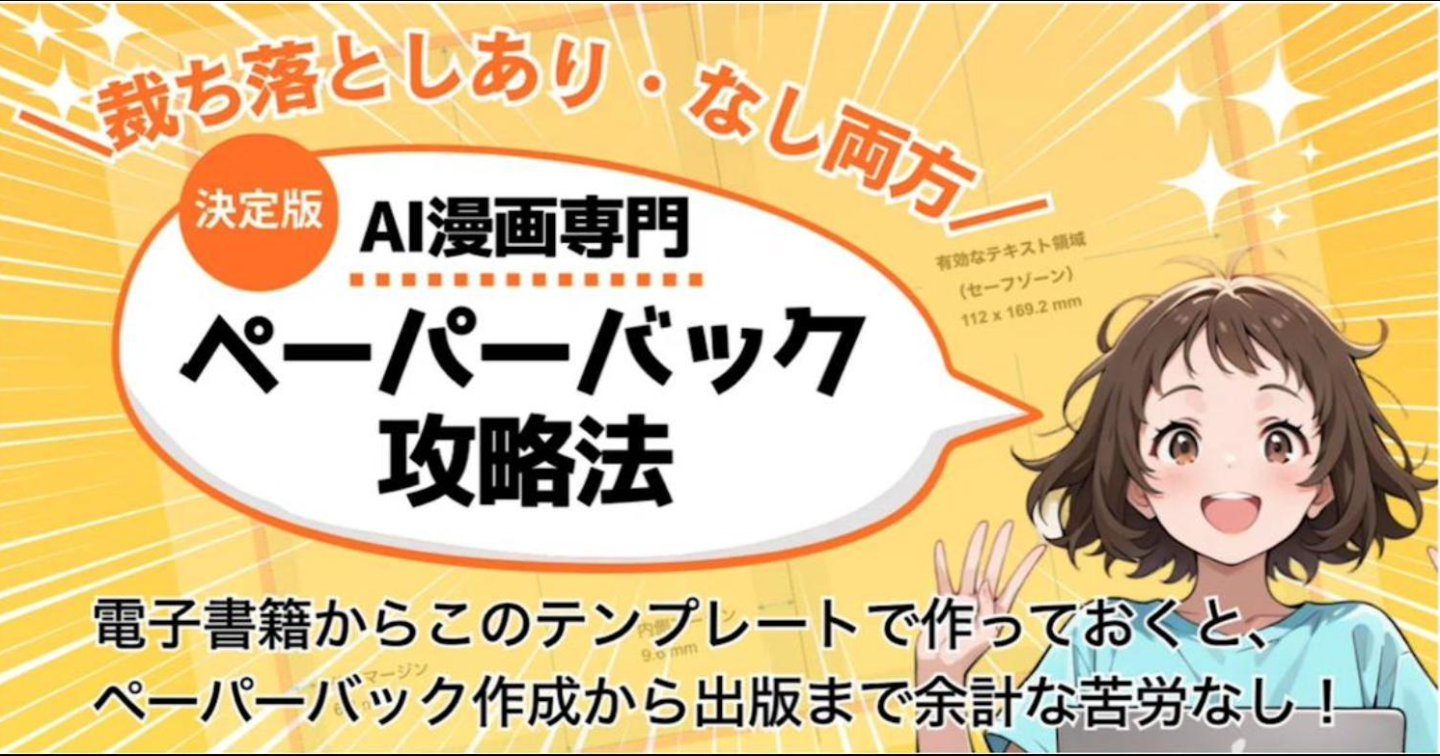『人間は完璧ではない』という言葉は、私たちの生活の真実を突いています。しかし、ヒューマンエラーの背後には、意外な心理や環境要因が隠れていることをご存知でしょうか?この記事では、その原因を解明し、効果的な対策を提案します。
今使っている品質不良対策の考え方は物理系に重点があって、
人為ミスの原因究明には使いにくいと考えます。
人為ミスは“心の動き”が原因となって発生します。
人間の心理作用に重点を置いた新しいアプローチが必要となってきます。
インシデントの原因と要因の判断をする
インシデントとは事故に至る可能性があったが、事故に至る前に未然に発見し、防止あるいは回避した場合のことをいいます。
主に人為的な要因によるインシデントを想定した解説をしていきたいと
思います。
まずインシデントが人為的なものかどうかを判断する基準としては
以下の2点がポイントになります。
インシデントが発生した場合には、
「すべきことをしなかった」か「すべきではないことをした」
2点のうちどちらかに該当するか否かを判断する必要があります。
ここで判断を誤れば、人為的な要因ではない問題に対して人為的な改善を
しようとしたり、環境や制度上の問題を放置する結果にもなりかねません。
人為的な要因によるインシデントの場合、
「すべきことをしなかった」か「すべきではないことをした」
という2点が考えられるわけです。
仮に「すべきことをした」あるいは「すべきではないことをしなかった」
にもかかわらずインシデントが発生した場合、そのケースは人為的な要因
というより環境的な要因や制度上の要因が考えられるからです。
例えば定められた手順やマニュアルを遵守した行動をとったのに
インシデントが発生したのなら、そこに人為的なミスはなく、
むしろインシデントが発生した当該現場の環境や定められた手順や
マニュアルの見直し・改善が求められます。
このような人為的な要因とはいえないインシデントに対して、
人為的な要因によるものとした改善を進めても有意義とはいえません。
場合によっては組織のスタッフが不満を抱える結果になるだけかも
しれません。
すべきこと=標準・ルール と考えてみてください。
※インシデント=不具合発生要因 と考えてみてください
インシデントの種類を分別する
インシデントの種類①「不足」
人為的なインシデントの中でも主に経験の浅い新人スタッフや業務内容が頻繁に変化する業務を行う際に多くみられるのが「不足」によるものです。
「不足」と言っても、経験が不足している場合もあれば、知識の不足や技能の不足など様々なものが考えられます。また、制度や取り決めに対する理解不足や認識不足も考えられるでしょう。
いずれにしても「不足」によるインシデントは、本来なら満たされているべき事柄に対する不足によって発生するインシデントのことであり、分析や対策を行う際には「何が不足していたのか」を定義し、それを補う対応が求められます。
インシデントの種類②「不遵守」
「不遵守」によるインシデントとは、その名のとおり手順やマニュアル、制度上の取り決め等を遵守しなかったことで発生する場合をいいます。
人為的な要因による2つのポイントである「やるべきことをしなかった」「すべきではないことをした」場合がこれに当たります。
つまり「不遵守」とは、「やるべきこと」を理解していることが前提にあり、理解しているにもかかわらず守らなかった場合のことです。
このラインより上のエリアが無料で表示されます。
インシデントの種類③「不注意」
「不注意」によるインシデントは、当該業務について知識や技能等を満たし、なおかつ手順等も遵守しているにもかかわらず発生するケースです。
単純に注意を欠いた場合がこれに当たります。
言い方によっては「注意不足」ともいえるため、①の「不足」とも内容が重複しますが、あえて差異をつけるとしたら知識や技能等の不足はないにもかかわらず起こる場合が不注意といえるでしょう。
重複しますが、あえて差異をつけるとしたら知識や技能等の不足はないにもかかわらず起こる場合が不注意といえるでしょう。
つまり「不注意」によるインシデントは、経験の浅い新人作業者だけではなく、経験豊富なベテランの作業者にも起こりえるケースといえます。
インシデントの種類④「疲労」
「疲労」によるインシデントとは、過酷な労働環境や多忙な業務環境で休憩がとれないなど疲労による原因によって発生するインシデントです。
前述した「不注意」などの背景には疲労が原因になっている場合もあるため、インシデントが発生した場合には背景要因として「疲労」が存在しないか考慮する必要があります。
当該インシデントに関わった作業者の労働環境や勤務実態などを考慮した上で、インシデントの対策と防止を進めることを要するかもしれません。
インシデントの種類⑤「錯覚」
錯覚」によるインシデントは、指示書の読み間違い等によって発生するケースです。
例えば手書きの指示書などを利用して複数のスタッフが関与する業務に多くみられるインシデントです。
数字やアルファベッドなどを誤って認識したり、確認した対象を「ない」のに「ある」としたり錯覚し思い込んでしまう場合などです。
「錯覚」によるインシデントを防止するためには、人間は錯覚する行動特性を備えていることを認識した上で、確認を怠らないことや表記方法を変更するなどの工夫をすることが重要です。
インシデントの種類⑥「欠陥」
「欠陥」とは業務遂行する上で必要とされる特質を欠いている場合のことです。
そもそも標準作業・ルールに対して注意をすることを全く考慮しない、業務遂行に対して著しく不適格な勤務態度などもこれに当たります。
①の「不足」との決定的な違いは、知識や技能等は不足していないことです。
また、②の「不遵守」との決定的な違いは、その行為を改める様子がみられない点です。
また「欠陥」として考えられるのは、当該業務について著しく素養を欠いてる場合なども考えられるかもしれません。
その場合には、当該作業者の再教育や配置転換等も考慮する必要があるでしょう。
インシデントの分析をする
インシデントの対策と防止を行うためには、インシデントの原因と背景を把握する必要があります。
もし仮に原因と背景を見誤ってしまえば、対策の立案と実施が真に有効な対策とはならないためです。
そのため、インシデントが発生した原因と背景を可能な限り正確に把握することが重要であり、そのためにもインシデントの分析は対策のために重要となるのです。
インシデントの分析では、発生した事象に至った経緯を把握する必要があります。
また、その業務に関与したスタッフによる業務の流れや他の作業者との業務の受け渡しなどの連携に問題は無かったかなどの事実の把握です。
この一連の把握には、主に「出来事流れ図」などの時系列による図を作成します。
この図では、発生したインシデントに至るまでの業務の流れ、関与した人物、使用した機器や設備等の情報を集約して行います。この図を作成する
作業では、関与した人物による報告または関与した人物へのヒヤリング等を行い、可能な限り経緯を明確にすることが大切です。
インシデントの対策をする
インシデントの対策を立案するためには、インシデントの原因となった解決すべき問題を明確にすることが大切です。そのため、対策の立案をするには、下図のような流れによって行うことが一般的となります。
インシデントの発生をどのように把握するのか。
まずここがハッキリとしていなければ、そもそもインシデントの対策は行うことができません。
一般的にインシデントの把握は、当事者や関係者の報告によって行われることが多いと思います。
しかし、必ずしもインシデントの発生を当事者が発見できるとは限らず、内容を正確に把握できるともいえません。
そのため、インシデントの発生をどのように把握し、事故に至ることをどのように防止するのかについて対策を立案する際には確認しておくことが重要となります。
また、そのインシデントは人的な要因によるものなのか、あるいは他の要因によるものなのかも明確にすることも重要です。なぜなら対策を立案する際に、事実誤認したまま進めれば対策案も的はずれなものになってしまうからです。
インシデントの対策案を立案する
インシデントの対策案を決定する際に注意が必要なのは、その対策案が有効な対策となり得るのか否かを吟味することです。例えば対策を行うインシデントが人的要因によるものだった場合、当該インシデントに関与した作業者への指導や教育を要することになるでしょう。
その際、インシデントに関与したスタッフは「なぜ」インシデントの発生につながるミスやエラーをしたのかを把握している必要があります。下図のように、一つのミスが原因だったとしても、複数の要因が考えられるからです。
例えば業務に関する知識が浅く、安全な業務を行うための知識を十分に持たない新人作業者の場合、知識教育を行うことが適切だったとします。しかし、そのような作業者に対して「なぜやらないのか」と責め、態度教育を行っても有意義な対策につながるとはいえません。逆に経験豊富で「やるべきこと」の知識もあり、それを行う技能も有する作業者に知識教育を行うのは必ずしも有意義な対策とはならないかもしれません。
大切なのは、インシデントの対策が適切なものであるかを十分に考慮した上で適切な対策案を立案することです。そうでなければ、その対策は「対策のための対策」となり、本来の目的であるインシデントの防止、その先にある事故を防止することに繋がっていかない可能性があります。
インシデントを防止する
インシデントの対策を立案して実行することによって、その対策がインシデントを防止するために有効な対策であるのか否かが判断できます。ここまで解説してきたインシデントの把握や分析、対策の立案は下図のPDCAサイクルにおける「プラン(plan)」つまり「計画」に過ぎません。
いわばインシデントの対策を立案することは「インシデントを防止できるのではないか?」という仮説に過ぎないということです。もしそうであるなら、仮説を実行し「検証」する必要があるのです。
インシデントの防止は対策の実行が「ゴール」ではなく「スタート」であるということになります。
対策を実行することによって、その結果を定期的に評価し、さらにその評価によっては改善を要するかもしれません。
重要なのは継続的な効果の追跡と絶え間ない改善のサイクルです。
インシデントを防止する方法は、この動的な活動の中にあり、その方法を知り得るのはインシデントの発生を防止しようとする現場のスタッフ一人ひとりの中にしかないのです。
インシデントとヒヤリハットは同じか
事故が発生すると、誰もがアクシデントと認識します。
しかし、その過程にはインシデントで食い止められる段階があったのです。
インシデントとアクシデントは別々の概念です。
アクシデントには必ずインシデントの段階が存在します。
そして多くの場合、そのインシデントに人は気づかないからアクシデントへと変わるのです。
たとえ誰も「ひやり」とも「ハッと」もしなくても、インシデントは起きている可能性があるということです。
品質というものを人々が最も強く認識するのは、品質が損なわれたときです。
平時に品質というものを意識することはもちろん可能です。
しかし人は、ときにその存在を当たり前に感じ、いつしか忘れてしまうものでもあります。
例えば夜空を見上げたとき、そこに無数の輝く星空が広がっている。
その星の一つ一つが「リスク」だとします。
しかしその星空は、夜が明けてしまえば見えなくなってしまう。
太陽の光によって明るくなったら、その星々は見えなくなり青空が広がる。
でも、その星々は見えなくなっただけであり、空の向こうにはいつも星はあるのです。
だから私たちは、その忘れてしまいがちな星、つまりリスクをいつも忘れずにいなければならないのです。
インシデントとヒヤリハットの違い
ヒヤリハットは文字どおり「ひやり」とした「ハッと」したというのが語源です。
その意味は、事故に至る可能性のあった出来事の「発見」です。
一方でインシデントは、事故に至る可能性のあった「出来事そのもの」であり、言い換えるなら事故に至らなかった出来事です。
一見するとヒヤリハットとインシデントは、ほぼ同義に見えます。
しかし、もし仮に「ひやり」とも「ハッと」もしないインシデントが起きたら、それはヒヤリハットなのでしょうか?
ヒヤリハットとは「ひやり、ハッと」とした出来事を発見したときに起きる人間側の感情です。
つまり人間の主観です。しかし同じ状況でも、人それぞれ感じ方は違います。認識も違います。
ヒヤリハットとインシデントが同義なら、インシデントも「ひやり、ハッと」している必要があります。
しかし、過去の事故事例をみると、「ひやり、ハッと」することもなくインシデントの状態に踏み込み、なおかつそれが重大事故まで発展しているケースが多々あります。
インシデント=ヒヤリハットという認識によって、「ひやり、ハッと」しない状態を、人は安全もしくは平常状態だと誤認をする可能性があります。
「出来事そのもの」と「発見すること」は異なる概念です。
注意が必要なのは、これらの概念を同一視し、主観で認識できない問題を見落とすことです。
ヒューマンエラーの原因を考える視点
13のメカニズムの定義