この記事では、「托卵(たくらん)」という行為がなぜ発生するのか?そして、女性はそれを「悪いことだと認識しない」のかを解説する。
レイプと托卵、魂の殺人という共通項
レイプは、女性の尊厳を踏みにじる最悪の暴力である。泣き叫ぶ女を押さえつけ、拒絶を無視し、力で貫く。その瞬間、男は人間性を捨て、女は「自分であること」を失う。肉体は生きていても、魂が殺される。だからこそ、人々はそれを「魂の殺人」と呼ぶのだ。
だが──。男の魂を殺すのは、レイプではない。それは、托卵である。
托卵とは何か —— “知らぬ間に殺される”構造的裏切り
托卵とは、他の男の子を孕んだ女が、その事実を隠して夫に育てさせる行為だ。夫は何も知らず、「愛する妻の子」と信じて人生をかけて養う。しかしその子は、自分の遺伝子を一滴も受け継いでいない。
男は死ぬまで気づかないかもしれない。だが、真実を知った瞬間、彼の中で何かが確実に死ぬ。誇りも、信頼も、そして自分の人生の意味さえも。これこそ、男にとっての“魂の殺人”である。
「托卵って、何が悪いの?」という女たち
SNSを覗けば、こうした声があふれている。
「托卵って、何が悪いの?」「誰の子でも愛して育てればいいじゃん」「自分が愛してる妻の子なら、父親が誰でも関係ないでしょ」「誰の子でも“俺たちの子”として受け入れる器が欲しい男が好き」「托卵されたくらいで怒る男、器小さすぎ」https://lasisa.net/post/70610
この発言群は決してネタではない。彼女たちは、理性ではなく本能でそう感じている。そして、それこそが托卵の恐ろしさである。
托卵は人類史に組み込まれた行動である
そもそも托卵は、どの程度発生しているのだろうか?
客観的な研究が、それらを推定している。結果は驚くべきものだ。
1997年の研究では、父親が自分の子だと思って育てている子どものうち、9〜17%が実際には別の男性の子であることが報告されている。
“Our parallel analyses of Euler and Weitzel’s (1996) data on grandparental investment suggest a similar estimate, that paternity uncertainty lies between 9% and 17%.”Anderson et al., 1997, “Matrilateral biases in the investment of aunts and uncles
つまり、托卵は例外的な逸脱ではなく、人類の進化史に組み込まれた行動様式なのだ。「愛の裏切り」ではなく、「遺伝子の戦略」。それが托卵という現象の冷徹な本質である。
そもそも研究では「サピエンスのメスは、そこそこ浮気性」であることが知られている。
これは、我々人類がたまに浮気をしながら合理的に子孫繁栄していた客観的な証拠なのだ。

なぜ女性は托卵をするのか — 二重の繁殖戦略
これまで女性は托卵を「悪」と認識しないのでは?と述べてきた。
そのまま主張を展開しても良いが、少し肩を持つことにする。
人間の赤ん坊は、他の霊長類に比べて極めて未熟な状態で生まれる。自力で立てず、母親一人では生存を保証できない。そのため女性は、単に「誰の子を産むか」だけでなく、「誰に育てさせるか」までも戦略的に考えるように進化した。
その結果、女性は二つの男を使い分けるようになった。
- 遺伝的に優れた男(イケメン・高地位・強者)から精子を得る
- 安定して資源を提供する男(誠実・経済力)に子どもを育てさせる
この構造こそが、托卵という繁殖戦略の生物学的ロジックである。
“Human infants are born at a remarkably altricial stage, requiring prolonged parental investment.This dependency shaped the evolution of cooperative breeding and paternal care, making mate choice and paternal uncertainty central evolutionary pressures.”Hrdy, S. B., 2009. “Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding”
女性は「誰と愛するか」だけではなく、「誰に育てさせるか」を選ぶ。この二重の選択が、ヒトという種を繁栄させてきた一方で、現代社会では“倫理の崩壊”として現れるのだ。
そしてこれは都合が悪いことに「女性の遺伝子のテキストに刻まれた、適応的な遺伝子拡散戦略」なのだ。
ちなみに補足だが、これは「気になる女性が現れたら、その女性とおともだちになるような形式でアプローチを仕掛けることは悪手(フレンドシップ戦略)」の進化心理学的理由だ。

女性は「種オス」と「育てオス」を早い段階で嗅ぎ分けるので、おともだちになるような戦略でアプローチしたら、復活できなくなってしまうのである。
女性は托卵を「悪」と感じない理由
つづいて、別の観点から女性が托卵を「悪」だと感じないことを論じようと思う。
ここで述べることは、例えば学生時代 小中学校とかでよく見たやつだと思う。納得感持って読み進められるはずだ。
1. 社会的バイアスによる“免罪”
2018年の教育心理学研究によると、女子生徒によるいじめは教師に発見されにくく、男性が同じことをすれば問題視される傾向がある。
https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/berj.3324
また、男女の嘘の動機に関する研究ではこう報告されている。
“Participants told relatively more self-centered lies to men and relatively more other-oriented lies to women.”DePaulo et al., 1996. “Lying in Everyday Life”
つまり、社会は女性の嘘に「優しい」。それが托卵という裏切りを“心理的に軽く”している。
2. 涙を使った操作 —— 「被害者」になる才能
1987年の研究「Tactics of Manipulation」では、女性は男性よりも頻繁に“泣く・悲しむ・弱さを見せる”といった戦術で他人を操作することが確認された。
“The item ‘He or she whines until I do it’ showed greater female than male performance frequencies.”Buss & Shackelford, 1987. “Tactics of Manipulation”
女性は本能的に「守ってもらう戦略」を持つ。その涙が、時に倫理を曇らせ、悪事を「愛の延長」として包み隠す。
これらの「女性は甘く評価される」という認知バイアスを「女性は素晴らしい効果(Women are Wonderful Effect)」と言う。

托卵の合理性 —— 父性の不確実性という罠
女性が複数の男性と関係を持つことで、複数の男性が「自分の子かもしれない」と思い、母子に投資する。この構造は“父性の不確実性”と呼ばれる。
母親のベイビーは、父親のメイビーなのだ。
進化心理学的には、これは母子の生存率を高める合理的戦略である。だが同時に、男の人生を奪うシステムでもある。
“Our results support theoretical predictions that social context can strongly affect the outcomes of sexual conflict in human populations.”Larmuseau et al., 2019. “A Historical-Genetic Reconstruction of Human Extra-Pair Paternity”
托卵は、倫理的には罪であり、進化的には成果である。この矛盾こそが、男女の永遠の悲劇を生む。
托卵を防ぐために —— 男性が知るべき真実
- 格上であり続けること女性は本能的に「格上の男」を求める。優しさだけでは惹かれない。誠実さに加え、“支配する強さ”を持つことが必要だ。
- 環境を選べ托卵率は、都市部・低所得層ほど高いことが知られている。https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(19)31305-3
- 生物の裏切りは、ストレスと機会が交差する場所で起こる。男は、女だけでなく「環境」も選ばなければならない。

女性への忠告 —— 理性で本能を制御せよ
托卵は動物的には合理的だが、倫理的には最悪である。それを「仕方ない」と笑う女は、進化に飲み込まれているにすぎない。理性を持つ人間ならば、その本能を制御しなければならない。
もし「他の男の子どもが欲しい」と思った瞬間があるなら、それは愛ではない。支配欲か、逃避だ。托卵は、誰も幸せにしない。男の魂を殺し、子どもの未来を汚し、女自身の尊厳をも奪う。
もし、パートナーがいるにも関わらず他の男性と性行為をしたいと思ったら、幸せにはなれないから パートナーを捨てるべきだ。
加えて托卵がバレたら、自分の生命を失うほどのリスクがあることも付言しておく。
結論:本能を理解し、理性で超えろ
托卵は、進化が生み出した最も冷酷で美しい戦略である。だが、理性なき戦略は、ただの破壊だ。人間とは、本能を理解し、それを超える存在であるべきだ。
本能を理解することは、正当化のためではない。理性によって制御するためだ。「愛」と「裏切り」の境界線を越えないことこそ、我々が人間である証だ。
参考文献
- Anderson et al. (1997). Matrilateral biases in the investment of aunts and uncles
- Hrdy, S. B. (2009). Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding
- DePaulo et al. (1996). Lying in Everyday Life
- Buss & Shackelford (1987). Tactics of Manipulation
- Larmuseau et al. (2019). A Historical-Genetic Reconstruction of Human Extra-Pair Paternity





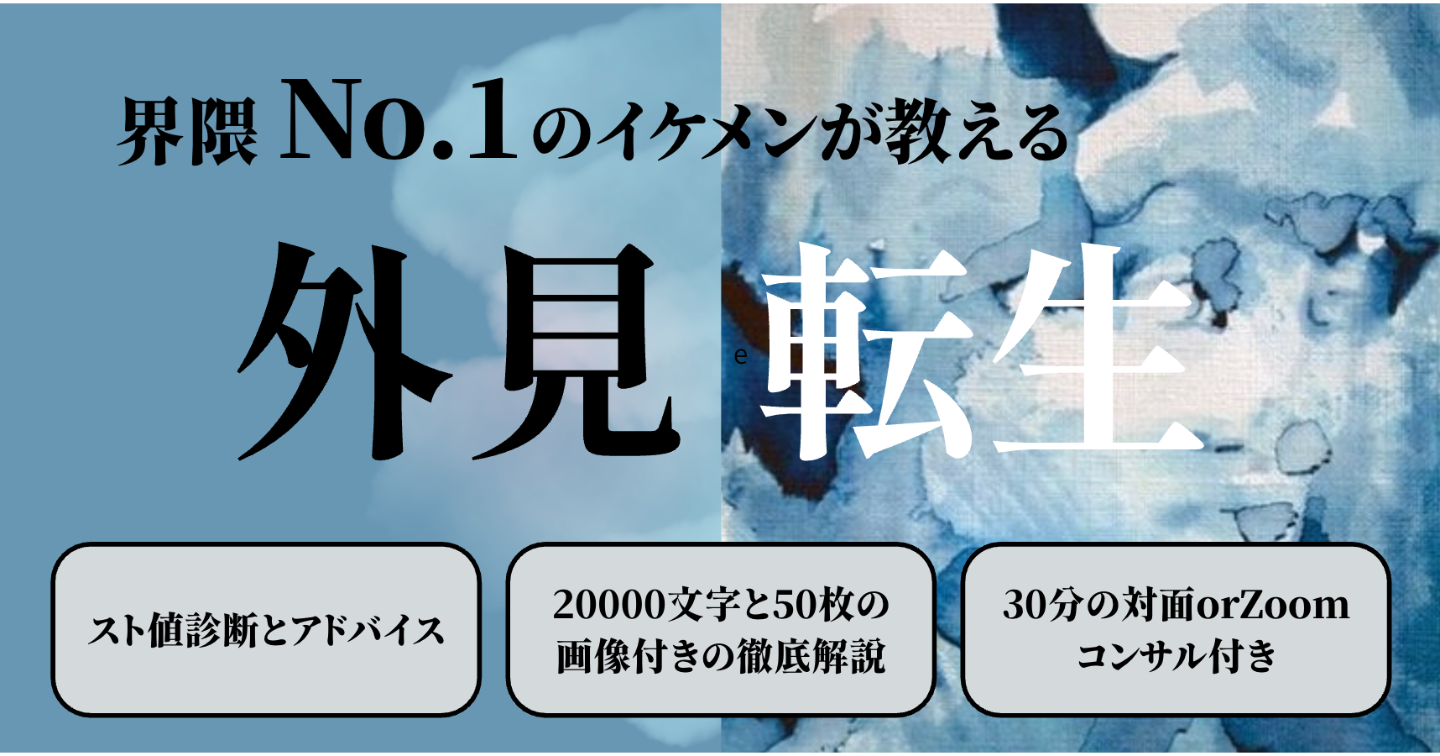

![[限定販売]対美女コミュニケーションの真髄~再現性のその先へ~](https://static.tips.jp/2024/10/28/tWkUPZsqmXXXgjYfJe0hqADwErHoGD4V.png)

