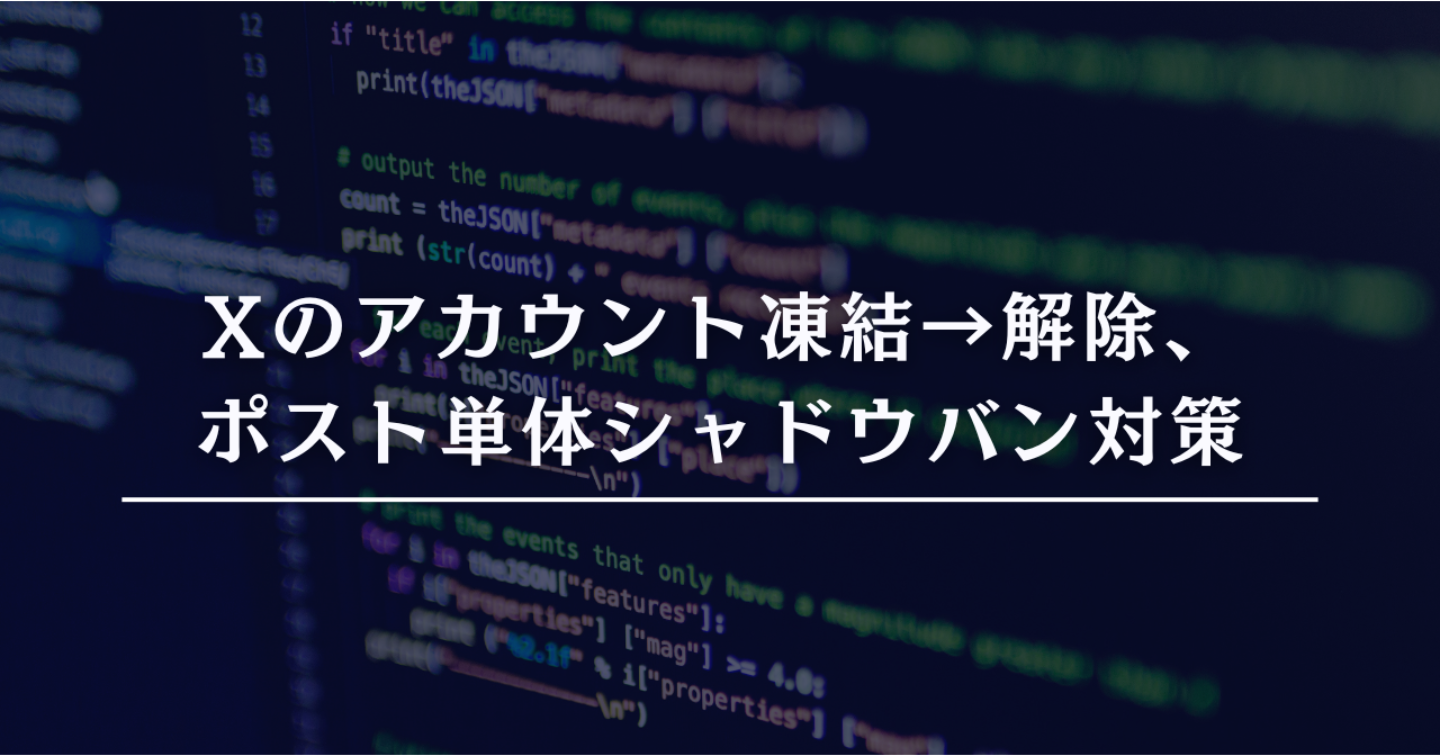まえがき:英雄は、崩れるべくして崩れる
歴史は勝者の物語である──などという決まり文句があるが、それは必ずしも真実ではない。 実際には、勝者の“演出”によって脚色された物語であり、その脚本は時代のニーズに応じて、都合よく書き換えられてきた。
織田信長という人物もまた、そうして生まれた「物語」の犠牲者であり、利用者であり、そして最終的には“商品”となった存在である。 彼の名は「革新」「合理主義」「恐怖政治」「文化人」など、ありとあらゆるラベルで飾られ、21世紀の今なお“語るに便利な人物”として機能している。
だが、この論考が挑戦するのは、その便利なラベルを一枚ずつ剥がし、 信長という「孤独な組織の管理者」の実像を浮かび上がらせることである。
本稿は、織田信長の英雄神話をなぞるためのものではない。 むしろ、その神話がいかに不安定な幻想であり、 彼の支配がいかに内側から静かに瓦解していったかを、一つひとつ丁寧に検証することを目的とする。
信長を“尊敬すべきリーダー”として語り続けることは簡単だ。 だが、それではいつまで経っても、人間関係の本質、組織の力学、そして権威の終焉について、私たちは何も学べない。
本書は、信長に対して冷笑を投げかけるものではない。 ただし、無批判な崇拝には、一滴の皮肉を垂らしておく必要があると考える。 それが、思考を止めないための礼儀である。
第一章:信長と“軽視されるリーダー”という逆説
「織田信長」と聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは何だろうか。 冷酷非情な戦国の革命児。旧来の秩序を打ち壊したカリスマ。火を以て寺社を焼き払った恐怖の権化。そして、天下統一目前で家臣に裏切られた悲劇の男。そうした印象が、いずれも間違っているとは言わない。だが、果たしてそれは「実像」だったのか。あるいは「後世が作り上げた神話」だったのか。
仮に、信長が「家臣にバカにされていた」としたら──。 その一文だけで、歴史好きは顔をしかめるかもしれない。だが、そう反射的に拒絶する前に、少し立ち止まって考えてみるべきだろう。歴史の表舞台で「絶対的カリスマ」として描かれる人物たちも、日常においては部下に煙たがられ、時には陰口を叩かれ、笑いものにされることもある。それは現代の組織でも同じである。むしろ、上に立つ者ほど、下からの視線は冷ややかだ。理由は簡単だ。「上司だからといって、人格者とは限らない」からである。
では、信長は本当に「尊敬されていたのか」? それとも「恐れられていただけ」なのか?
こう問うたとき、私たちはリーダーシップという概念の根本にぶつかることになる。信長が有能であったことと、信長が好かれていたかどうかは、まったく別の問題なのだ。 そして多くの場合、こうした人物は「評価されながらも、心の底では舐められている」という二面性を抱えている。信長もまたその例外ではなかった可能性がある。
もちろん、正面きって「信長はバカだ」と言った家臣はいなかっただろう。だが、内心ではどうだったか。家臣たちは皆、信長の機嫌を伺いながら忠誠を誓うふりをしつつ、陰ではその言動を冷笑していた。そんな仮定は、決して荒唐無稽ではない。むしろ、人間の組織の中では自然な力学である。
たとえば、信長が「うつけ」と呼ばれていた若き日々。表向きは狂ったように踊り、奇抜な服をまとっていたが、それが戦略だったというのが通説だ。しかし本当にそうだったのか? 周囲が「これは計算され尽くした仮面だ」と考えていたとすれば、ある意味では信長の思うつぼだが、仮に「本当に頭がおかしいやつ」と思われていたとすればどうだろう。それでも家督を継ぎ、やがて尾張を支配するようになった。ならば、その「誤解される能力」こそが、彼の武器だったのかもしれない。
この逆説──「バカにされる信長」──こそが、彼のリーダーとしての実像を探るうえで重要な視点である。 つまり、信長は「尊敬」ではなく「誤解」と「恐怖」で人を従わせていたのではないか。カリスマという言葉が後から貼られたラベルに過ぎないとしたら、そこにはリーダー像の大いなる虚構が浮かび上がってくる。
そして皮肉なことに、信長が最後に倒れたのは「外敵」ではなく「身内」、すなわち最も信頼していたはずの家臣であった。明智光秀による本能寺の変。 これは、ただの裏切り劇ではない。長年にわたって積もり積もった「軽蔑」と「反発」の結果だと考えるならば、その真相はきわめて人間臭いものとなる。つまり、信長は家臣にバカにされながらも、最後までそれに気づかなかった──あるいは、気づいていたが、舐められた自分を認めたくなかった──そんな男だったのかもしれない。
この連載では、「バカにされる信長」という一見不遜で不敬な仮定を通じて、カリスマ、権威、リーダーシップ、そして組織の本質について、冷静に、かつ皮肉を交えて考察していく。 時に歴史の文献を引用し、時に現代の企業社会と対比しながら、「絶対的存在に見える者の脆さ」を浮かび上がらせたい。
さて、神格化された信長の足元に、そろそろ人間の影を照らしてみようか。
第二章:「カリスマ」は幻想か:見た目と現実のギャップ
「カリスマ性」という言葉ほど、現代においても誤解されやすく、かつ便利に使われる概念はない。テレビのコメンテーターが「彼にはカリスマ性がある」と口にすれば、それだけで対象は何らかの特別な存在として認識されてしまう。だが、その中身がどのようなものかを問われたとき、多くの人は言葉に詰まるだろう。派手な服装か? 演説のうまさか? 一目置かれる存在感か? 答えはすべて「イエス」であり、同時に「ノー」である。
織田信長もまた、この「カリスマ」という概念の中で語られることが多い。だが、ここで疑問を持ってみたい。信長は本当にカリスマだったのか? それとも「カリスマらしく見える」ように、後世の史観が仕立て上げた存在なのか?
まず見た目から検討してみよう。信長は奇抜なファッションを好み、南蛮風の装束を着て金平糖を好み、天守閣の上から天下を見下ろすような絢爛豪華な城を築いた。派手好きだったことは間違いない。しかし、それを「カリスマ性の表現」と捉えるのは、いささか短絡的ではないか。なぜなら、奇抜さは尊敬を生むとは限らないからだ。むしろ滑稽に見えるリスクの方が高い。
現代でも、カリスマ経営者と持ち上げられる人物の中には、よく見ると単に「風変わり」であるだけの者も多い。個性と奇行の区別がつかない時代、人はしばしば「理解できないもの」に価値を見出そうとする。だが、信長の「異質さ」が尊敬を集めたのではなく、むしろ嘲笑や侮りの種になっていた可能性はないのだろうか。
実際、信長の言動は家臣たちにとって「読めないもの」だった。読めないリーダーは、時に畏怖の対象となり、時に軽蔑の対象となる。どちらに転ぶかは、その場の空気と集団心理による。たとえば、「ある日突然、仏閣を焼き払う」といった過激な行動は、外から見れば革命的でも、内側にいる者からすればただの暴走と映る。家臣たちは「また始まった」と内心で呆れていたかもしれない。表では忠誠の姿勢をとりながら、裏では「我が殿は血の気が多すぎる」と茶化していた可能性もある。
さらに、信長のカリスマ性とされる「決断力」や「非情さ」は、現代のマネジメント理論で言えば「コンプライアンス違反」と見なされかねない類のものである。気に食わない相手を殺し、協調を拒み、合理性を振りかざして感情を排除する。こうした姿勢が一定の成果を上げたとしても、組織の中では摩擦を生みやすい。つまり、信長が結果を出していたことと、彼が本当にリーダーとして敬われていたかどうかは別問題である。
そして何より皮肉なのは、「カリスマ」があったからこそ、家臣はその下で働いたのではなく、「そのカリスマに耐えられなかったからこそ」反旗を翻したという点である。本能寺の変は、信長の強権によって忠誠を強いられた家臣が、その圧に耐えきれず爆発した結果だった。つまり、彼の「カリスマ性」が崩壊の原因だったのだとすれば、それはもはや「成功要因」ではなく「失敗要因」として再定義されるべきである。
このように、カリスマとは幻想である。見た目や雰囲気で語られるそれは、実体のないオーラに過ぎず、周囲の認識によって成立しているにすぎない。信長が「カリスマ」と呼ばれるのは、彼が死んだあとに語られた物語が、それを必要としたからである。だが、現実の彼は、むしろ部下たちにとって「扱いにくい存在」であり、時に笑い者であり、時に恐怖の対象であり、そして最終的には「いなくなった方がマシ」と思われた、そんな存在だった可能性がある。
信長という存在は、まるで現代のSNSでバズったインフルエンサーのようだ。フォロワー数は多いが、実際に慕われているかどうかは分からない。派手な発言で注目を集めても、その裏では「あいつまた言ってるよ」と冷ややかな目が向けられている。だが、注目が集まる限り、表面的には「成功者」として扱われる。信長もまた、そのような虚像と実像のあいだで生きていたのではないか。
カリスマの本質とは、「周囲がそのように見ようとした幻想」であり、本人の資質とは別の次元で成立するものである。 信長が本当に家臣から敬愛されていたかどうかは疑わしい。 しかし、「敬われていたように見えた」ことが、すべてを正当化している。 このギャップこそが、リーダー像の持つ最も危うい点だ。
第三章:織田家中の内情:忠誠心と裏腹の軽蔑
組織において、上司と部下の関係が「信頼と尊敬」で成り立っているというのは、理想論でしかない。実際には、忠誠の仮面の裏に軽蔑が潜み、表向きの服従が裏切りの予兆であることは、珍しくも何ともない。戦国時代の武家社会も、現代の企業も、そうした構図の延長線上にあるにすぎない。
織田家の家臣団は、しばしば「精鋭ぞろい」と称される。木下藤吉郎(豊臣秀吉)、柴田勝家、丹羽長秀、明智光秀、滝川一益……その名前を並べるだけで、日本史の教科書が数ページ進みそうな顔ぶれである。だが、信長が彼らを選んだというよりも、「彼らが信長を利用できると判断したから仕えた」という側面も否定できない。つまり忠誠は「打算」であり、「崇拝」ではなかった。
事実、当時の家臣団にとって、主君とは「敬うべき人格」ではなく、「出世の踏み台」であることが多かった。信長の下に集まった面々もまた、彼を通じて自らの地位を築こうとした人々である。その証拠に、彼らの動きは極めて現実的だ。たとえば、信長が勝ち進むにつれて、彼の配下に入る武将が増えたが、それは信長の理念に共鳴したからではなく、「今はこの男に従った方が得策」と計算した結果に過ぎない。
では、その「忠誠」はどれほどの強度を持っていたのか。答えは明らかだ。信長が絶対的優位に立っていた間は、誰も逆らわなかった。だが、その威光に陰りが見えた瞬間、家臣たちの忠誠は蜘蛛の糸のように脆く崩れる。これは、単なる結果論ではない。すでに信長の治世下においても、その兆候は見えていた。
たとえば、柴田勝家は信長に仕えつつも、たびたび命令に背くような動きを見せていた。滝川一益も、自身の裁量で勝手な動きをとることが多かった。彼らの行動を見れば、主君の命令は「命令」ではなく、「相談」に近かったのではないかとさえ思える。信長は一見して独裁的に見えるが、その実、家臣団に強く出られない場面も多く、特に軍事行動においては「勝手連」的な状況が散見された。
また、明智光秀の台頭も、興味深い現象である。もともと外様でありながら、信長の信頼を得て重用されたが、その過程において周囲の家臣たちはどう見ていたのだろうか。出世競争のライバルとして警戒しつつ、内心では「信長は人を見る目がない」と冷笑していた者もいただろう。つまり、家臣同士の関係も信長に対する態度に影響を与え、相互の牽制と軽蔑が渦巻いていたと考えられる。
さらに、信長の強権的な政策に対して、表向きは服従していた家臣たちも、陰では不満を抱いていたことは容易に想像できる。寺社の焼き討ちや一向一揆への弾圧など、宗教的な背景を持つ家臣にとっては、精神的に受け入れ難い命令だったはずだ。だが、逆らえば粛清される。ゆえに、表向きは従いながらも、内心では「我が殿は狂っている」と思っていた可能性は高い。
また、信長は家臣に対して報酬を与える一方で、その成果に対する要求も高かった。結果を出せば褒美、失敗すれば叱責か処罰。この単純な構図は、短期的には効果を上げるが、長期的には疲弊と反感を生む。家臣たちは次第に、「信長のために働いている」のではなく、「自分が生き延びるために働いている」だけの存在になっていった。
皮肉な話だが、忠誠の最たる形として語られる家臣たちの行動は、多くの場合、信長という人物に対する敬意よりも、「信長体制の中でいかに自分の立場を守るか」というサバイバルの産物だった。そして、その構造こそが、信長のリーダーシップの危うさを物語っている。
すなわち、信長の支配は、強烈な光を放ちながらも、その足元には常に軽蔑と反感の影が落ちていたのである。