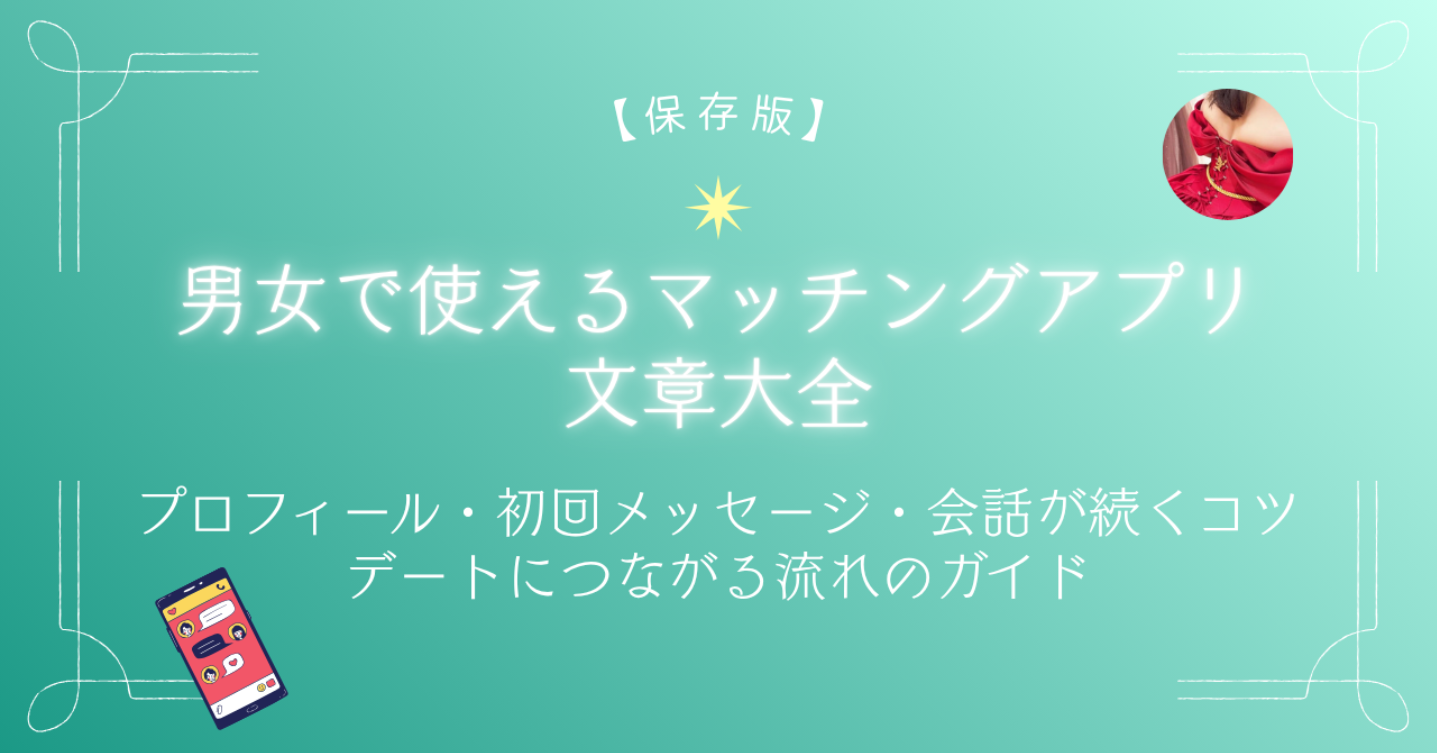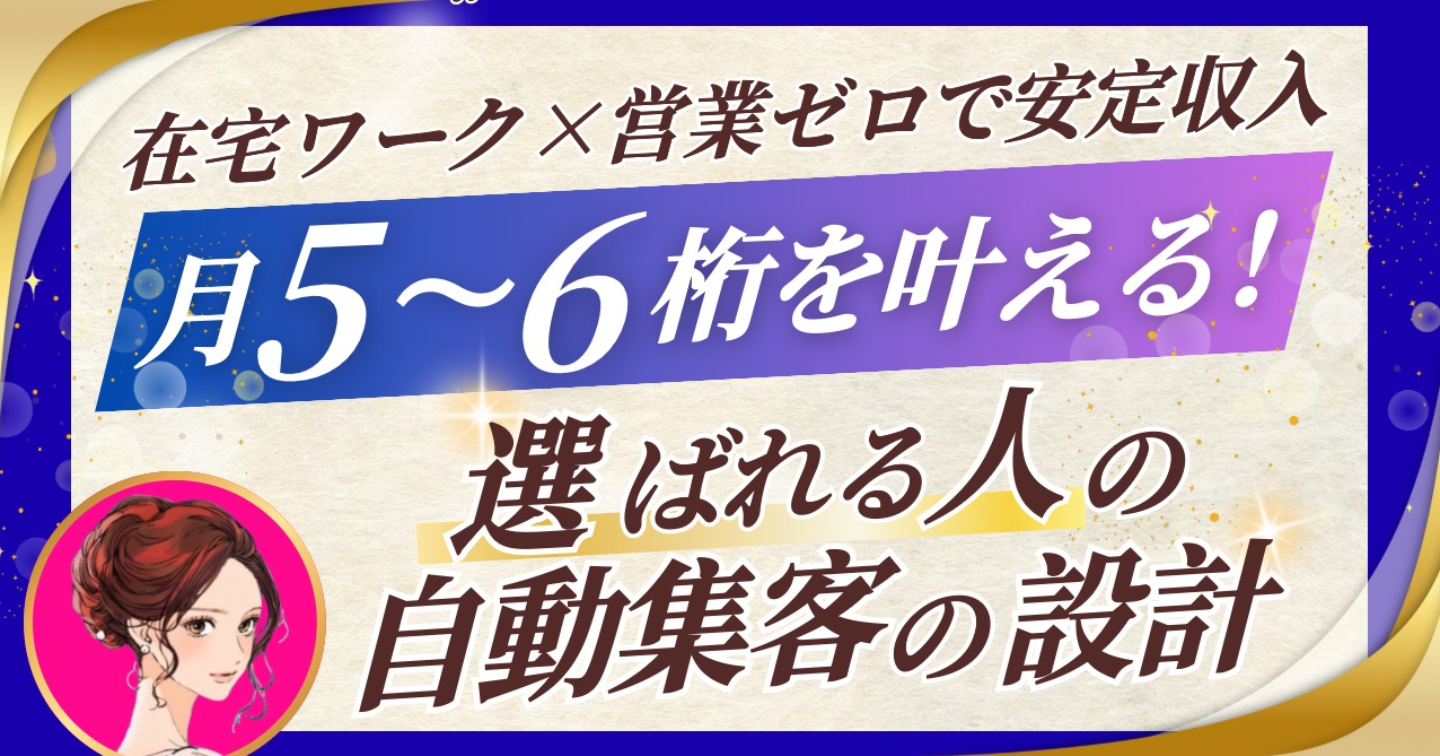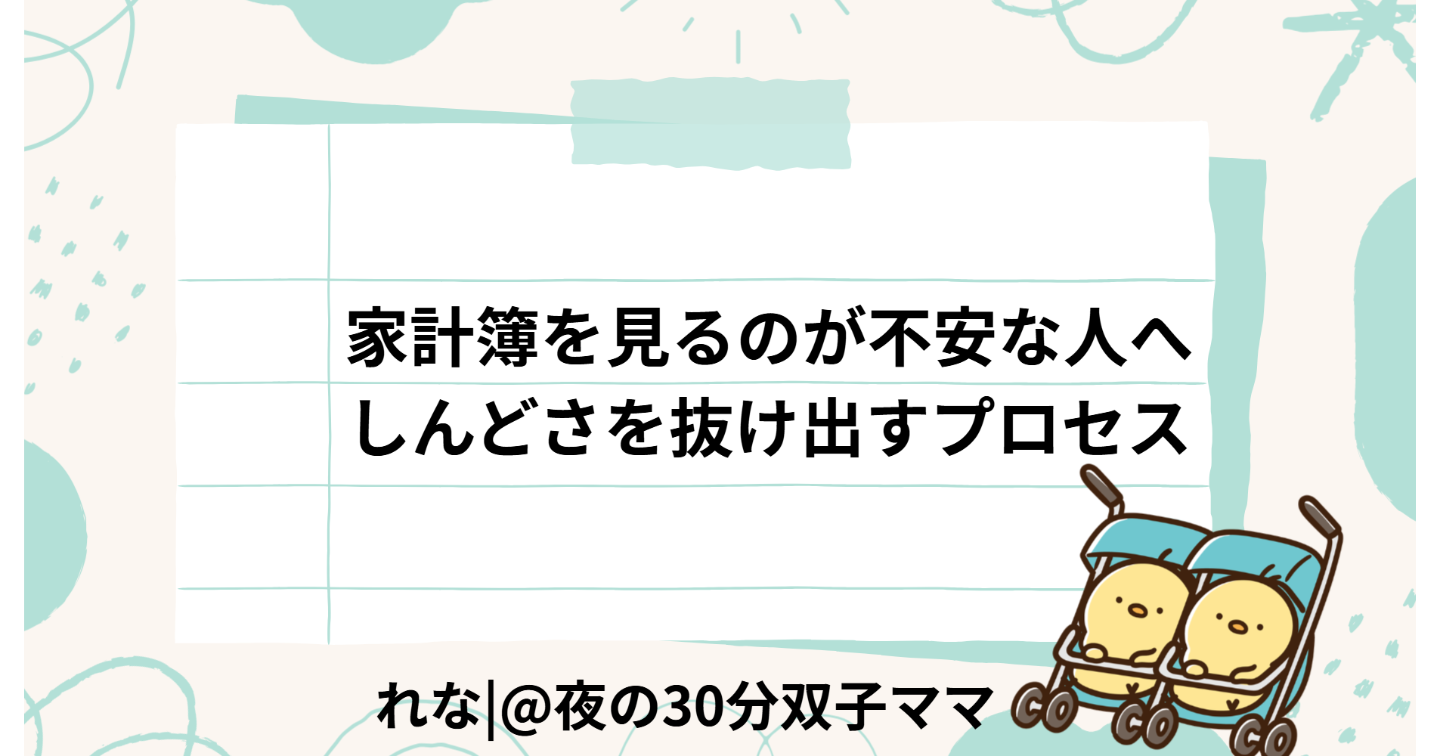第1話: いつもの日常と呼び止められた瞬間(全10話)
注意
本連載は筆者の実体験をもとに、一部脚色・変更を加えて構成しています。特定の店舗・業者・業界を非難したり、違法行為や詐欺行為を断定・告発する意図はありません。記載内容はあくまで個人の体験と感じ方に基づくものであり、すべてのケースに当てはまるものではないことをご理解ください。本記事が、似た状況に遭遇した際の判断材料や冷静に考えるきっかけの一つになれば幸いです。
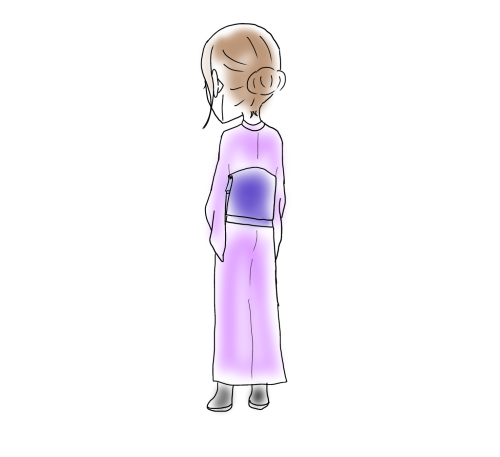
子どもの頃から慣れ親しんだ町がある。今はもう住んでいないけれど、観光地として日本中に知られていて、季節ごとに名前がニュースに出るような場所だ。思い出補正もあると思う。でも私は今でもその町が好きだ。
事件が起きたのは、そんな「好きな町」でのことだった。
その日は午後から、少し改まった用事があって、朝から着物を着て外に出た。私の家では、着物は特別な服というより、ちょっと良い普段着みたいな扱いだった。着物で散歩も、着物で買い物も珍しくない。だからその日も、紫がかった地色の着物に、帯は気持ちゆるめ。寒かったのでブーツを履いていた。
名所から一本外れた通りを歩いていると、小さな呉服屋が目に入った。ガラス越しに反物が数点、きれいに並んでいる。普段なら通り過ぎる店だ。ところがその日は、入口に立っていた男性店員が、妙にタイミングよく声をかけてきた。
「お客様、そのお着物、とてもお似合いですね」
声がやけに通る。色、帯、足元。褒め言葉が細かすぎて、少し居心地が悪い。
「よろしければ、1階の展示だけでも見ていきませんか?本当に、見るだけで大丈夫ですから」
予定は午後から。時間はある。それに、観光地価格で売るような店でもなさそうだった。私は軽い気持ちで、店の中に入ってしまった。
店内は思ったより狭く、照明が暗めだった。羽織と着物が数点、壁にかかっているだけ。音が吸い込まれたみたいに静かで、客の気配がない。いるのは、私とその男性店員だけ。
店員は距離を詰めるのが上手だった。私の着物の横に、棚から取り出した反物を並べる。
「ほら、地色が似てますでしょう?こういうお好みなんですね」
確かに似ている。でも、私はこういう褒め方が苦手で、うまく反応できない。苦笑いをしていると、店員はさらに勢いづいた。
「実はですね、近々、特別な展示会がありまして」
数日後、有名な芸術書に名前が載るようなデザイナーが来店するらしい。反物の単価は百万円以上。招待状がないと入れない、限定イベント。そしてなぜか、「お客様みたいな方に、ぜひ」と続く。
興味はなかった。むしろ、断らないと帰れない空気を感じていた。
「買う予定はないので……」
そう言うと、店員は笑顔のまま目を細めた。
「もちろんです。買わなくていいんです。ただ見るだけ。それに、当日はそのデザイナーが、その場で足袋にワンポイントを描いてくれる企画もあるんですよ」
足袋。値段は足袋代だけ。五百円。
白足袋は、確かにそろそろ替え時だった。買う予定のものを、別の形で買うだけ。そう考えてしまった。

「じゃあ、招待だけなら……」
条件は念押しした。着物は買わない。見るだけ。
店員は、待ってましたと言わんばかりに、はがきを差し出した。後日、招待状を送るからと、名前と住所を書くように言われた。
書き終えると、彼はそれ以上何も言わなかった。「お待ちしています」とだけ。
店を出た瞬間、急に空気が軽くなった。同時に、嫌な予感が胸の奥に残った。
なんで入ったんだろう。なんで書いたんだろう。
大好きな町で起きた出来事なのに、その日の帰り道だけは、少しだけ景色がくすんで見えた。
【詐欺で使われることもある心理的な誘導構造】好意の返報性+フット・イン・ザ・ドア。着物を褒めまくり好印象を与え、低額(足袋500円)の小さなYESを取ってから徐々に大きな契約へ誘導する典型だそうです。
※ここでいう「詐欺の手法」とは、法的に詐欺だと断定する意味ではありません。一般的に悪質な勧誘や詐欺的行為の解説で用いられる心理的な考え方を、当時の自分の体験に照らし合わせて振り返っていることをご理解ください。
【今振り返って】あの時「めんどくさい」と思った直感を信じて断っていれば…と今でも本当に後悔しています。