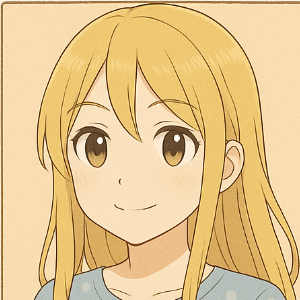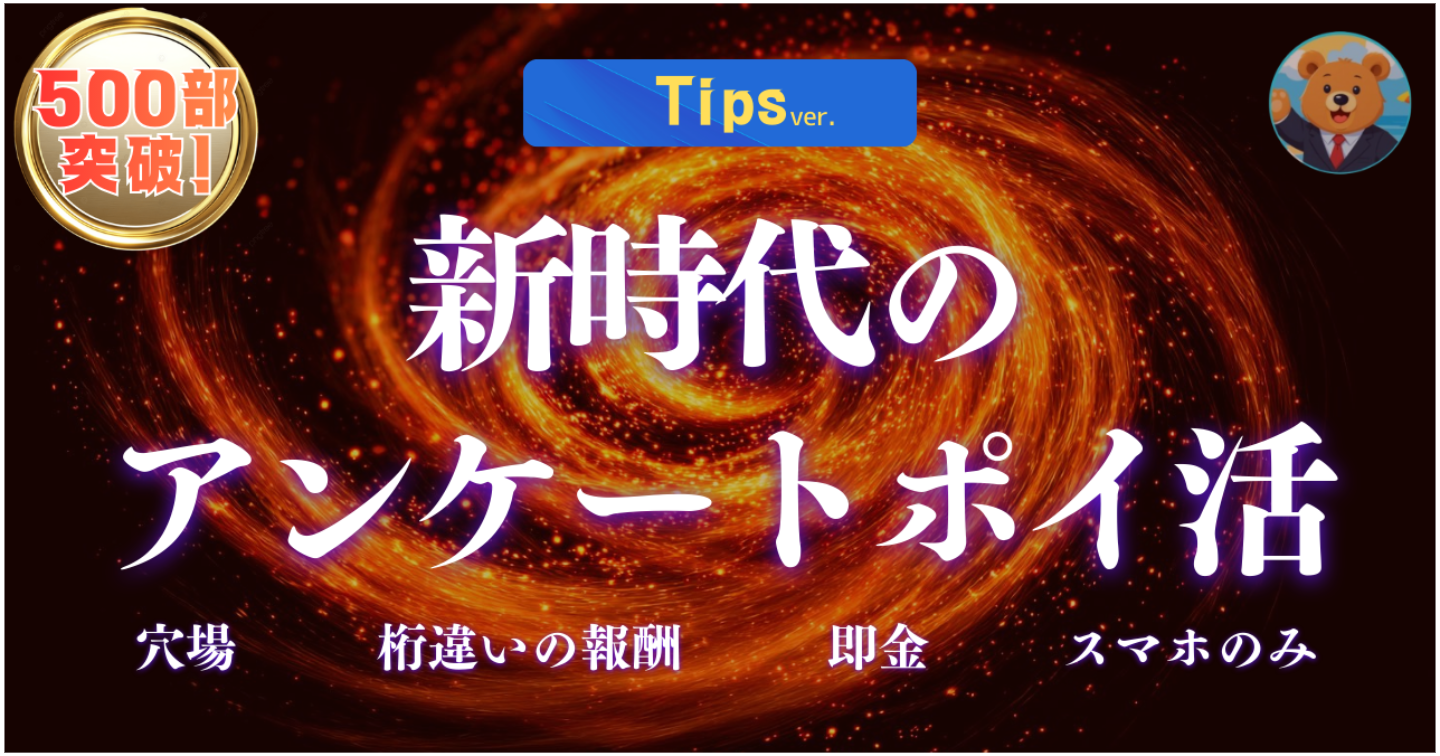1. 概要
外国為替市場は、各国の通貨が取引される場であり、その価格変動には様々な要因が影響を与えます。中でも、各国の経済状況を示す経済指標は、投資家の判断材料となり、為替レートを大きく動かす要因の一つです。発表される経済指標の結果が市場の予想と大きく異なる場合、サプライズとなり、より大きな価格変動を引き起こす可能性があります。
2. 指標と為替の影響
一般的に、ある国の経済状況が良好であれば、その国の通貨は買われやすくなる傾向があります。これは、経済成長が企業の収益増加や雇用改善につながり、投資の魅力が高まると考えられるためです。逆に、経済状況が悪化している場合は、その国の通貨は売られやすくなります。ただし、経済指標の発表後の為替レートの動きは、単に指標の良し悪しだけでなく、市場の期待値や他の要因(金融政策、地政学リスクなど)との組み合わせによって複雑に変動します。