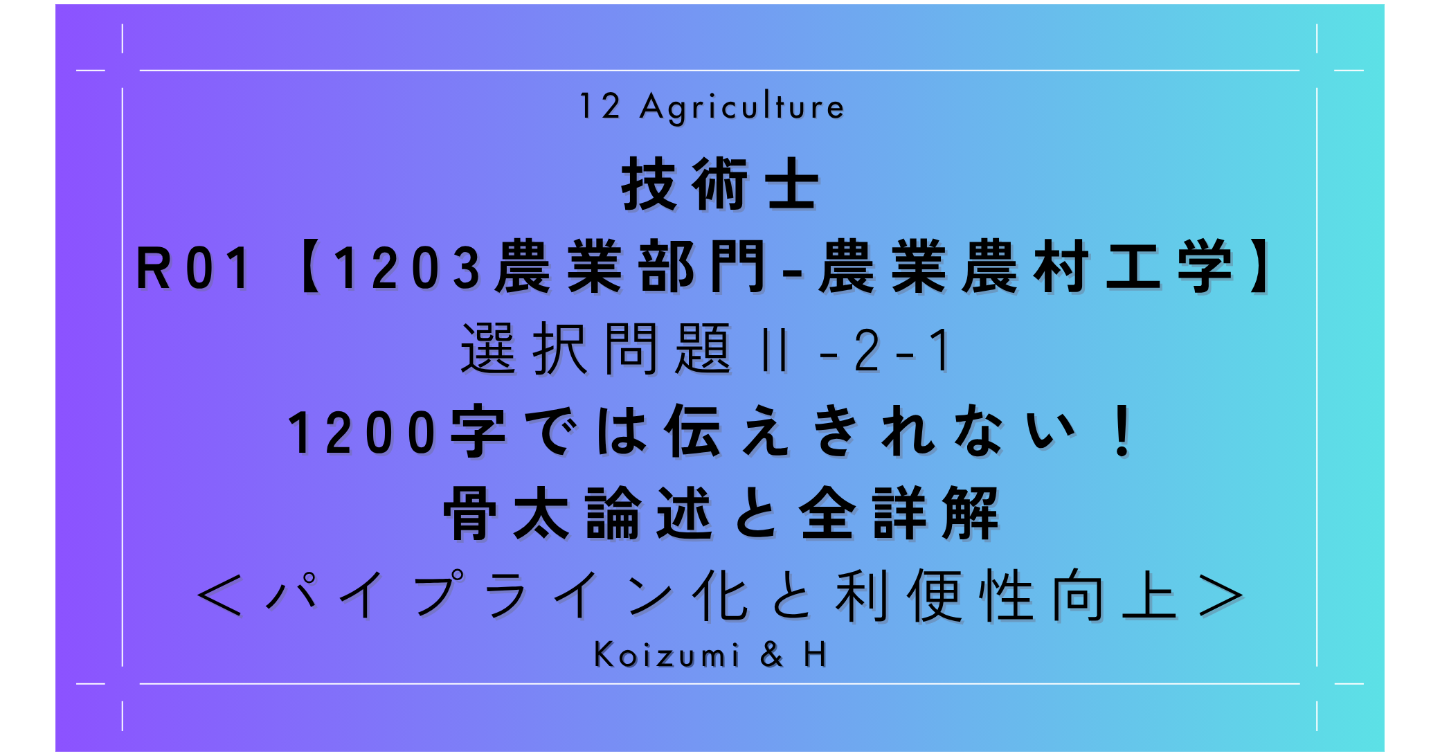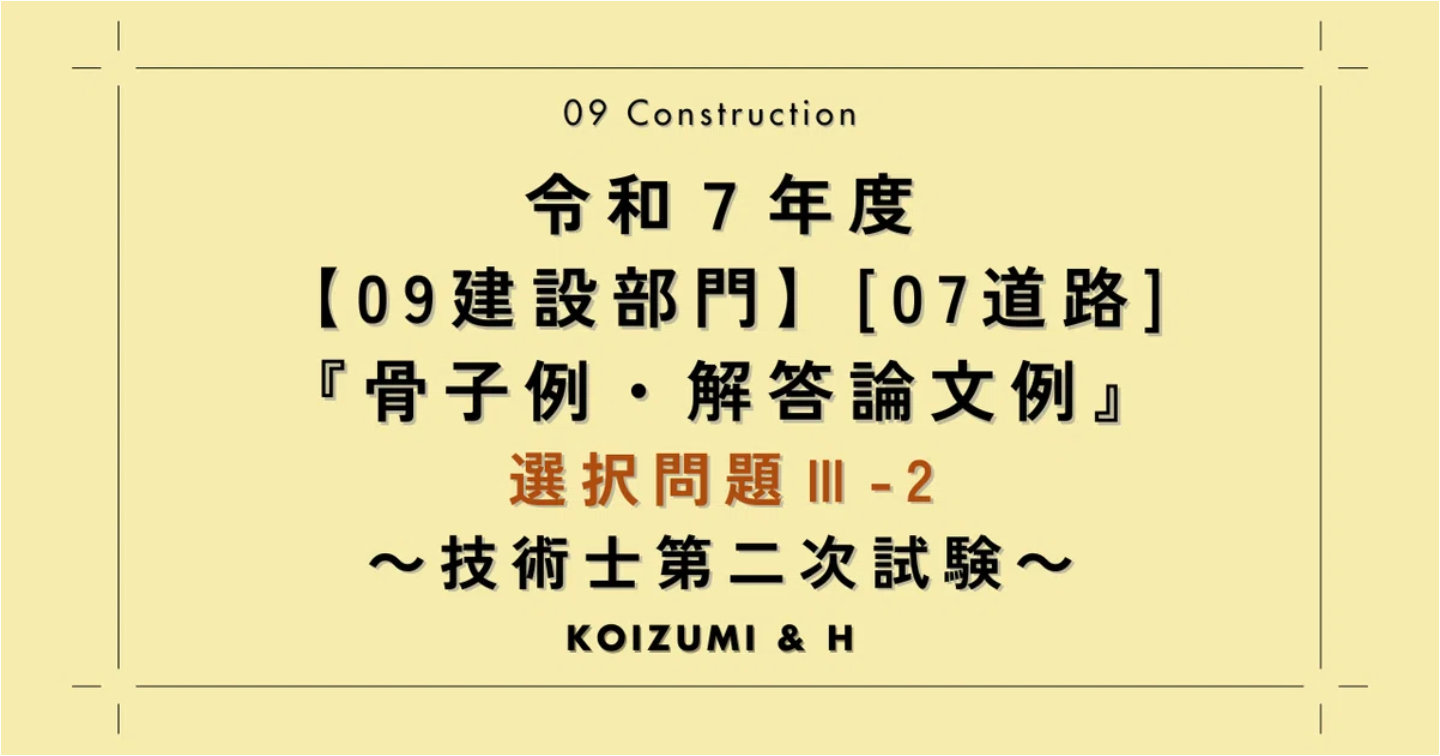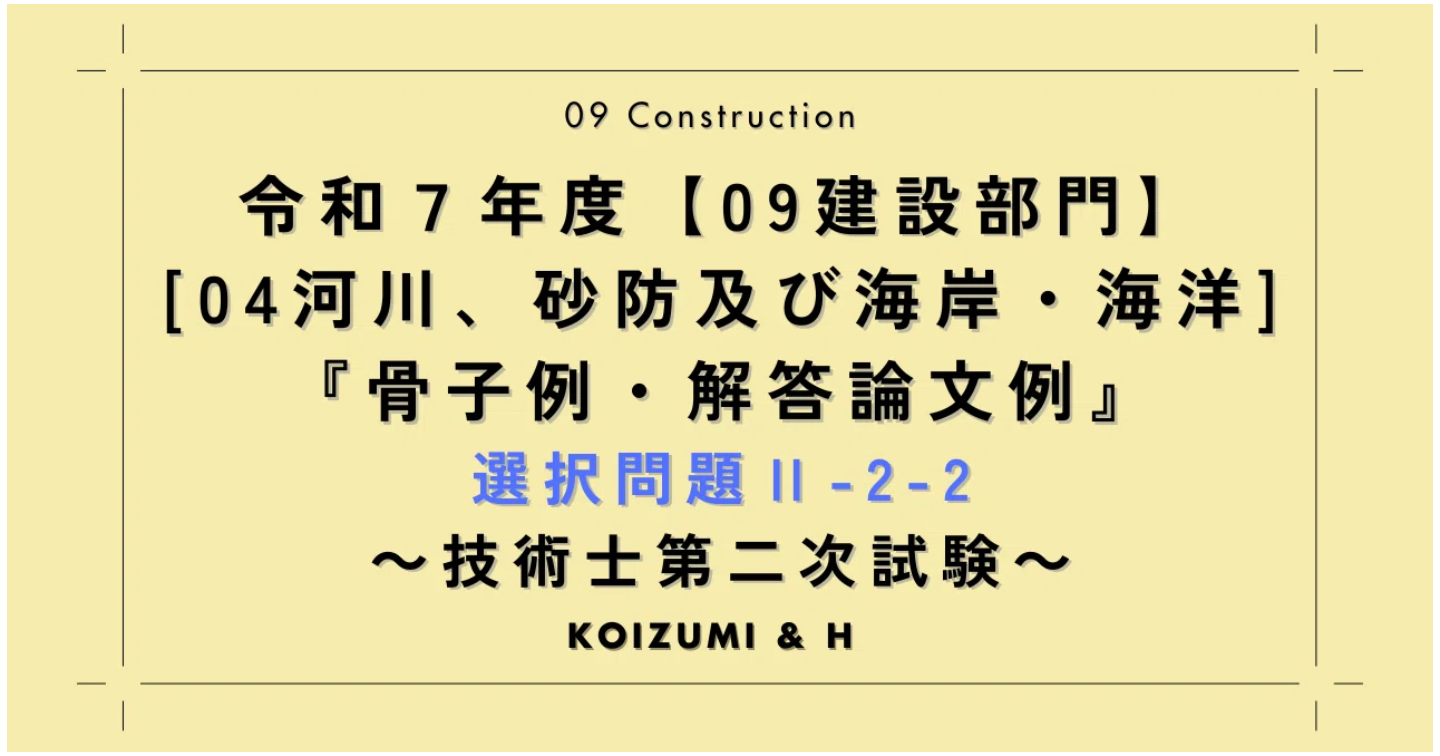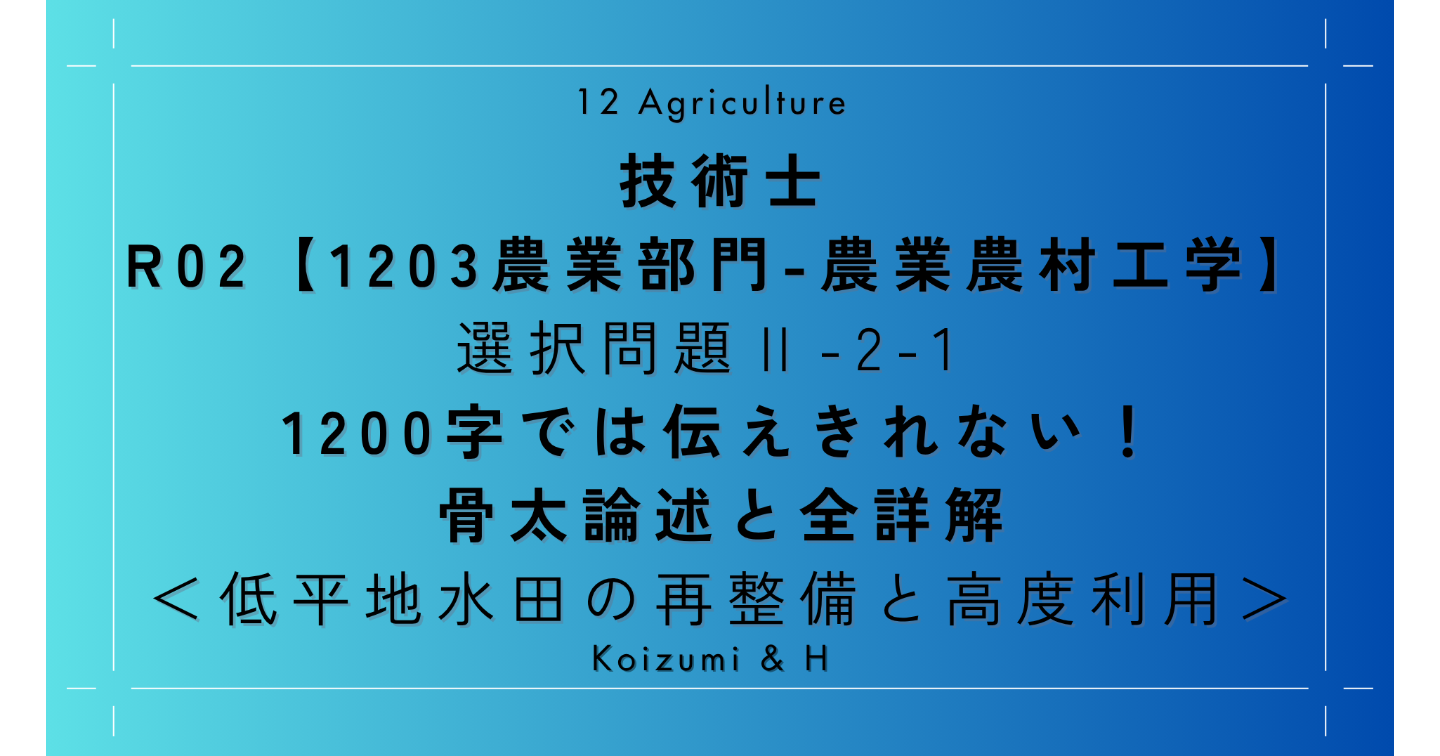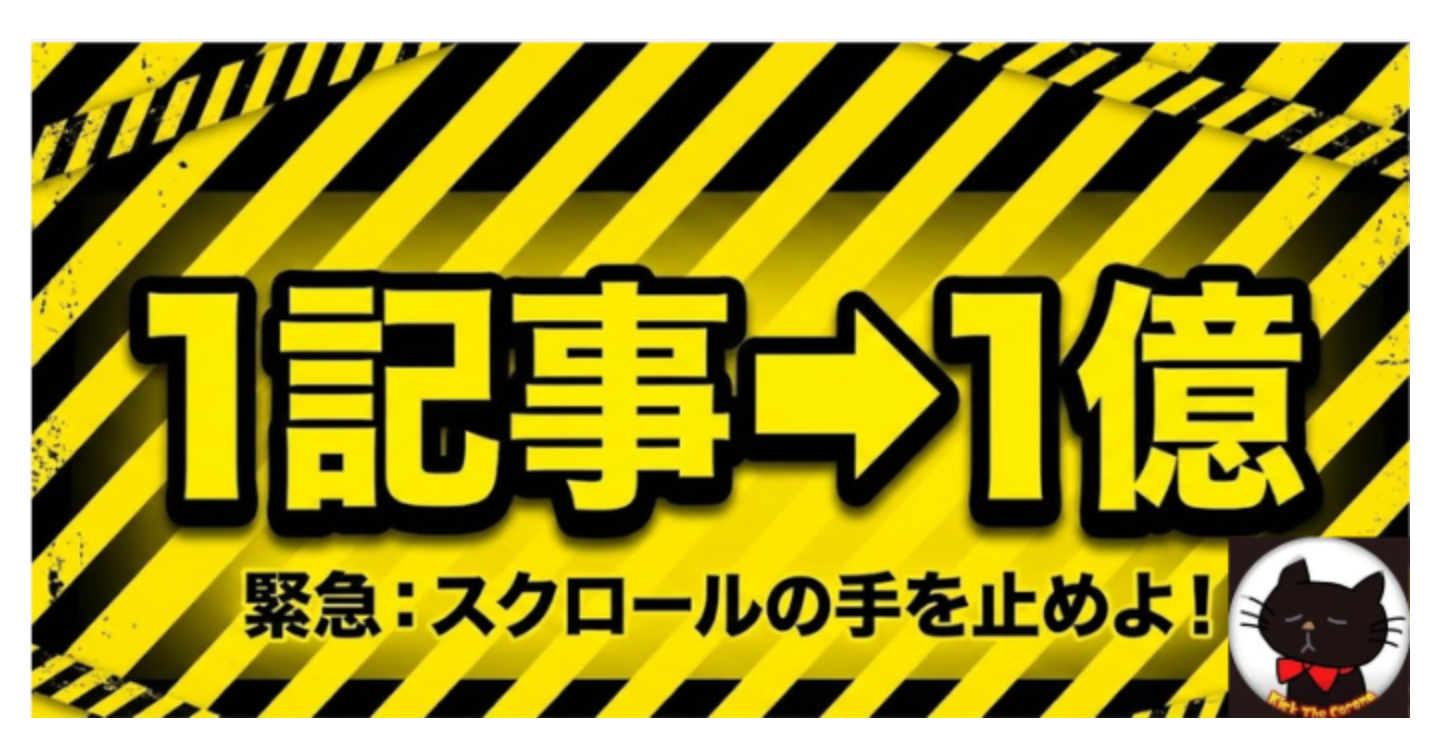【技術士第二次試験|規定字数に関する重要なお知らせ】
本記事の解答論文は、
「深い考察と多角的な視点を学ぶための教材」
として作成しています。
- 本記事の内容規定字数(1200字以内:600字詰め解答用紙2枚)の1.3~1.5倍程度の分量で、骨太な論述と詳細解説を行っています。
- 規定字数(1200字以内:600字詰め解答用紙2枚)の1.3~1.5倍程度の分量で、骨太な論述と詳細解説を行っています。
- 試験本番での対応実際の技術士第二次試験においては、規定字数(1200字以内)を厳守してください。本記事の論旨や視点を、規定字数内に収める訓練としてご活用ください。
- 実際の技術士第二次試験においては、規定字数(1200字以内)を厳守してください。
- 本記事の論旨や視点を、規定字数内に収める訓練としてご活用ください。
🔷R01_Ⅱ-2-1|過去問題
近年、農業構造や営農形態の変化から起こる用水の時期的・量的変化への対応や支線水路を主体とする配水ブロックでの需要者の水利用の利便性を向上させるため、開水路のパイプライン化が進められている。あなたが、パイプライン化計画の策定の担当責任者として業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。
(1)調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
(2)業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。
「日本技術士会」HP
🔷R01_Ⅱ-2-1【1.5倍論述のための】骨子例
1.調査・検討すべき事項およびその内容
①現況水利用実態と用水需要の調査
・営農形態と配水ブロック別用水需要
・既設開水路の水理特性と管理実態
②パイプライン施設の設計条件の検討
・管路諸元と水理設計条件の設定
・地形地質調査に基づく管路ルート選定
③事業実施に関する技術的・経済的評価
・概算事業費と費用対効果分析
・施工計画と営農改善効果の定量化
④既設施設と地域環境の調査
・既設開水路の老朽化状況調査
・地域用水利用と関係者意向把握
2.本業務を進める手順及び留意点・工夫点
▽手順①:基礎調査・現地踏査の実施
・水利用実態把握のための調査時期選定
・ドローン活用による地形データ効率取得
▽手順②:パイプライン施設の基本設計
・最大需要量設定と減圧工の適切配置
・水理解析と配水操作自動化の検討
▽手順③:事業評価と実施計画の策定
・維持管理費削減効果の適正評価
・複数施工案比較による最適工法選定
3.関係者との調整方策
1)農業者・水利組合との調整
・複数回の事業説明会による丁寧な説明
・施工中通水確保と維持管理移行支援
2)行政機関との調整
・定期連絡会議による進捗状況共有
・占用許可協議と上位計画との整合確認
3)地域住民・自治会との調整
・工事説明会による周知と環境対策説明
・地域用水代替と親水施設整備検討
4)設計・施工業者との調整
・技術提案重視の業者選定
・定期工程会議とVE提案制度活用
🔷R01_II-2-1【深掘り考察】設問(1)解答
(1) 調査・検討すべき事項およびその内容
①現況水利用実態と用水需要の調査
営農形態、作付体系、耕作者の分布状況等の現況を把握し、配水ブロック内における時期別・地区別の用水需要量を調査する。既設開水路の通水能力、水位、流量等の水理特性を測定するとともに、用水管理の実態、取水方法、配水操作の頻度等を把握する。将来の営農計画や農業構造の変化予測を踏まえた需要量を推定し、用水の時期的・量的変化の実態とその要因を分析する。
②パイプライン施設の設計条件の検討
管路延長、管径、分水工の配置等の基本諸元を設定し、計画流量、管内流速、管内圧力等の水理設計条件を検討する。地形測量、地質調査に基づき管路ルートを選定し、土質条件、地下水位、既設埋設物の状況を調査する。減圧工、排泥工、空気弁等の付帯施設の配置を計画するとともに、維持管理の省力化を図るための自動化・遠隔監視システムの導入を検討する。
③事業実施に関する技術的・経済的評価
工事費、用地補償費、維持管理費等の概算事業費を算定し、費用対効果分析により事業の経済性を評価する。施工時の通水確保、仮設工法等の施工計画を検討し、工期、施工の難易度、施工時期の制約条件を整理する。パイプライン化による営農改善効果や維持管理労力軽減効果を定量化するとともに、環境への影響や景観への配慮事項を調査・評価する。
④既設施設と地域環境の調査
既設開水路の老朽化状況、漏水箇所、構造物の健全性を詳細に調査し、廃止・残置の方針を決定する。地域用水としての利用実態や生態系への影響を把握し、親水機能や環境保全への配慮事項を整理する。地権者や関係者の意向を調査し、事業実施に向けた合意形成の条件を検討する。