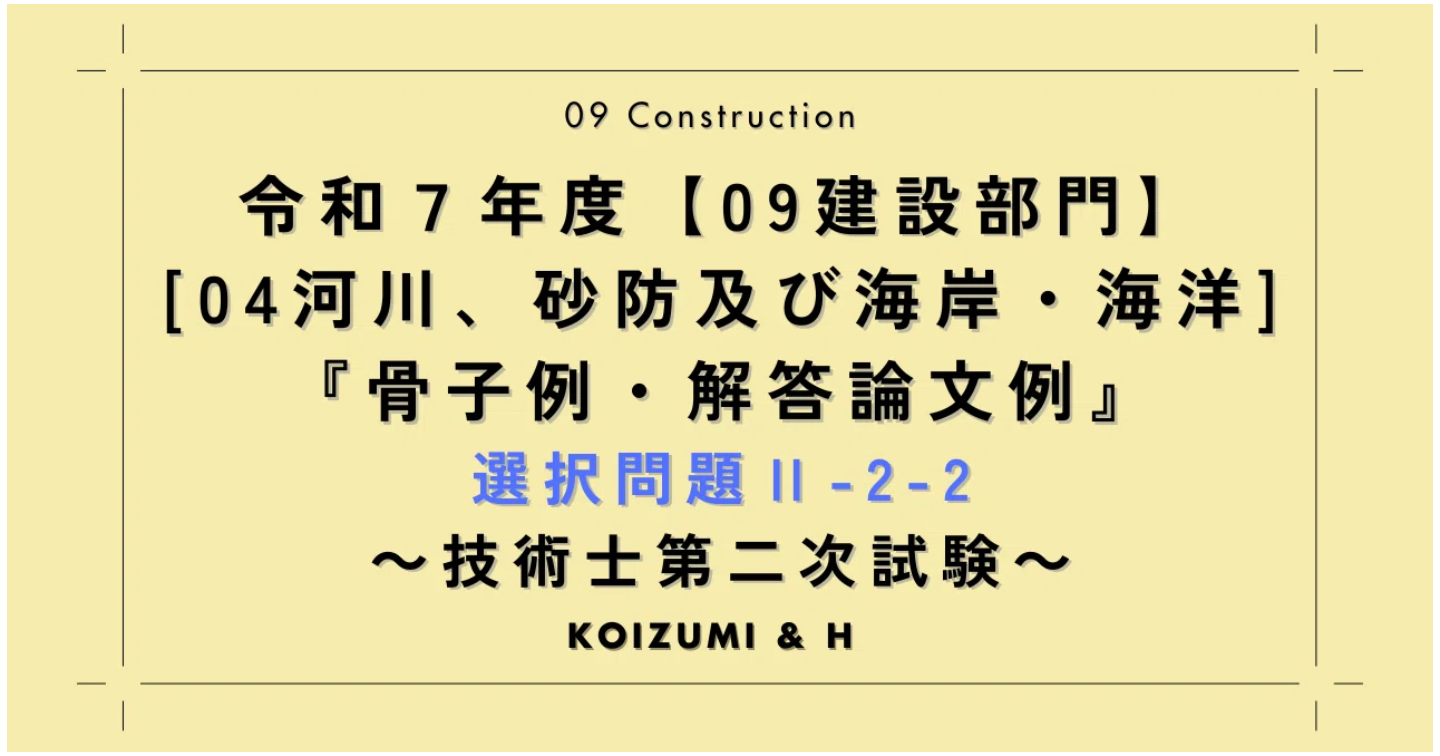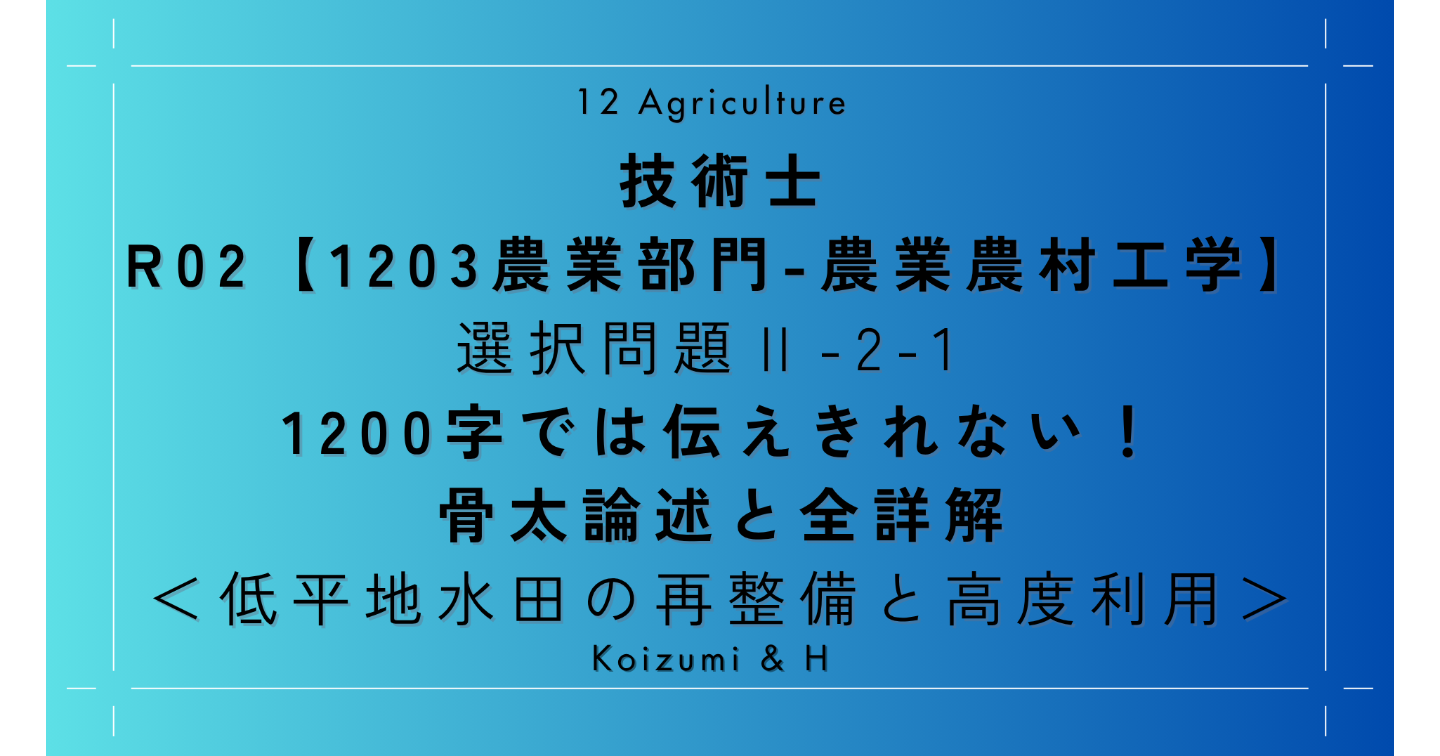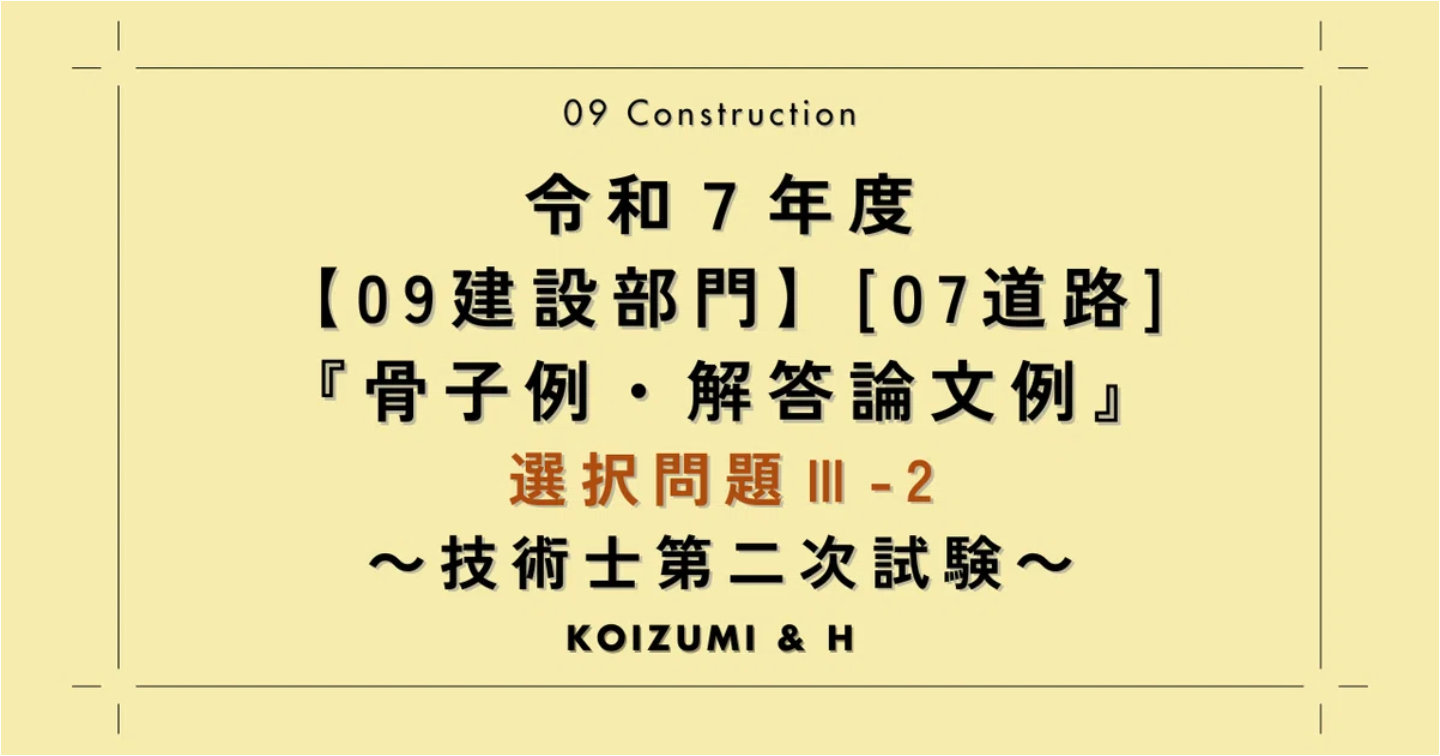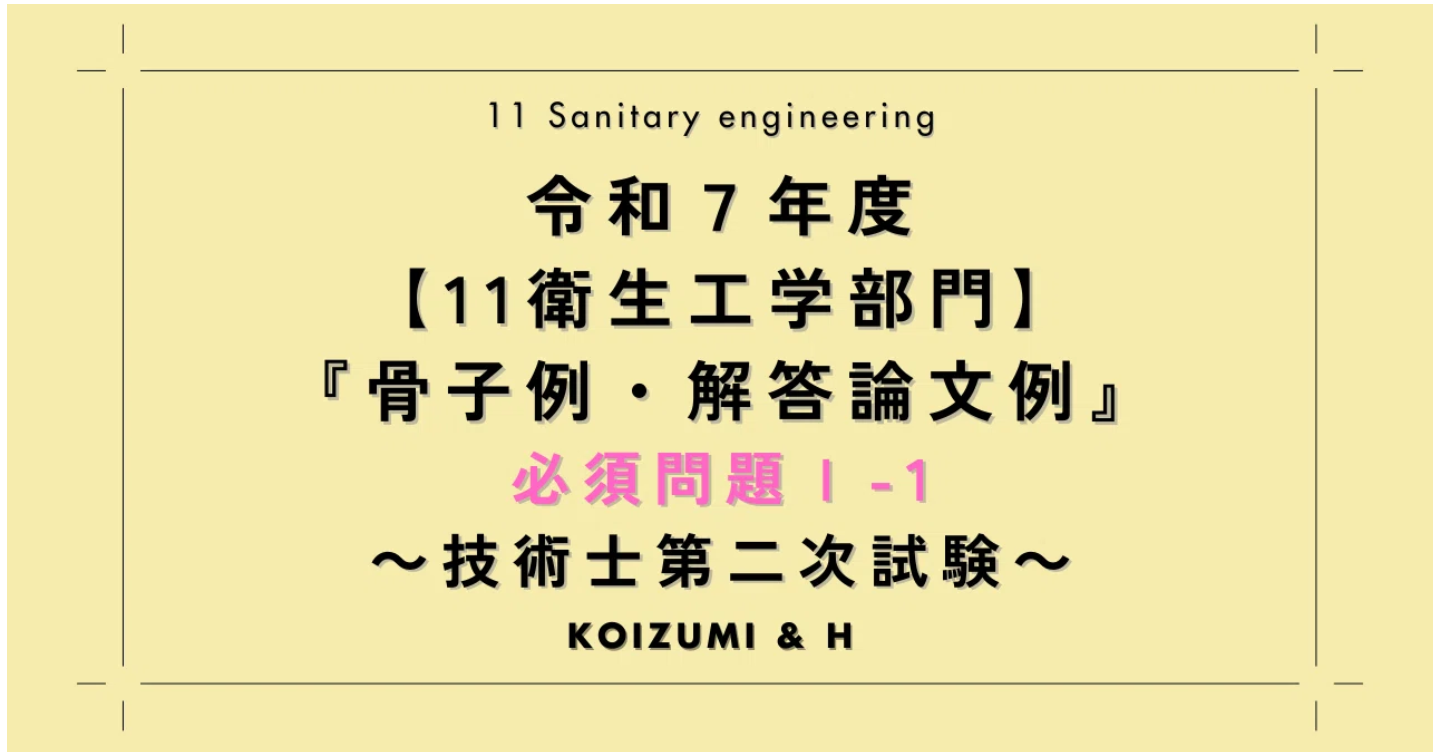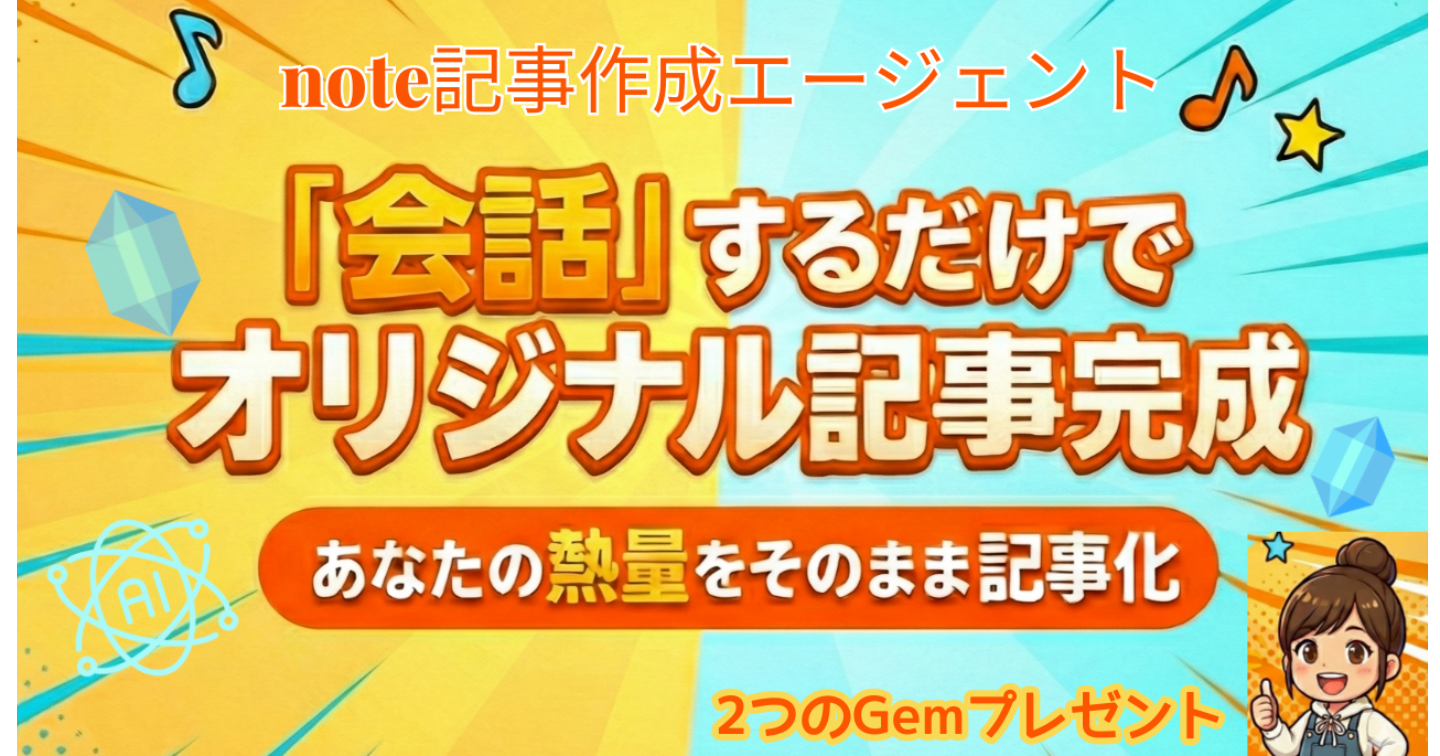🔶R07_Ⅱ-2-2|過去問題
国や都道府県では、これまで、想定しうる最大規模の降雨あるいは計画規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域図を作成し、公表してきた。今後、水害リスクを踏まえた土地利用の促進などを推進するためには、比較的発生頻度が高い降雨規模も含めた複数の確率規模の降雨によって想定される浸水範囲や浸水深を明らかにし、浸水の生じやすさや浸水の発生頻度を示す新たな水害リスク情報を公表することが求められている。
あなたが降雨の確率規模別に作成する浸水想定図(以下「多段階の浸水想定図」という)及び所与の浸水深になると想定される浸水範囲の浸水頻度を示す地図(以下「水害リスクマップ」という)の作成に携わることとなった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。
(1)多段階の浸水想定図及び水害リスクマップを作成するに当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
(2)多段階の浸水想定図及び水害リスクマップを作成する手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
(3)多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの作成及び活用を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。
「日本技術士会」HP
🔶R07_Ⅱ-2-2|骨子例
1.事前調査・検討事項の整理
①流域特性の把握
・対象流域データの収集と解析モデル構築
・確率規模降雨量の水文学的設定
②既存インフラの調査
・施設規模・能力の現状把握
・治水リスク区間の特定
③地盤高データの整備
・高精度レーザー測量による数値標高モデル
・微地形反映による浸水解析精度向上
④社会基盤施設の分布調査
・要配慮者利用施設等の位置把握
・リスクコミュニケーション基礎資料作成
⑤過去災害実績の分析
・過去洪水データの収集・分析
・解析モデル検証への活用
2.本業務を進める手順、及び留意点・工夫点
1)降雨シナリオの設定
・複数確率年降雨量の統計解析
・気候変動・計画外降雨の考慮
2)流出・氾濫解析の実施
・統合的な外水・内水氾濫評価
・破堤条件の感度分析
3)多段階浸水想定図の作成
・市民理解を促進する表示方法
・浸水継続時間・流速情報の併記
4)水害リスクマップの作成
・発生確率の見える化
・解説資料・実績比較情報の提示
3.効率的・効果的に進める関係者との調整方策
〇河川管理者
・将来河川改修計画の解析条件反映
・定期技術検討会による合意形成
〇市町村
・地域防災計画等への活用前提
・ワーキンググループによる地域特性反映
〇地域住民・事業者
・リスク理解促進と避難行動支援
・説明会・個別相談会の実施
〇学識経験者
・解析手法の妥当性確保
・技術委員会による透明性の高い検証体制