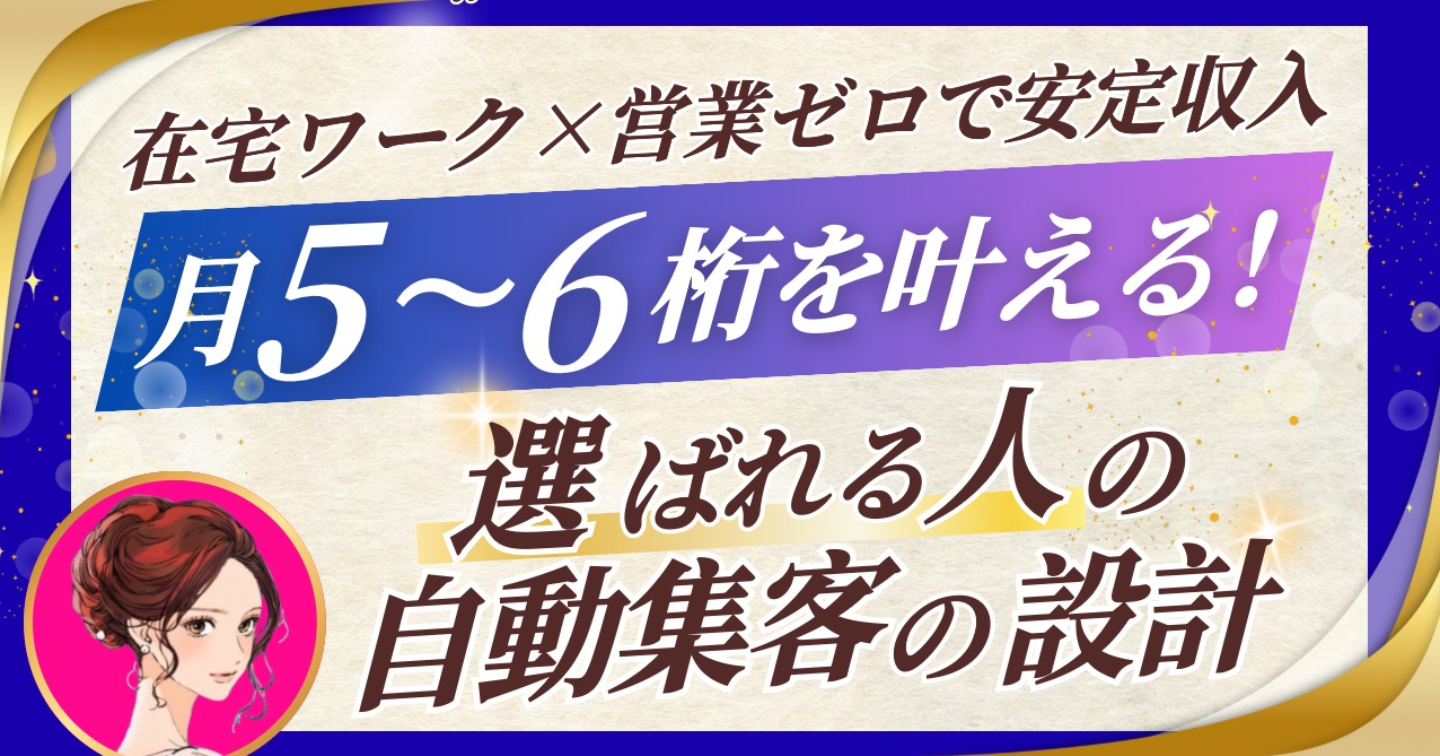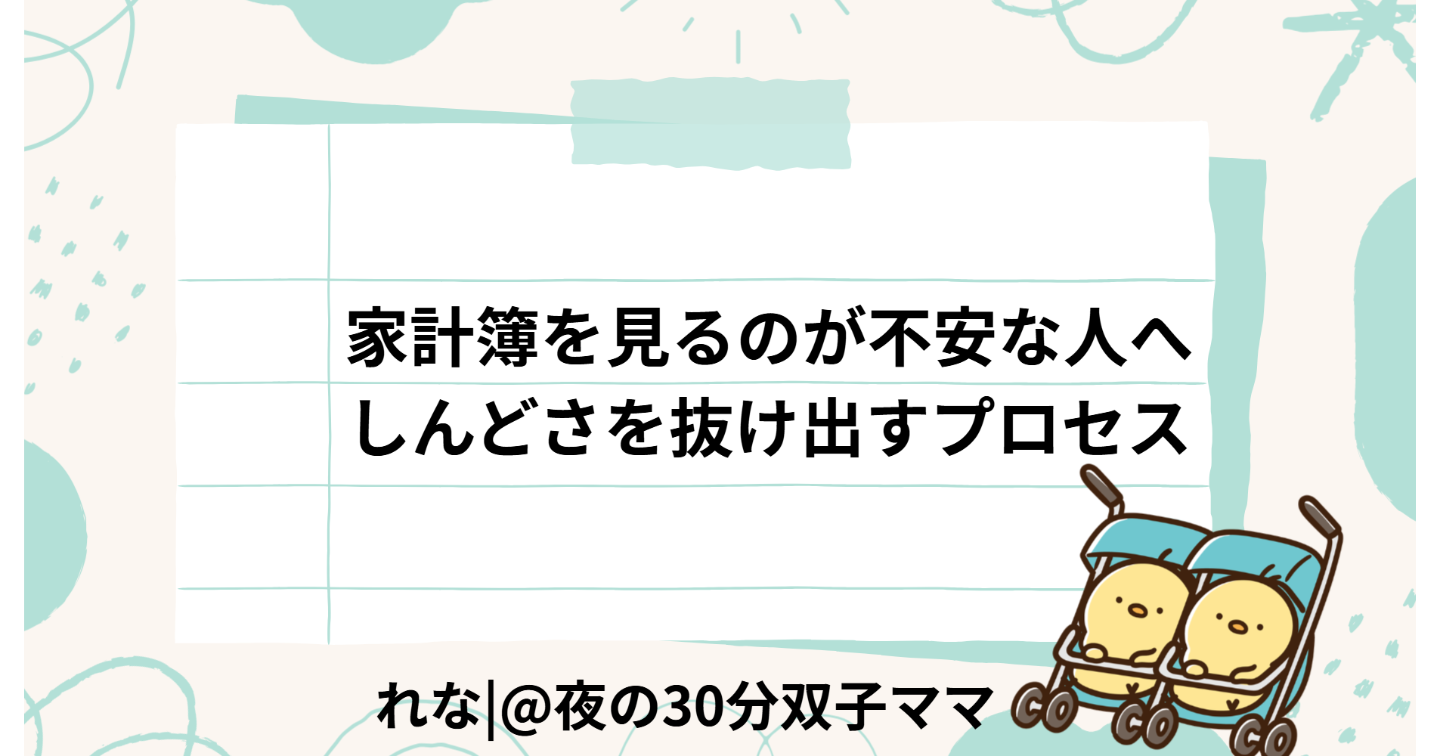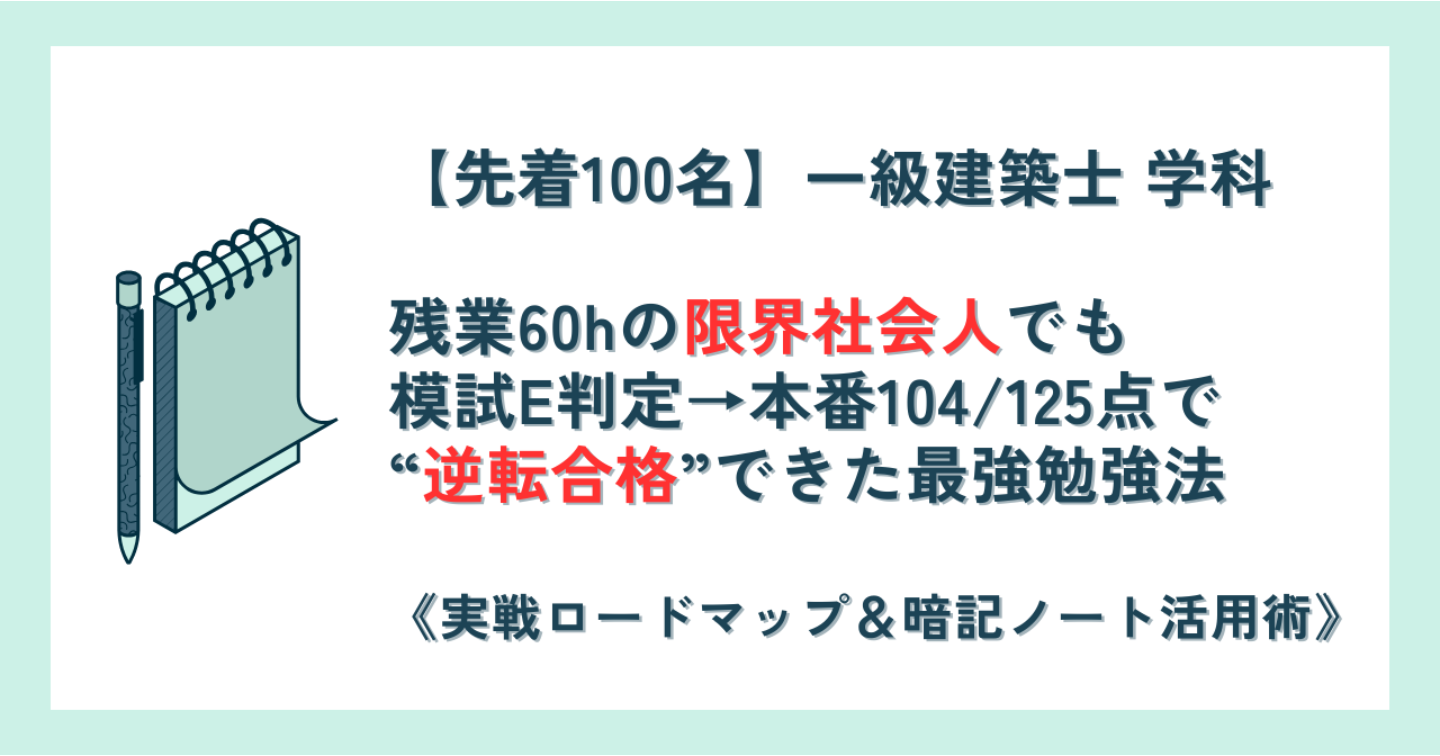
【先着100名】残業60hの限界社会人でも“逆転合格”できた最強の勉強法│模試E判定→本番104点│一級建築士学科│《実戦ロードマップ&暗記

ぐりこ│一級建築士 合格サポーター
「時間がない社会人でも、7か月で“確実に受かる力”を積み上げる。」
──暗記ノート×過去問の二段導線と、5科目を横断して伸ばす戦略 誰でも合格できる最強のメソッドをご紹介します。
1.この記事で何が起きる?
- 筆者の成功体験:試験当日、時計を見ても焦らない。法規は条文の“当たり”が一瞬で引ける。構造の応用問題も「なぜ正解か」を説明できる。結果は104/125点。社内評価も上がり、配属や転職の選択肢が増える。
- よくある失敗:膨大な教材に手を広げ、直前期に“暗記の海”で溺れる。法規は例外で落とし、構造の計算で時間切れ。あと5点足りない…。
- そのまま使える勉強法:この記事は私の合格体験記を元に、確実に合格点をつかみ取る勉強メソッドを詳しく解説。さらに7か月実戦ロードマップと暗記ノートの活用方法についても記載しています。
2.私のリアル
点数の変遷
2か月目:31/125点
4か月目:73/125点
6か月目:98/125点
本番:104/125点(合格)
学習の順番
法規:法令集の場所当て訓練 +頻出箇所の暗記
構造:計算問題の仕上げ+誤答分析
環境・設備:頻出科目対策
計画:頻出科目対策
施工:鉄骨・RCで得点の軸作り
3.5科目の“得点戦略”
1) 法規:「場所当て」→暗記→例外で伸ばす
最初の1か月、私は正誤より“場所当て”に全振り。
問題を見て法令集のどこかをパッと指させる練習を反復しました。
正誤は後回しでOK。引ければ勝ちです。
その後、暗記ノート(赤シートで隠す)で条文の“核”を暗記。
実戦では「暗記で解く」「法令集で保険をかける」を往復。
暗記に寄りすぎると例外で落ちるので塩梅には注意が必要です。
暗記ノートを直前期に重点回しして、本番は28/30点まで乗せました。
2) 構造:誤答の理由を言語化する“修正学習”
丸暗記は応用で破綻。
私は暗記ノートでひと通り覚えた後、過去問で間違いを溜める→なぜ正解/不正解かを一問ずつ日本語で説明。
同じ“つまずき”が繰り返されるので、誤答一覧リストに記録していきます。
計算は早期に基礎問題を固めて、最後は手が勝手に動くレベルへ。
3) 環境・設備:環境は“深掘り”、設備は“面で広げる”
環境は、とっつきやすい&出現率も悪くない。
数で解くより、誤答の理由を深掘りして理解の網目を細かくする方が伸びが早い。
設備は、量的訓練が必要。ただし出現率の高い論点から順に暗記ノートを拡張。
4) 計画:頻出→スケール感→数値
実例集はおもしろい。けど出題効率は控えめ。
最初は頻出分野(住宅、高齢者など)から。
つぎにスケール感(車いす座面→可動域→操作高など)を体で覚える。
最後に具体的な数値を叩き込む。
順番を守ると暗記が“刺さる”。
5) 施工:鉄骨・RCを軸に、直前は“誤り肢”狩り
専門用語×細かい数値で沼りやすい科目。
構造と重なる鉄骨・RCを深く取ると得点の背骨ができる。
内装は初出も多く難易度高め。裏技として、過去の誤り肢を別年度でもう一度誤り肢として出してくるパターンが多い。
直前期に誤り肢ノートを回しまくると効果絶大です。
4.暗記ノート × 過去問 = “二段導線”とは?
- 導線①:暗記で即答(時間短縮)
- 導線②:過去問の出題傾向で解く(問題に慣れる)片方だけに寄らない。このバランスが得点の天井を上げます。私は暗記ノートに誤答の理由と例外を書き足していき、一本化しました。
各科目ごとの対策すべきポイントを解説しました。では実際に、合格するための具体的な勉強時間やスケジュールについて、詳しくロードマップにして説明します。