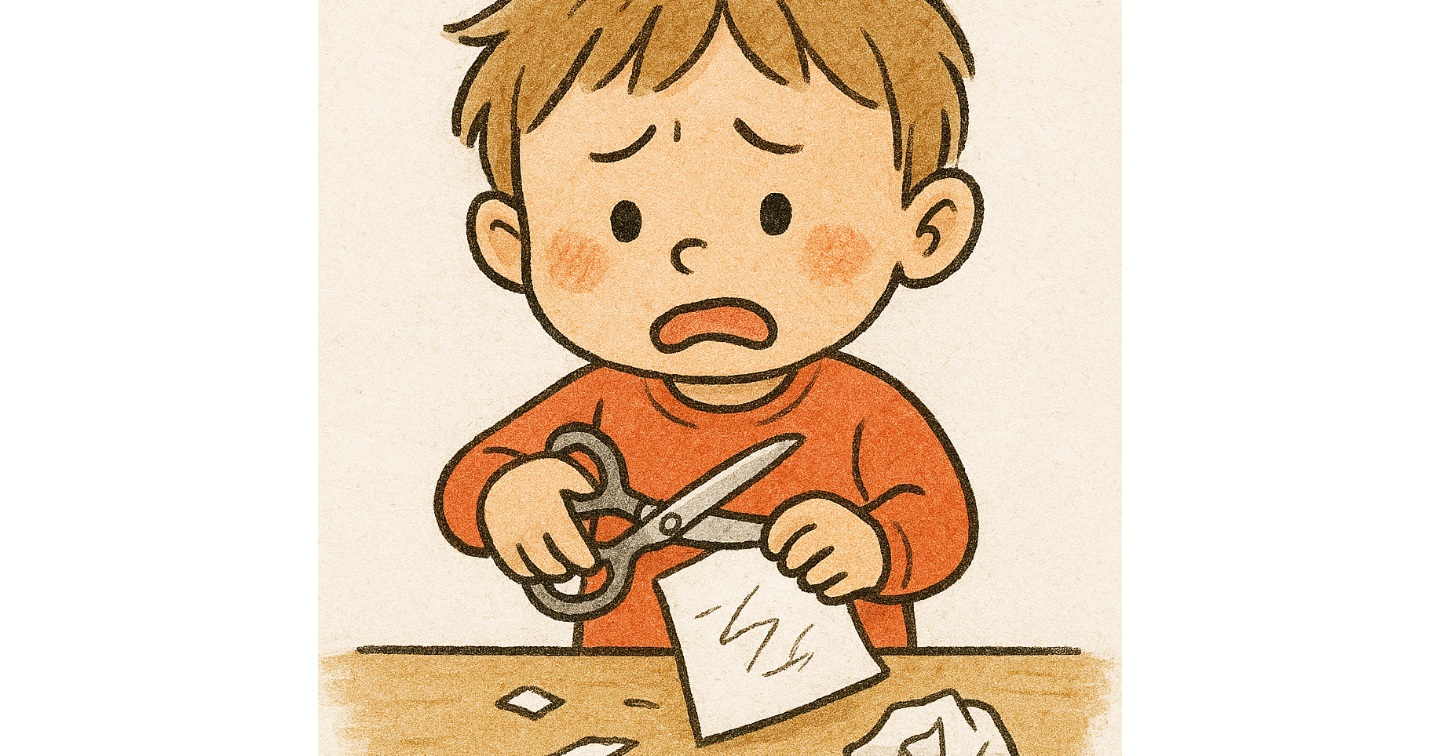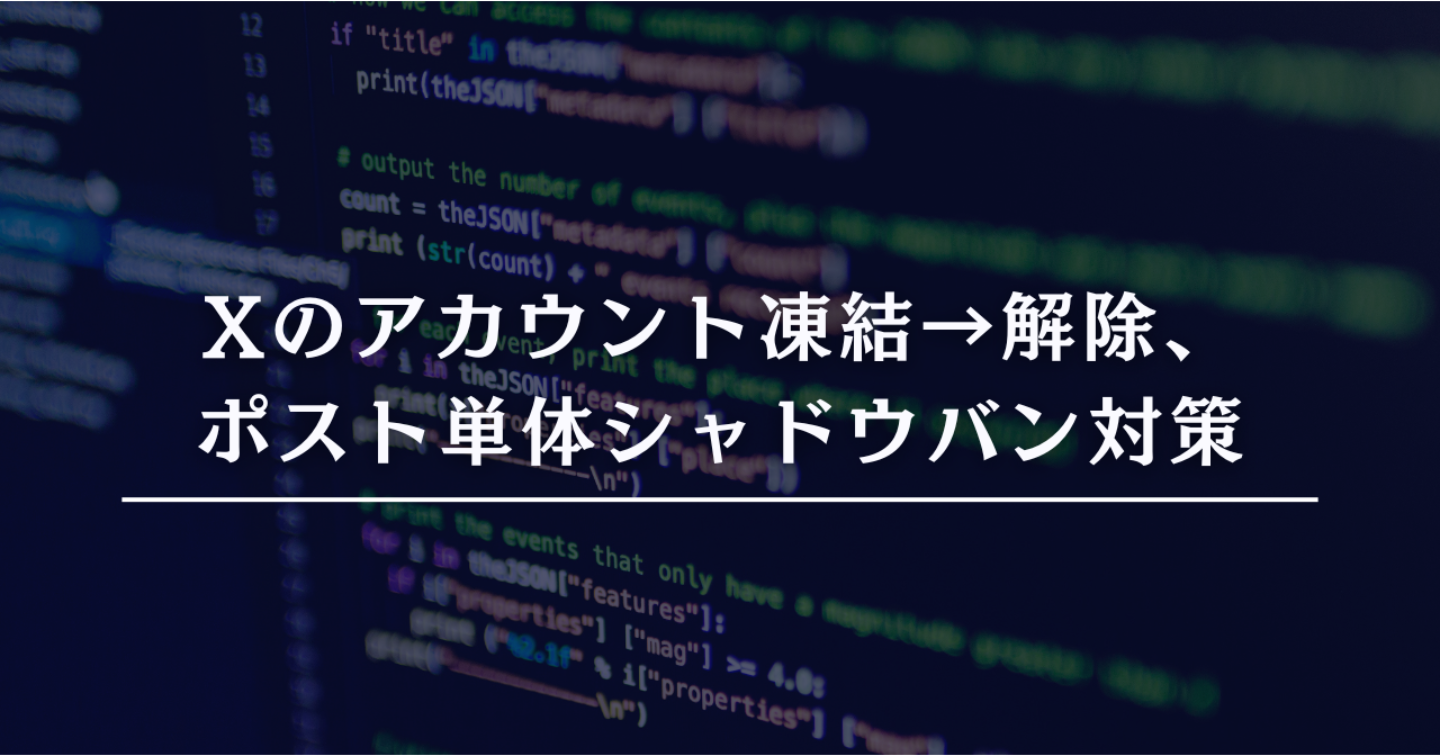支援を必要とする人は、私たちが「助けたい」と直感的に思える姿をしているとは限りません
むしろ、不規則な生活、無頓着な身なり、攻撃的な態度、対人関係の難しさなど、
「関わりづらい」印象をまとうことがあります
しかし、その背後には、特性、障害、精神疾患、トラウマといった深刻な背景が隠れているケースが多いのです
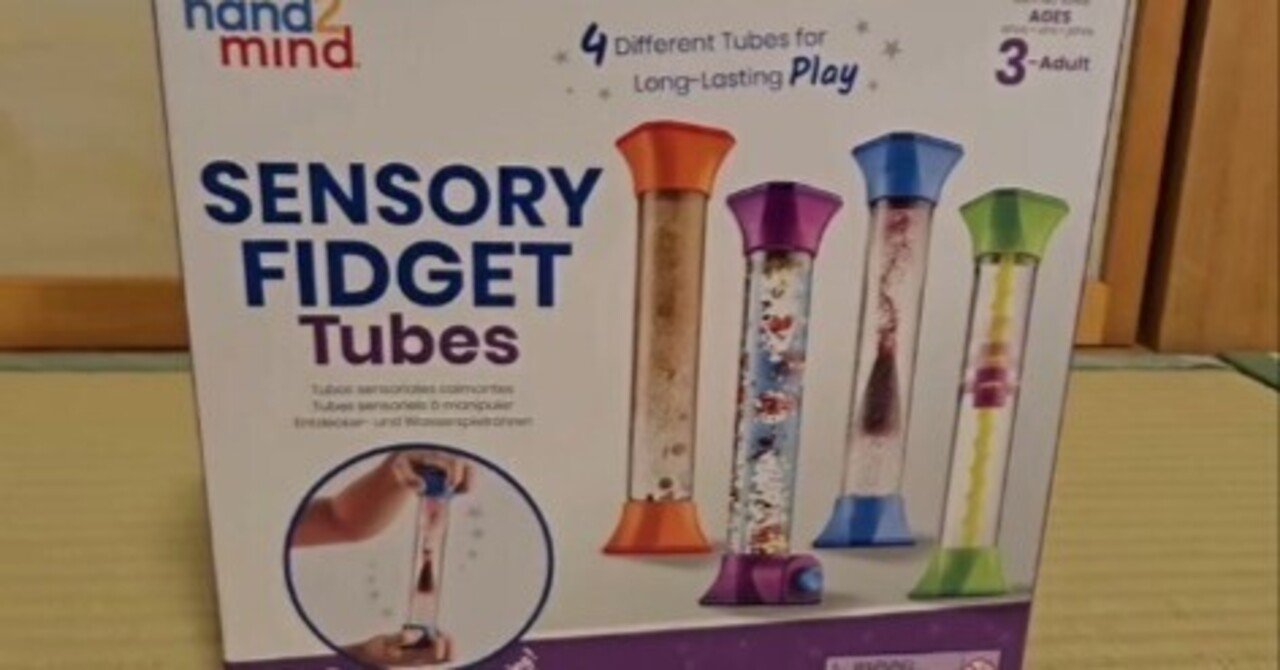
よく誤解されるのは「助ける側の権利」という言葉です
・助ける側にも助ける側を選ぶ権利がある
・助けられる側が助けたい姿をしているんじゃ助けられなくてもしょうがない
・優しくするにも限度がある
この捉え方がそもそも間違っており、歪んでいます

皆さんが日常で覚える「相手を助けたい」という気持ちも「エゴ」、「欲望」の一つです
人の数だけ、状況の数だけ、感情の数だけ、「助けたい相手」は変わるし、生まれるでしょう?
その何に左右されるか分からない曖昧な
「エゴ」や「欲望」の「強弱、度合い、レベル」によって
相手が「助かる、助からない」が決まってはいけない
この思考が
「本当に支援、助けが必要な社会的な弱者は、助けたいと思うような姿をしていない」
が意味することなのだと、私は認識しています

こういった「助けたいエゴや欲望」を振りかざす人の多くは
「助けられる力」を持っていません
大抵の場合、
相手を「現実をみろ」という言葉で卑下したり、
「誰でも助けられる訳ではない」と誰も助ける気もないのに恰好つけたり
「綺麗事を言うな」と汚く、能力不足の自分を正当化
します

「誰かを助けたい」というその感情は決して悪いものではありません
しかし、そういった「助けたい」「助けたくない」という感情で支援の判断を曇らせてはならないのです
「支援」は「公に誰でも受けられること」が必要不可欠で、重要あると我々は認識しなければなりません
一個人の感情の天秤に左右されてはいけないのです
そして「支援」とは、その「関わりづらさの奥にある背景を見抜くこと」から始まります
要するに「知識」と「技術」と「倫理」といった部分が支援者にも、そのシステムにも必要なのです
ここが抜け落ちると、如何に「助けたい」と思っても無理です
自分も相手も「だれも幸せにならない結果」を招きます
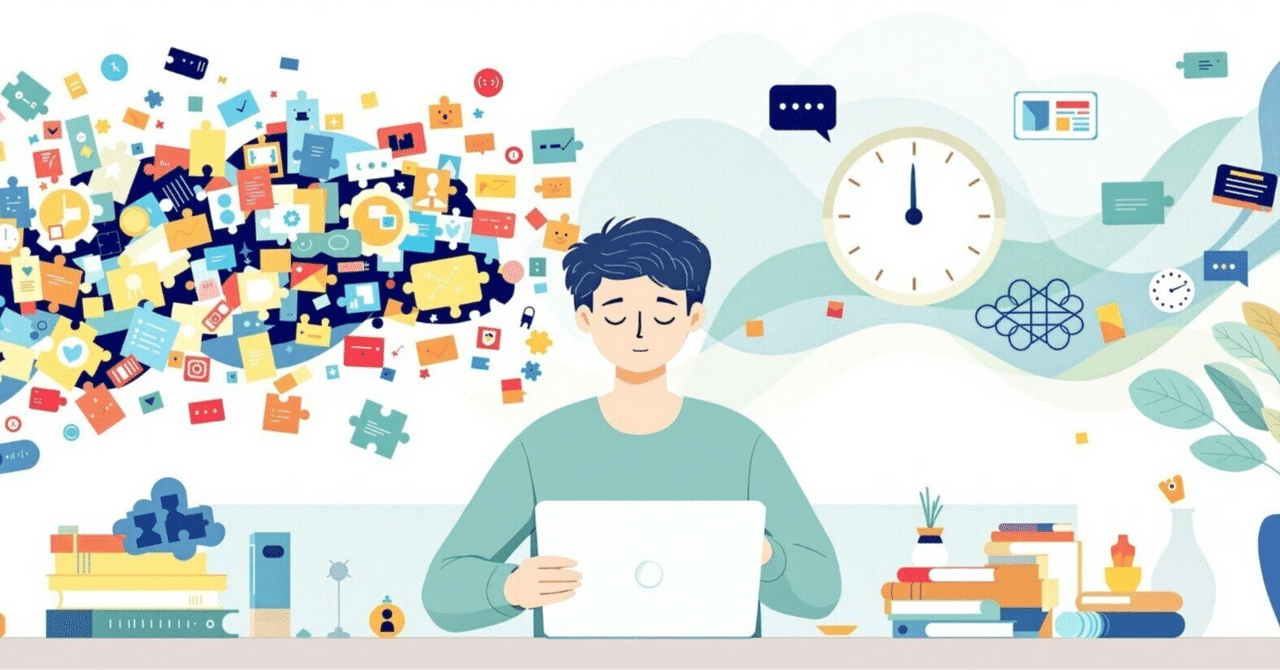
「本当に支援、助けが必要な社会的な弱者は、助けたいと思うような姿をしていない」
最近SNSでは「なんでこいつを私が助ける必要があるんだ?」という意味で使用されることが多いですね
本来の「システム」でなければならない対人援助職でさえ、そういった誤用を平気で使う人がいます
支援員、介護士、保育士、幼稚園教諭、教員…
専門職、有資格者失格、適正なしと言わざるを得ません
この言葉は誰かを排除するものではけっしてないのです