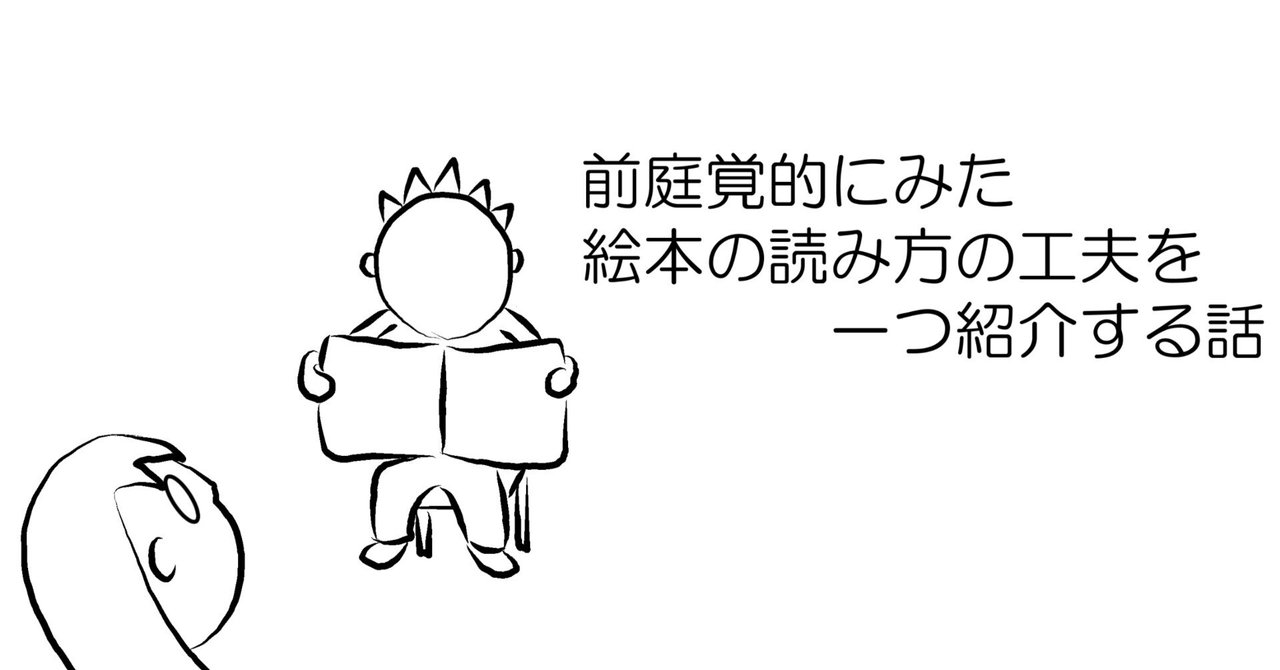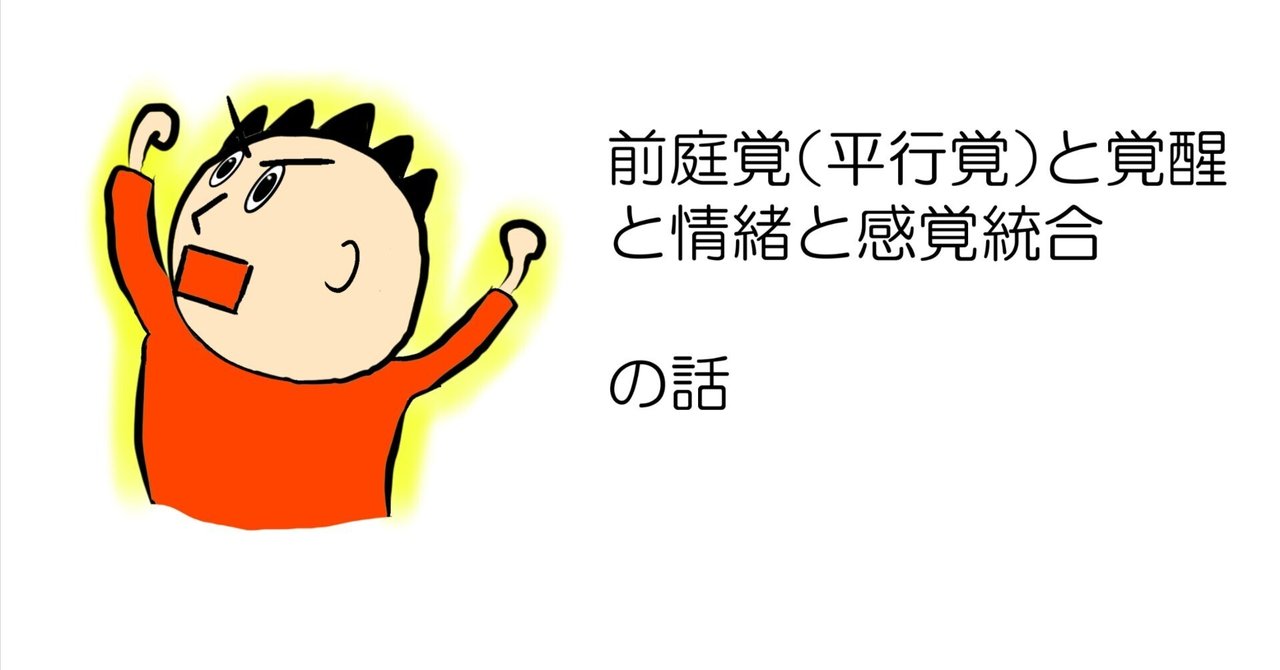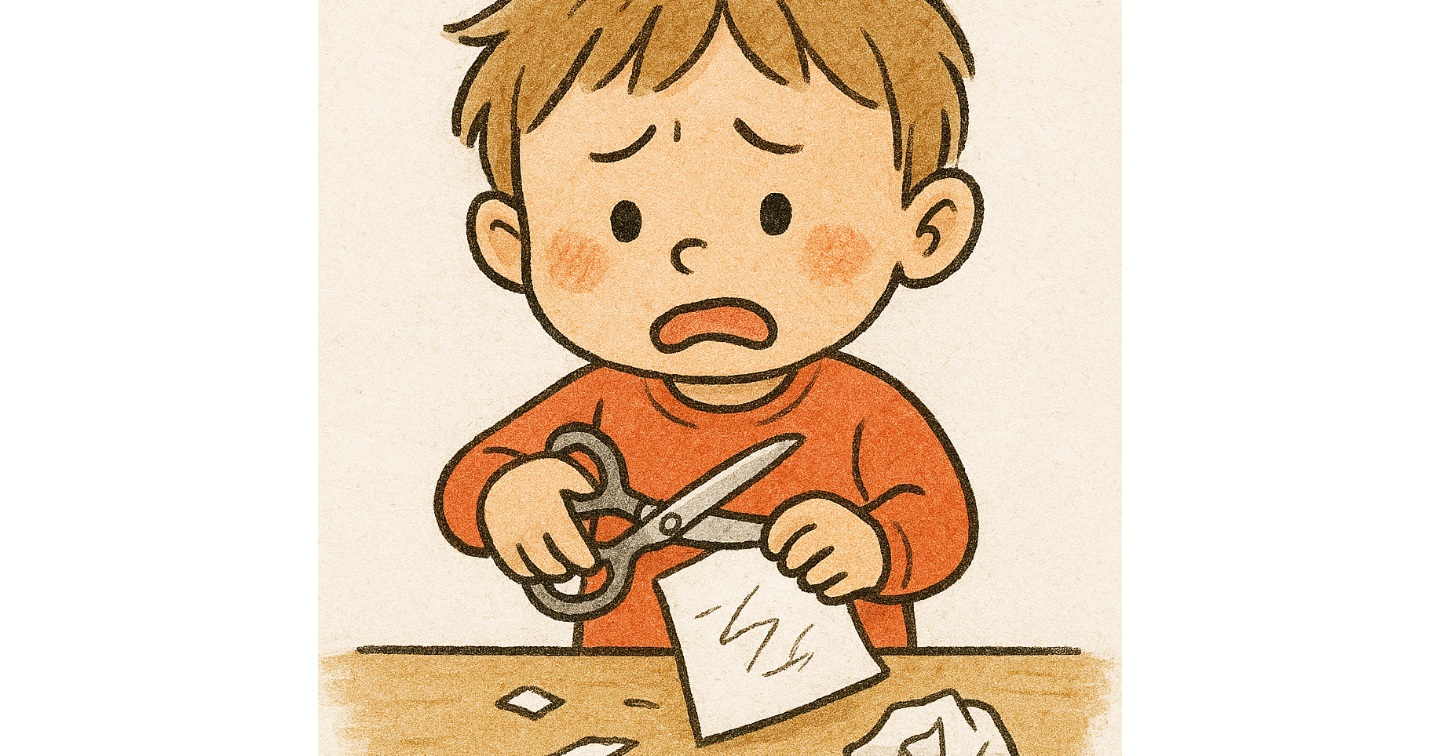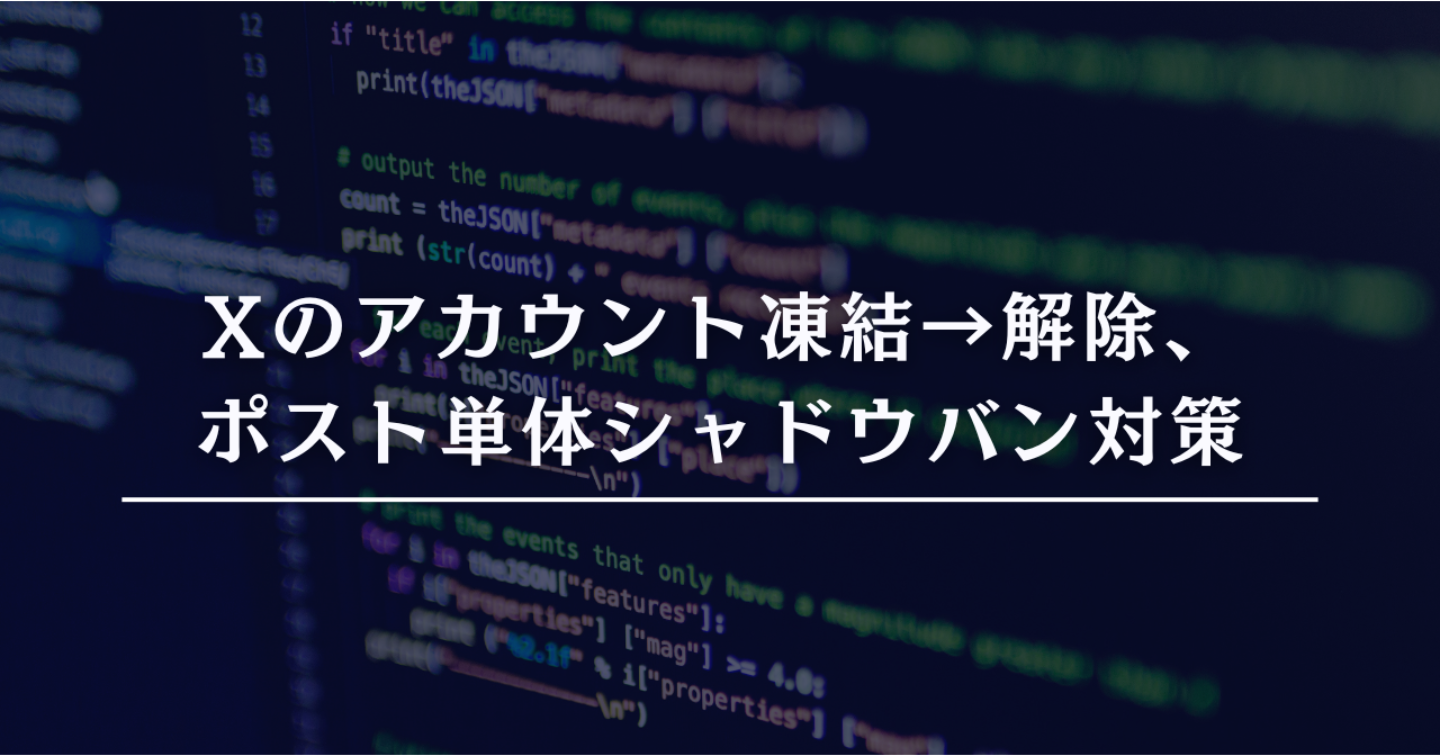前回の記事

では、どのように前庭覚を育てればいいのかを記述していきます
大人の心構え
前庭覚が育っていない、鈍麻、過敏なお子さんが「わがままに行動している」「人の話を聞かない」などに見られがちです
しかし、本当は「感覚が育っていない」ために起こっていることで、「本人の意図しないことで失敗経験を重ねている」ことがほとんどです
本人を責めず、前庭覚を育てる方向で遊びを積極的に行うことで、成長を促すことがとても大切です
また、前庭覚を使う遊びはできるだけ「大人を交えて行う」と とてもいいですなぜなら、大人と一緒に行うことで、遊びの中で「信頼関係」が構築される流れが生まれるからです
「信頼関係」はお子さんとの関わりで一番重要になります
まず信頼関係を作る方向性で、関われる遊びを紹介したいと思います
以下に前庭覚を育てる遊びの一部を紹介したいと思います
基本的に、前庭覚を育てる遊びは皆さんが思いつくものばかりです「こういう考え方もあるのか」、と意識するだけで、遊び方や評価の仕方が変わってきます。これも支援の楽しい所ですね
また、( )内は「この感覚にもいいよ」というものも書いています。また、投稿していきたいと思いますが、自身で調べてもみてください
ついでにいろいろな便利な物も紹介していきたいと思います
抱っこ、おんぶでぐるぐる、お馬さん(前庭覚、触覚、視覚、固有覚)
抱っこ、おんぶををしながらぐるぐる回ります。最後はどしーんと、床に寝転がります。前庭覚を大人、子どもと一緒に楽しむことができますあまりやりすぎると大人が持たないので、1~3回を繰り返します
大人も疲れた時は、「ちょっとまって」「10数えたらもう一回やろう」と待つ動作を楽しく学ぶきっかけになったりします。お馬さんはその名の通り、大人が四つ這いになり、子どもが乗ります
抱っこ、おんぶ、お馬さんの時に、子どもがどれくらい力を入れれるかも確認してみて下さい。固有覚の操作が苦手な子は、力を入れすぎたり、逆に力を入れれなくて落ちたりします。
個人的には身体を壊さないことがベストなので、サポーターをの装着をお勧めしています。身体に負荷がかかる遊びは、事前に身体を補強してから臨んだほうが、負担感が少なく、モチベーションの維持につながります
面白いことに、この遊びが習慣化すると、子どもが「やってほしい」と思った時にサポーターを持ってきてくれて、気持ちが分かりやすいなどの効果がありました(笑)広告はこれですが、自分に合ったものを選んでみてください
段ボール、紙袋に入って回る、傾ける、引っ張る(前庭覚、視覚、固有覚、触覚)
段ボール、紙袋に子どもを入れてぐるぐる回します
紙袋、段ボールの底は滑りやすいので、回しやすいです。でも大人は結構疲れるので、これも1~3回くらいを繰り返します。意外なことに中くらい段ボール、大きめの紙袋、案外2歳4歳くらいのお子さんってすっぽり入るんですよ
ここでお勧めしたい商品でツイスターボードがあります
段ボールの下に敷いたり、直接乗って、回転刺激を受けれます私がこれを知ったのは知ったのは金魚運動の健康器具のお尻置きです
段ボールに乗って回る動きがとても楽に、そして、簡単に回ることができます。ぜひ試してみてくださいお子さんも別の遊び方を見つけてくれるかもしれません
また段ボールを前後、左右傾けることで、バランスを保とうという身体の動きを促すことができます
これも遊びとして、とても優秀です。安全のために布団やマットの上で行ってみてください
段ボールそり(前庭覚、視覚、固有覚、触覚)
段ボールに紐をくくりつけて大人が引っ張ります。スピード感や、揺れる感覚を楽しんでくれます
前のめりに倒れる危険もあるので、段ボールは奥行きがある、大きめのものが望ましいです
あと普通のひも付きそりでも楽しいですが、段ボールはそこが深く、両手で姿勢を安定させられるという意味で段ボールがお勧めです
段ボールに穴をあけてくくりつける紐は、できるだけ太めのものをお勧めします。細い物だと、大人の引っ張る指がつらくなるからです。ビニール紐の荒縄タイプがお勧めです
商品がアマゾンでなかったので載せられませんでしたが、段ボールの「補強板」と検索すると、紐で段ボールがちぎれない商品が売ってます。まとめ買い用でしたが、あると便利です。買ったら周りに配りましょう!
まとめ
前庭覚を育てることが結果として、様々な成長につながっていきます
ただこれは、前庭覚だけでなく、他の感覚も合わせて考えると、更にやれること、意識できることは多くなり、成長への道筋になります
今後もこのような「感覚」に対してどのようなアプローチがあるか、紹介できたらと思います
関連記事