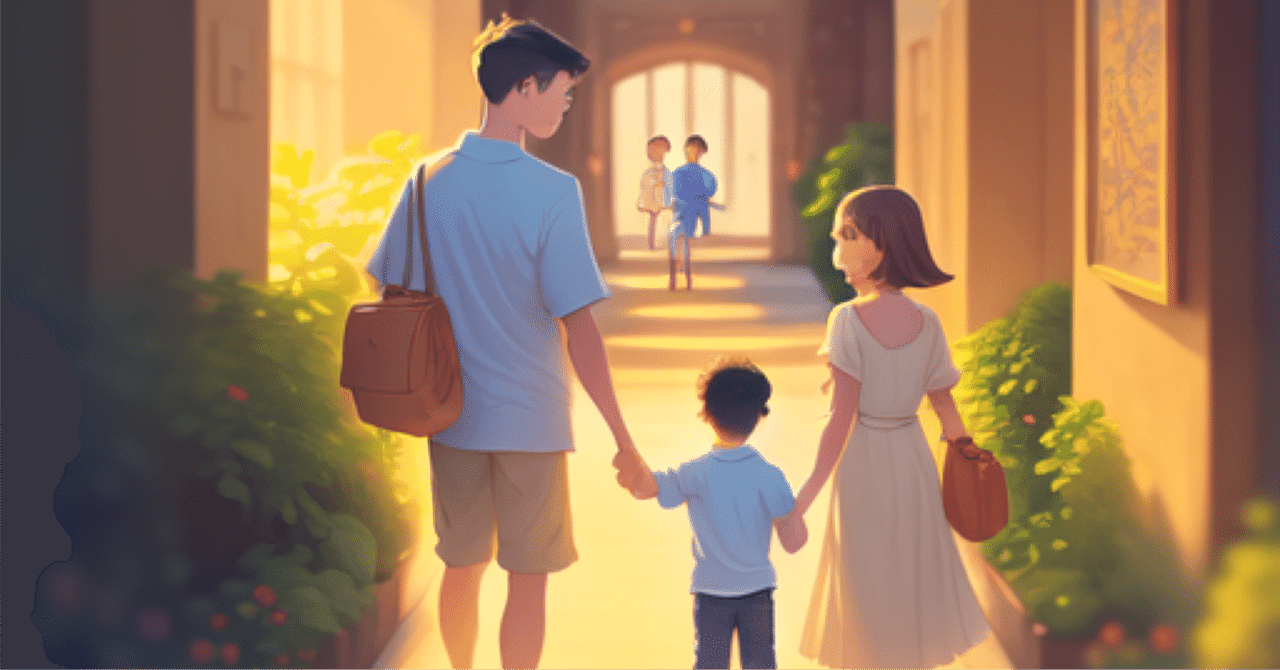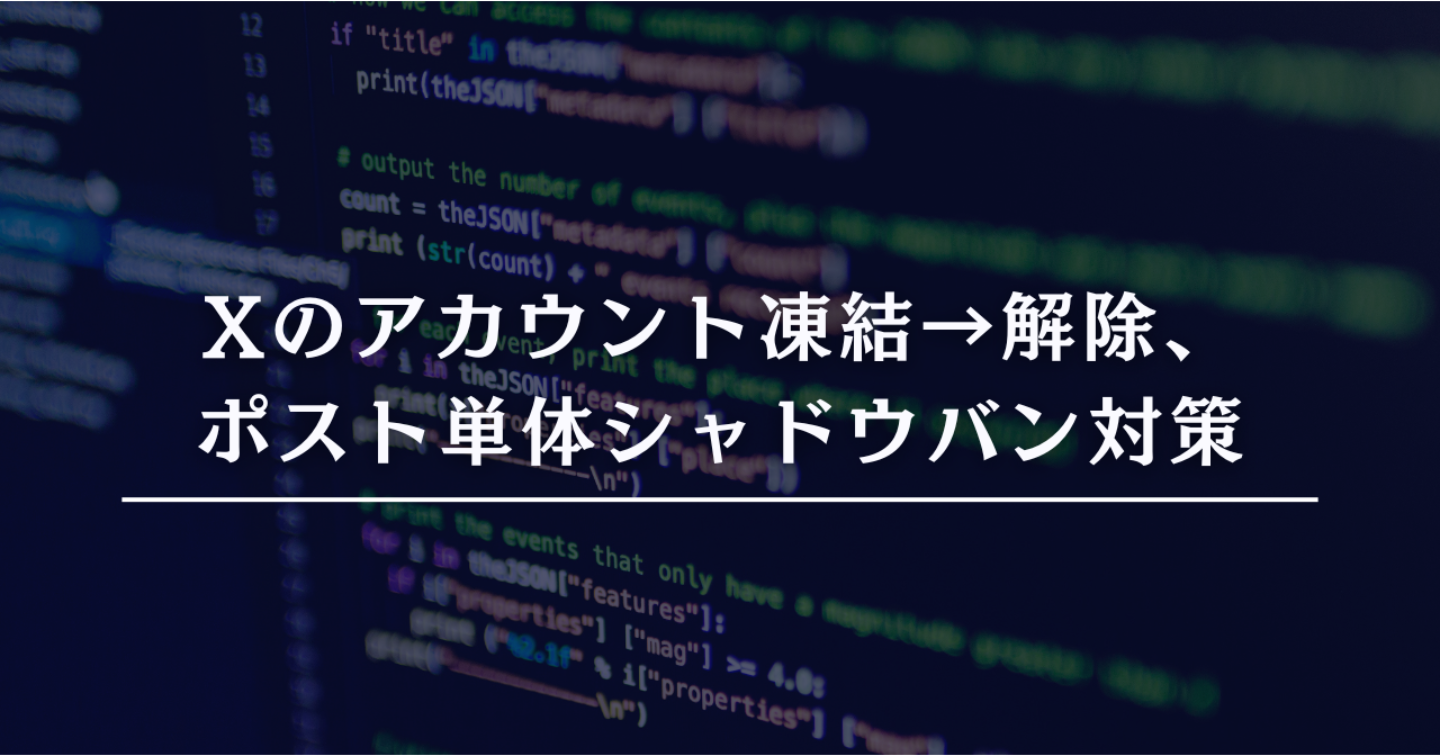感覚統合の領域でみて考えた愛着、愛着障害についてまとめた話②「愛着形成がされていないのは親のせい」とする暴論

絵本作家おがさん 発達支援、心の在り方ブログ
「愛着形成がされていないのは親のせい」とする暴論
「愛着が形成されていないのは親のせい」
というような話をSNSではよく見かけますね
私はこれは「暴論」だと思っています
「子どもの権利条約」において
「児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する」
としています
要するに「お子さんの養育責任の多くは保護者にある」ということです
私はここに不服はありません
しかし、これには続きがあります
「父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する」
「父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる」
これは要するに
「国は、親や保護者が子どもを育てる際に支援を行い、子どもの養育に必要な施設やサービスを充実させ、必要な環境や支援を整える」
ということです
「子育てにおける親の責任が大きい」
というのは当然のことですが、そればかりが一人歩きし、あまつさえ
「お子さんが上手く育っていないのは親の育て方が悪いせいだ」
と決めつける風潮があります
それを結論とするのではなく、「子育て」に関わる事象を社会全体で支えるような意識を持ち、システムづくりをしていく
こともセットで覚えておかなければなりません
社会に属する我々全体の問題として認識することが求められるのです
お子さんの「愛着形成における課題」もその一つとして認識する必要があります
一方で、「子どもの権利条約を批准しているのは国なので、自治体や個人、関係のない他者がそれを求められるのは違う」
という意見も見聞きします
納得させられそうになりますが、それは違います。順番が逆なのです
個人が集まり集団になり、国になり、その過程で
「大事だよね」
という意思や学習の積み重ねが「法律」や「条約」になるのです
子どもの権利条約もその一つです
国が勝手に決めたことだから、と法律や条約を守らない気持ちが生まれているであれば、それは
・「過去の学び」を足蹴にする行為
・自分は関係ないからとサービスだけ享受して自分はやらないという甘ったれた行為
ではないでしょうか
次の記事はこちらからいち早く読めます