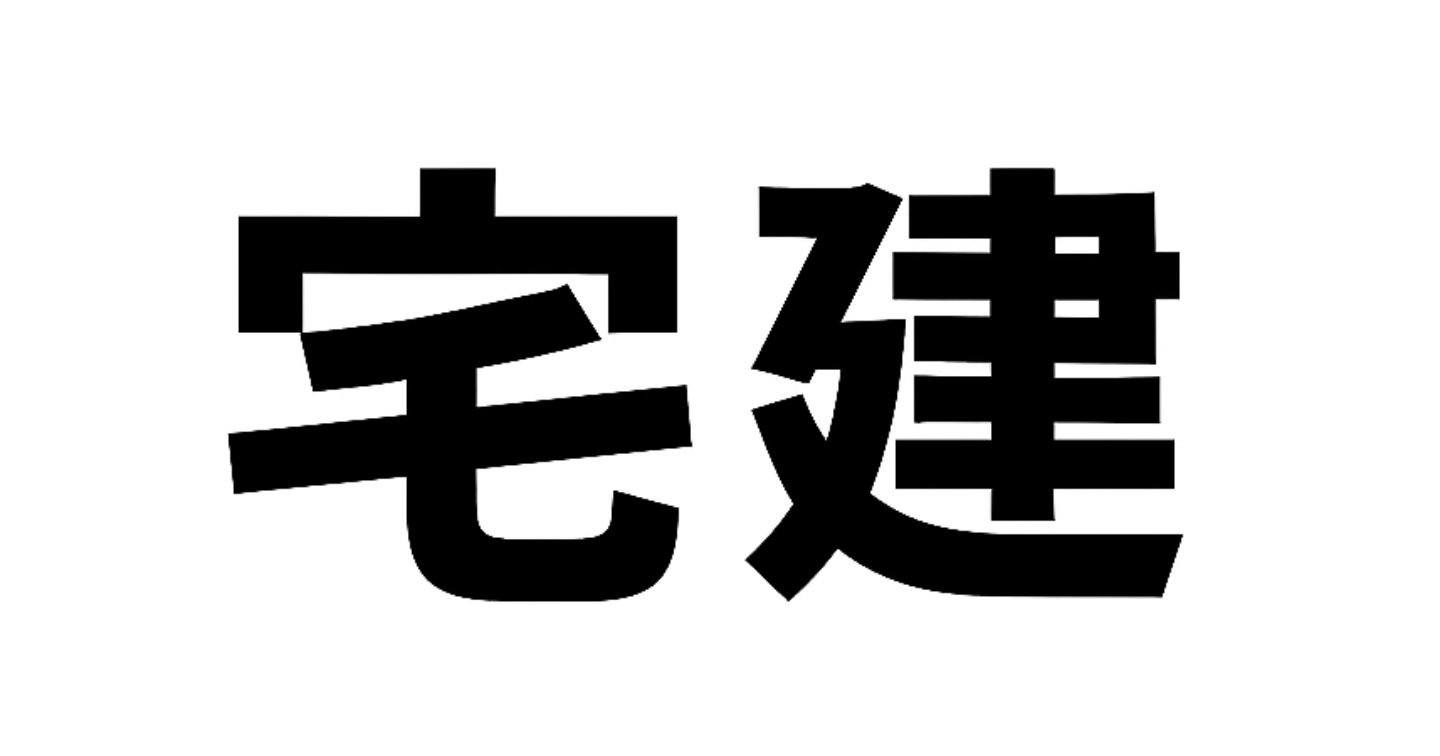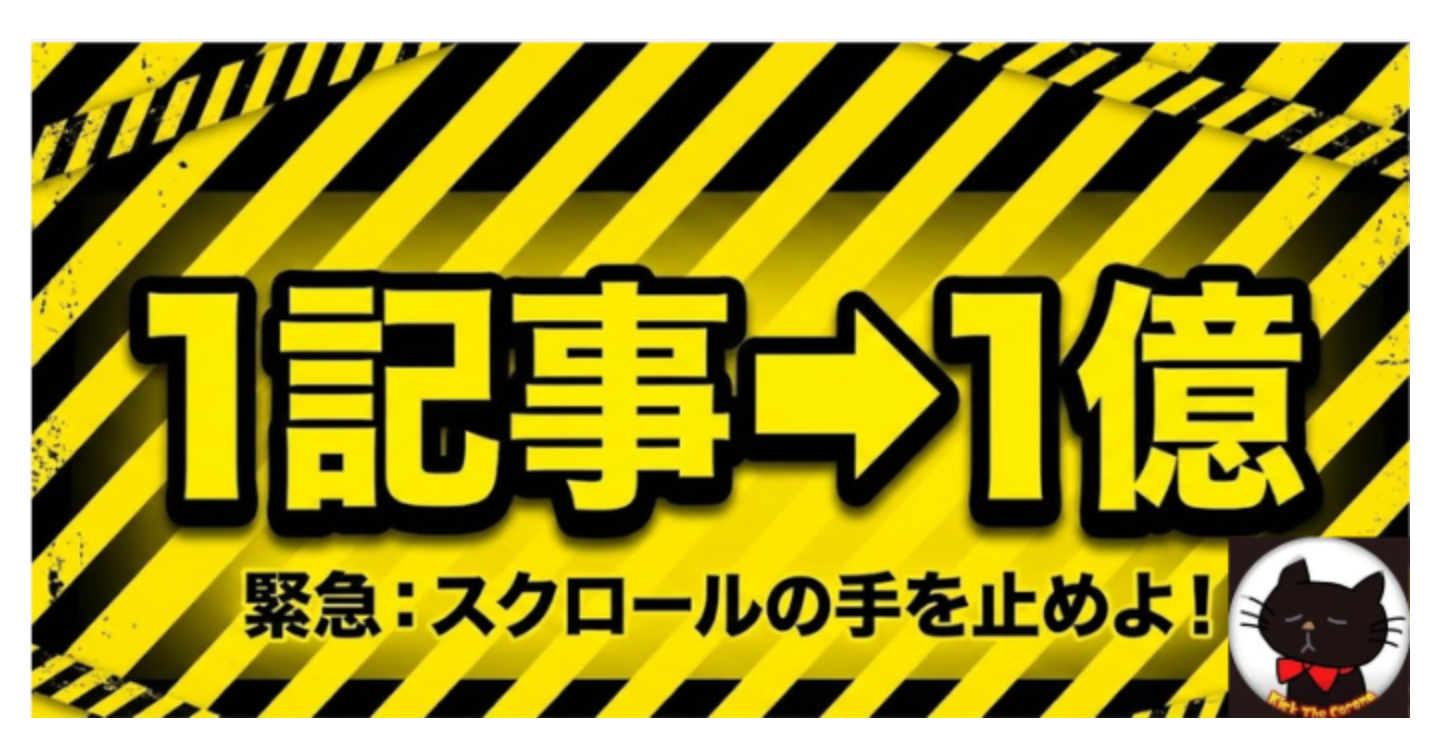私の勉強法と心構え
皆さんは宅建試験について、どんな風に感じていますか?
「難しそう」「自分にできるかな?」など感じている人はいませんか?
でも安心してください。全然そんなことはありません。
私は不動産業界が全くの未経験ですが、独学で挑戦し、合格をしました。
「宅建に挑戦してみたいけど、最初の一歩が踏み出せない」「資格試験に興味はあるけど自信がない」そんな方はぜひ本記事を読んでみてください。
ここでは、私が実践した勉強法と心構えを公開します。
ただし、これは試験合格に特化したアプローチであり、実務に必要なスキルや知識は別途学ぶ必要があります。
その点をご了承ください。
試験概要
宅地建物取引士は国家資格ですが、受験資格に学歴や実務経験は不要です。
20歳以上であれば誰でも挑戦可能です(※合格後の登録には2年以上の実務経験が必要な場合がありますが、登録実務講習で代替可能)。
受験資格
- 満20歳以上であること(学歴や職歴は問わず)。
- 試験は毎年10月に全国の主要都市で実施。
学科試験(択一式)
- 試験時間:2時間
- 問題数:50問(4肢択一)
- 出題範囲:
- 権利関係(14問):民法、借地借家法、不動産登記法など。不動産取引の法的基盤を問う。
- 法令上の制限(8問):都市計画法、建築基準法、農地法など、土地利用の規制に関する知識。
- 税・その他(8問):固定資産税、不動産取得税、地価公示法など。(この8問の中の「その他」の分野に免除科目が5問含まれており、不動産業界従事者は免除対象だが、一般受験者は全50問を受験する必要がある)。
- 宅建業法(20問):宅建士の業務ルールや規制、重要事項説明の詳細。
※ 試験問題は持ち帰り可能なため、試験後に自己採点することが可能です。
合格基準
- 合格点:例年35~38点前後(70~76%)。
- 合格率:約15~17%。戦略的な学習で初回合格が可能。
過去10年の合格率と合格点の推移
| 回 | 年 | 申込者数 | 受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
| 28 | 平成27年 | 243,199人 | 194,926人 | 80.15% | 30,028人 | 15.40% | 31点 |
| 29 | 平成28年 | 245,742人 | 198,463人 | 80.76% | 30,589人 | 15.41% | 35点 |
| 30 | 平成29年 | 258,511人 | 209,354人 | 80.98% | 32,644人 | 15.59% | 35点 |
| 31 | 平成30年 | 265,444人 | 213,993人 | 80.62% | 33,360人 | 15.59% | 37点 |
| 32 | 令和01年 | 276,019人 | 220,797人 | 79.99% | 37,481人 | 16.98% | 35点 |
| 33 | 令和02年10月 | 204,163人 | 168,989人 | 82.77% | 29,728人 | 17.59% | 38点 |
| 34 | 令和02年12月 | 55,121人 | 35,258人 | 63.96% | 4,609人 | 13.07% | 36点 |
| 35 | 令和03年10月 | 256,704人 | 209,749人 | 81.71% | 37,579人 | 17.92% | 34点 |
| 36 | 令和03年12月 | 39,814人 | 24,965人 | 62.70% | 3,892人 | 15.59% | 34点 |
| 37 | 令和04年 | 283,856人 | 226,048人 | 79.63% | 38,525人 | 17.04% | 36点 |
| 38 | 令和05年 | 289,096人 | 233,276人 | 80.69% | 40,025人 | 17.16% | 36点 |
| 39 | 令和06年 | 301,336人 | 241,436人 | 80.12% | 44,992人 | 18.64% | 37点 |
※33~36はコロナにより試験が2回に分けられた。
合格発表
宅建士試験の合格発表は例年、11月下旬に行われます。
試験後の流れ
合格後、宅建士として登録するには都道府県知事への申請が必要です。
実務経験がない場合は、登録実務講習(約2日間)を受講することで登録資格を得られます。
登録後、宅建士証が交付され、正式に業務を開始できます。
心構え
個人的には宅建士試験は、合格ラインに到達するには最低3.5カ月の準備期間が必要だと考えております。
私は7月に勉強を開始し、10月の宅建試験に挑戦しました。
年に1度の試験で、学習ボリュームも多いため、まずは自分の生活環境で勉強時間を確保できるか確認してください。
その上で、本記事をお読み下さい。
過去問だけで合格可能か?
過去問を徹底的にやり込めば、合格圏内に到達可能です。
ただし、やみくもに解くのではなく、計画的に進める必要があります。
ここからは、私が実践した勉強法、効率的なスケジュールを詳しくお伝えします。