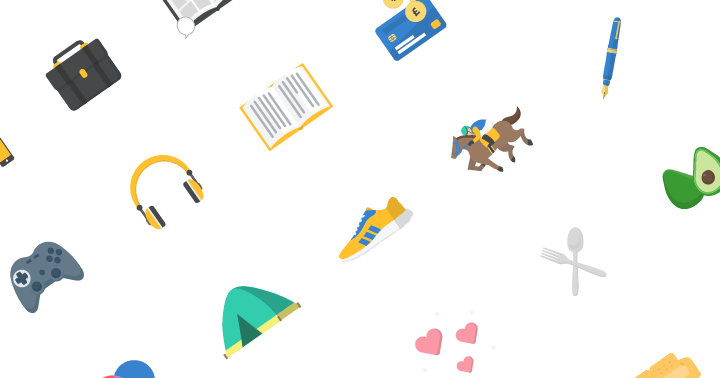【20229-6】No,1

芍薬椿
称号に劣るべきよう乙女が祈る。
与えられた役割に不満はない。
誰もいないことは慣れている。いたとしてもあたしは誰かに何かを伝えられない。封鎖されている。鉄壁の古城に悪い噂がつかないように細心の注意を払い続けた過去が癖としてしみついている。
ベッドの右側と枕の左側にはいつもシミがついている。毎日クリーニングをしても追いつかない。あたしはベッドの左側で寝るし、枕はまんべんなく頭を乗せている。
誰かがこの部屋に入っているに違いない。
でも誰が入ってくる?封鎖しているこの部屋にどうやって。
称号に劣るようあたしは祈りを捧げている。完璧な涙は介入を許さず孤立を形成するには最善にして最高の見せしめだ。あたしの涙はあたしをみせしめるための十字架でありこらしめであり懲罰であり監獄だということを誰かが知ってしまったのか?
いや、知ったとしたら、逆に入ることを遠慮するだろう。踏み込んでまで何かをこじ開ける必要が今ではないことが論証されたと言い換えられるのだから。
目的は?どう考えても、仮説を立てても腑に落ちない。
いくつもの柱が乱立した。建立の過程は時にさまざまだったと思うが、どちらにしろこの柱の盾も援護してあたしの部屋には誰も立ち入ろうとは思わないはずだ。
ベッドのシミは消えることはなく、毎日ご丁寧に必ず右側と左側に残されていた。
称号に劣るように祈る意味も少しずつ薄れていった。薄れてもあたしは心を維持できるまでに世の中に平和が浸透しはじめていたからだ。
眠りは浅い。シミを残す主を見ようと思えばいつでも見ることができた。
あたしはそれをこの数ヶ月やってこなかったことに気づいた。
あたしはそのシミをどこかで恋しがっていたんじゃないだろうか?
そのシミによって何かを保っていたんじゃないだろうか?
幸福にかけられていく橋のような不安を抱いた。答えはきっと何か得体の知れない幸福であろうとあたしは感じた。
彼がいてあたしは生きてきた。彼があたしを守ってくれたからあたしはなんとか生きてこられた。彼はあたしの秘密だ。彼はあたしだけの騎士だ。
言えなかったから、あたしは称号に劣るように祈ってきた。あたしはいつもひとりで生きていた。そう言うことであたしが彼を知らないことの辻褄が合う。
気づいていても言えないあたしの弱さを紀平はどこかに感じていたと思う。いつもどんなときも、出会ったその日から。
あたしは弱さゆえに弱さを隠し、その弱さを知ってくれている紀平に甘えて知らないふりをしていたのかもしれない。
紀平は言わない、あたしも言わない。
だからいくつもの面倒に巻き込まれた。あたしたちの自業自得なのに。
笑い話になるくらいあたしたちは苦さを経験した。
お尻とお尻が触れ合う背中合わせくらいが今はちょうどいい。
長い間あたしたちは知らんぷりをしすぎたから。