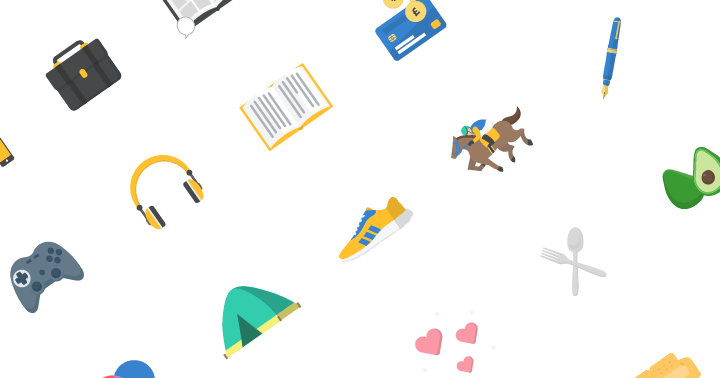感想『扉は閉ざされたまま』石持浅海
ta-e
【あらすじ】久しぶりに開催されることになった大学の同窓会のため、成城にある高級ペンションへ七人の旧友が集まる。和やかな再会の空気に包まれるはずだったその日、伏見亮輔は、客室の一室で後輩の新山を殺害する。そして事件が外部からの侵入ではないと思わせるよう、部屋を完全な密室状態に仕立て上げた。部屋から出てこないことに不審がる友人たちは、扉の向こうで何が起きているのか分からないまま、事故や自殺ではないかと案じる。殺人事件の発覚を遅らせることが犯行計画において重要のため、伏見は出来るだけ死体発見を遅らせようとする。しかし、同窓会の参加者のひとりである碓氷優佳だけは、この状況に拭いきれない違和感を覚える。閉ざされた扉の外で、扉を開けさせようとする彼女と犯人の伏見との間で、緊張感あふれる知的な駆け引きが静かに始まっていく。
この作品はミステリー小説でありながら、従来のミステリーのお決まりである「死体が発見されてから推理が始まる」という定型を大胆に裏切っている斬新さが特徴である。
物語は倒叙形式で始まり、読者は早い段階で犯人の正体と犯行の手口を知ることになるが、その代わりに「なぜ殺したのか」「なぜ扉を閉ざしたままにしておく必要があるのか」という二つの謎は読者に残される。
密室は開かれない(そもそも密室と認識されない)まま、事件性の有無すら確定しない状態で論理が積み上げられていく構成は、ミステリーというジャンルそのものに対する挑戦といえるだろう。
そして、同窓会の参加者全員が集まる中で、犯人・伏見亮輔と探偵役・碓氷優佳の間だけで水面上で展開される緊張感あふれる駆け引きが特に読みごたえがある。派手なアクションや劇的な展開はなく、会話と推論だけで物語が進むにもかかわらず論理の繋がりの美しさが読者の読む手を止めさせない。
登場人物のほとんどは事件に気づいていないため、推理や謎を積極的に暴いていくべきという雰囲気にはならない。同窓会という安心した空間では、人は最悪の事態を想像したがらない。その心理を巧みに利用した犯行と、そんな中、碓氷の脅威の洞察力により冷徹に主張を切り崩していく鮮やかな対比が綺麗だ。死体も物証もない段階で殺人の可能性を見抜いていく姿は、恐ろしさすら感じさせる。読者は犯行を知りながらも、論理がどこへ辿り着くのかを見届けずにはいられない。
最終的に扉は開かれるのかどうか、犯行の動機は何か、読者に強力な余韻を残すラストまで、著者の論理に酔いしれることは必定である。