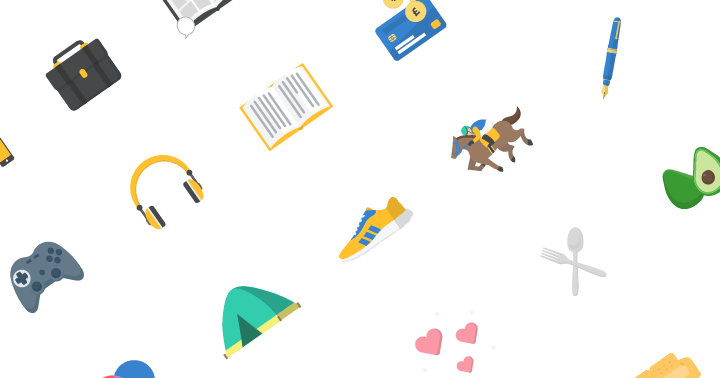by つづき こう
第1章 出会いの方程式
その日、私は予定より早く喫茶店に着いてしまった。店内はまだ空いていて、窓際の席に座ると、午後の光がテーブルに柔らかく落ちていた。
数分後、彼女は小さく会釈をして入ってきた。最初に見た印象は、とあるアイススケーター兼タレント似だった。今時の若い子らしい化粧と髪型、よくある大学生の雰囲気。だが、席に座り、私の問いに答え始めた瞬間、予想が覆された。
「前回はいろいろお話ができて楽しかったです。今回もいろいろなお話ができることを楽しみにしています」
そう言ってきたのは、まだ二度目に会う前、LINEで送られてきた言葉だった。パパ活という場で、そんなことを言う子は今までひとりもいなかった。多くは「条件は?」「いつ会えますか?」とか、定型句の連発。誰もが形式的に礼儀を整えるだけで、「楽しみ」とは口にしない。だが彼女は違った。
私はそのとき、彼女のことを「珍しいキャラクター」と直感した。
––この子は話がしたいんだ。そう感じさせる一文だった。
そこで私は、話す準備を始めた。私は昔から、相手が言葉を投げてくれるなら、その言葉の輪郭を磨き返すのが好きだった。質問ノートを作り、見取り図を描く。最初から、私は彼女に「質問したい」人間になっていたのだと思う。
実際、彼女と向かい合ってみると、その「話したい欲」は確かにあった。初対面の緊張はあっても、こちらが投げる質問にはきちんと考えて答える。時に間を置き、時に笑いながら。
私は、心の中でペンを走らせる。
-自己肯定は高い。だが「謙虚」を選び取る言い回しに習熟している。
-物語を生きるタイプ。記憶のディテールを残す。
さらに会話を重ねるうちに、彼女のパーソナリティが一段と見えてくる。
幼少期からバスケを続け、中学ではキャプテンも勤めた、そこで培ったのは、判断の速さと自信だという。挫折経験は「試合で1点差で負けたこと」くらいしかなく、「自分は世渡り上手だと思う」と平然と言い切る。
一方で、自己肯定感は高くないと口にする。だが、実際は矛盾していた。承認欲求は強いのに、自分を卑下する言葉を並べる。「ネガティブなんです」と言いながら、実際は明るく、楽天的に見えた。自分を下げることで、逆に「そんなことないよ」と言われたいのだろうか。私はそう感じていた。
LINEでもその傾向は見えた。
「面白いって言われると悪い気しないです」
「そらそうでしょ。みんな君のこと会ってみたいって言うよ」
「えー?でも自分から誘うのはできないです。誘っていいのかなって思っちゃう」
そんなやりとりの中で、私はさらに「質問魔」になっていた。彼女の生育歴、価値観、好きな映画、親との関係 とにかく聞きたいことが次から次へと湧いてくる。彼女も嫌がらず、むしろ答えることを楽しんでいるように見えた。
彼女は「親に甘やかされてきたとは思わない」と言うが、iPhoneやアップルウォッチを当然のように買い与えられている。家族仲はきわめてよく、反抗期もなく、食卓は夜9時を過ぎてもそろって共にする。月1回は外食もする。「守られている」実感は薄いと言いながら、実際には手厚く守られている。そんな矛盾もまた、彼女らしかった。
パパ活の動機を尋ねると、即答だった。
「好奇心8割、お金は2割ですね」
金銭目的でないからこそ、彼女は時給換算でトクしても平気でこちらを切る。バイトの時給1500円よりも、こちらの方が割がいいのに、彼女はバイトを優先する。その矛盾が、後に大きな衝突を生むことになるのだが、この時点ではまだ気づかなかった。