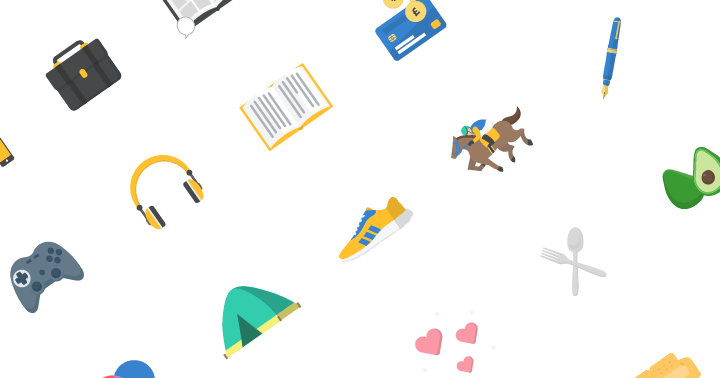だから、選んだ。

みき
「はい、次の者」
とくに名を呼ばれることなく、一列に並んだ靄のかたまりがひとつ、またひとつと消えていく。
どこへ行くのかは、後方でただ呆然と見つめているだけの御魂は知る由もない。おそらくほかの者も。
ここには『闇』しかないはずなのに、奇妙なことにかろうじてモノが認識できる不思議な空間。異臭も芳香もなく、ただ列が『視える』だけ。
ところてん式にどんどん押され、ついにその御魂が招かれる。ある一点だけ、あたりの闇より深い闇がぽつんと穿たれていた。
どうやらさきに行った者たちは、ここを通ったようす。
「次はお前か?」
唐突に無機質な声音が降りそそぐ。はるかな高みから、厳かな雰囲気がしめつける。
背後を振り向けば、延々と続いていた行列がなくなっていた。
はぐれた覚えはなく、かといって後方の連中がさぁ、と消失したわけでもなく。
「お前、と訊ねたのだが? 聞いているか? 聞こえているのか?」
無愛想な声は性別不明。姿も影もない。
まわりにこの御魂以外の存在は確認できないから、その代名詞は、こちらに向けられたのを受け入れた。
「……どんくさいやつだな。ほら、さっさと《企画書》を出せ」
面前にほのかに輝く右手が現れた。ぎょっとした御魂はわずかに後ずさりする。嘲笑が聞こえたのは気のせいか。
さっさと寄越せ、無言の催促はしかし、御魂はまったく意味が解らないでいた。そもそも《企画書》とは何のことだ? 考えあぐねていると、しびれを切らした風情の右手は無造作に御魂の前面に突っ込んできた。
触れた瞬間、弱い火花が飛び散った。瞬き一つで右手は何かを取り出してブツブツと小言をつぶやく。陰湿な気配はなく、複雑そうな、それでいて物悲しい声をもらす。
「ずいぶんと、まぁ……。『これ』でいいのか?」
右手『だけ』だったのが、淡い光をまといながら姿を現す。と同時に、背後から勢いよく突き飛ばされた。
バシャン、水のなかに叩き落された感覚。これはなんだろう? だが、先ほどまでいた空間とは比べ物にならない快楽が、全神経に伝うのはどういうことなのか。
結局、姿ははっきりと認識できずにその場を離れてしまう。
◆ ◆ ◆
ずっと、肌を知らないでいる。
きっと、明日は頭に乗る手はやわらかいはず。
もっと、みていてほしかった。
どれも違った。つまらない夢をまだ追い続けていた。