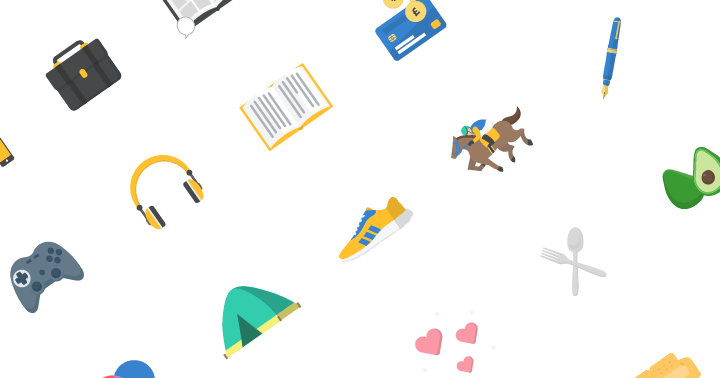■主人公
及川 美奈子(31)警視庁捜査一課・特命刑事。黒髪ショート、白のミニスカスーツを身にまとう。既婚、身長167cm、体重60kg、股下77cm、バスト93cm、太もも周り63cm

第1章:血の招待状
濃い霧が山間の道路を覆い、遠くの森が白く霞んでいる。
――ハンドルを握るのは、警視庁捜査一課・特命刑事、及川美奈子(おいかわ・みなこ)。31歳。白のミニスカスーツに包まれた肉感的な肢体、特に胸元のボリュームは目を引く。黒髪のショートカットと鋭い目元が、彼女の冷静な判断力を物語っていた。

助手席には、夫の**及川悠介(ゆうすけ)**が座っていた。

都内の小さな広告会社に勤める温厚な性格の男性で、美奈子とは大学時代に知り合って結婚した。
「……やっぱり、行くのか?」
その声に、美奈子は小さく頷いた。
「警視庁からの特命よ。断れないわ。それに……妙に気になるの」
「何が?」
「“ドラキュラ伝説”よ。あの村で、実際に人間が血を抜かれて殺されているっていう話。ふざけた話に見えて、過去にも失踪者が続出してる。偶然とは思えない」
目的地は、山間にある夜神村(やがみむら)。人口わずか300人足らずの集落。近年では“吸血鬼伝説の村”として一部で都市伝説のように語られていた。
昨夜、村の旧家“鴉屋(からすや)家”の当主が、自宅のベッドで首筋に二つの傷を残したまま死亡しているのが発見された。

しかも、遺体はまるで“血を吸われた”かのように貧血状態で、死因不明。
地元の警察は「自殺の可能性もある」と言いながらも、どこか腰が引けている様子で、警視庁に捜査支援が依頼された。それを受けたのが、美奈子だった。
やがて、霧が晴れていく中――村の入り口に到着した。
木製のアーチには、煤けた文字で「夜神村へようこそ」と書かれていた。どこか不気味な静寂が、山全体を覆っている。
「……なんだか、空気が重いわね」
「美奈子、本当に気をつけて。夜は……なるべく一人にならないでくれよ」
「大丈夫よ。私、刑事だもの」
冗談めかして笑いながら、美奈子は助手席の悠介の手を軽く握る。
「3日以内に戻るわ。……無事にね」
それが、夫婦の最後の平穏なやりとりになるとは、まだこのとき誰も知らなかった。
***
村の中心には、石畳の道が続いていた。年季の入った木造の民家が並び、道ゆく住民たちの視線がどこか異様だ。よそ者を嫌う空気が、露骨に漂っている。

美奈子は村役場で、事件担当の村長・早乙女誠司に出迎えられた。60代後半、やせ細った体に古びたスーツ。どこか影のある男だった。

「遠路ご苦労さまです、警視庁の及川刑事。……この村のこと、よく知らずにいらしたのでしょうが……お気をつけください」
「警察が介入するということは、重大な事件と判断されたのですよね。私もそのつもりで来ています」
「ええ……ええ。ですが、ここでは“常識”が通用しないこともあります。特に……夜は」
意味ありげな言葉に、美奈子は眉をひそめた。
「どういう意味です?」
「……夜、外を歩いていると、“呼ばれる”んです」
村長は一瞬だけ、何かに怯えるように辺りを見回した。
「“ドラキュラ様”にね」
***
被害者の遺体が見つかったのは、村の奥にある鴉屋家――400年以上の歴史をもつ名家であり、村の開祖とも言われる血族だという。
屋敷は黒塗りの木壁に囲まれ、まるで洋館のような陰気な佇まいだった。

美奈子は案内人として同行した村長と共に屋敷に足を踏み入れる。出迎えたのは、鴉屋家の当主の妹――**鴉屋麻璃(まり)**と名乗る女性。40代後半、美しいが何かを隠しているような目をしていた。
「兄が……このような最期を迎えるとは。鴉屋の血筋は、とうとう呪われたのかもしれませんわね」
「呪いというのは、何を指しておられるのですか?」
「この村には“契りの儀”という古い風習があります。“鴉の契り”と呼ばれていて……鴉屋の血を守るために、婚姻や供物として他家の娘が差し出されるの」
「供物、ですか?」
「ええ。……今も年に一度、“祭壇の扉”は開くのです」
その言葉の意味を問おうとした美奈子の前で、突然、奥の部屋から扉がきしんで開いた。
中から現れたのは――白髪まじりの老人。
「ほう、刑事さんとは随分若い。しかも……ミニスカとは、実に大胆な格好じゃ」
男は鴉屋家の執事・市村宗一郎と名乗った。70代とは思えぬ背筋の通った立ち姿。だが、目は蛇のように細く、冷たい光を宿していた。
「ミニスカも、警視庁の流行かね?」
「職務に必要なら、どんな格好でも致します。重要なのは中身ですから」
胸を張って堂々と応じる美奈子。その胸元の膨らみが、わずかに揺れる。
「ふむ……中身ねぇ。確かに君の“器”は、大したもののようじゃ」
品のない視線をあからさまに向けてくる市村。だが、美奈子は一切動じなかった。
「被害者の遺体を見せてください。詳細な検視と撮影を行います」
やがて案内された寝室には、すでに遺体は運び出された後で、血痕と枕に残された歯型のような傷跡だけが残っていた。
「……まるで、映画の吸血鬼に噛まれたみたいですね」
「村の者は、皆そう言っておりますよ。……“ドラキュラ様が蘇った”とね」
村長がぽつりと漏らす。
「では、ドラキュラの正体は誰なのか。私はそれを調べに来ました」
美奈子はそう言い残し、寝室を後にした。
彼女の背に、村長と市村の視線が静かに交差する――まるで、獲物を待つ獣のように。
第2章:吸血鬼の館
夜神村の空に、早くも夕暮れが迫っていた。日の落ちるのが早く、あたり一帯はすでに茜色の闇に包まれつつある。夜神村の空に、早くも夕暮れが迫っていた。日の落ちるのが早く、あたり一帯はすでに茜色の闇に包まれつつある。

及川美奈子は、村のはずれにある小さな民宿へと荷を下ろした。村にある唯一の宿泊施設であり、警視庁の手配で確保された部屋だった。
「やっぱり……寒いわね、この村。空気がひんやりしてる」
美奈子はそう呟きながら、上着の裾を整える。だがミニスカスーツから伸びた脚線美は、冷気をものともせず毅然と立っていた。
窓の外には、山の稜線がくっきりと浮かび、黒く沈んだ森が広がっている。その中心に、まるで化け物の口のような裂け目がぽっかりと空いていた。
「“森の裂け目”……?」
ふと、何かを思い出すように視線を凝らしていたとき、部屋の扉がノックされた。
「失礼します。……夕食のご案内に参りました」
現れたのは、民宿の娘・橘さゆり。20代後半、明るく気さくな笑顔の持ち主だが、どこか常に警戒心を漂わせている。

「さゆりさん、この村で“ドラキュラ”って呼ばれている人物について、何か聞いたことはある?」
食堂へ向かう途中、美奈子はさゆりに尋ねた。
「……ドラキュラ様、ですね。ええ、みんな“冗談だ”って言いますけど、でも……誰も夜の森には近づきません」
「なぜ?」
「昔から言い伝えがあるんです。“月の無い夜、鴉屋の血筋が覚醒する”って……それが“ドラキュラの夜”」
「吸血鬼伝説……鴉屋家に?」
「ええ。でも私が小さい頃から、夜になると奇妙な声が聞こえてたんです。うめき声とか、笑い声とか……それに、祭壇の方から、誰かを引きずる音も」
その言葉に、美奈子は立ち止まる。
「“祭壇”って、どこに?」
「森の奥……“鴉ヶ洞(からすがほら)”って呼ばれる場所です。誰も近づきません。今は封印されてて、入れないはずですけど……」
さゆりがそう言った直後、店内のラジオから、奇妙な放送が流れてきた。
『――鴉は、血を啜る。夜が来た。契りを果たせ』
「……なに? いまの……」
「これ……村内放送じゃないです。誰が流してるのか、みんな知らないんです。決まって、誰かが死んだ日の夜にだけ、これが流れるんです」
美奈子の背筋に、ぞわりと冷たいものが走った。
***
その夜、美奈子は宿に戻ってから、夫の悠介に連絡を入れた。
『元気にしてるか?』
「ええ。ちょっと変な村だけど、大丈夫。そっちは?」
『うん……でも、ニュースで見たよ。血を抜かれた死体って……なんか、怖い事件だな』
「たしかに。でも、怖がってるだけじゃ、犯人は捕まらないから」
『……お前は昔からそうだよな。強くて、まっすぐで……でも、あんまり無理するなよ。誰よりも、お前の無事が心配だから』
画面越しに映る夫の顔が、切なげに微笑んだ。美奈子はほんのわずかに唇を緩め、そっと画面を撫でる。
「ありがとう。……帰ったら、一緒にあったかい鍋でも食べましょ」
『約束だぞ』
画面が消えると、美奈子は窓の外を見た。
そのとき――森の方から、確かに聞こえたのだ。
――ズリッ……ズリッ……
何かを引きずるような音。そして、低く湿った呻き声。
「……!」
すぐにスーツの内ポケットから小型ライトと拳銃を取り出し、美奈子は外へ出た。
冷気が肌に刺さるようだ。だが、それを振り払うように美奈子は足を進めた。
音の主は……間違いなく、森の方角だ。
***
20分後――。
森の入り口にたどり着いた美奈子は、古びた木製の鳥居の前で足を止めた。
「“鴉ヶ洞”……ここか」
だが、鳥居の向こうには、朽ちかけた鉄の柵があり、“立入禁止”の札がぶら下がっていた。
その瞬間――カサリ、と背後で枯葉を踏む音。
振り向くと、誰もいない。だが、確かに“気配”がある。
そして次の瞬間――。
ガシャンッ!!
足元の土が崩れ、美奈子の体が地面ごと落下した。

「くっ……なっ……!?」
落下の衝撃で気を失いかけたそのとき、彼女の足首に何かが絡まり――
ギチッ!
ロープが締まった。美奈子の体が空中で止まり――
逆さ吊りになっていた。

白のミニスカスーツが宙で揺れ、豊かな胸が逆さまに持ち上がる。