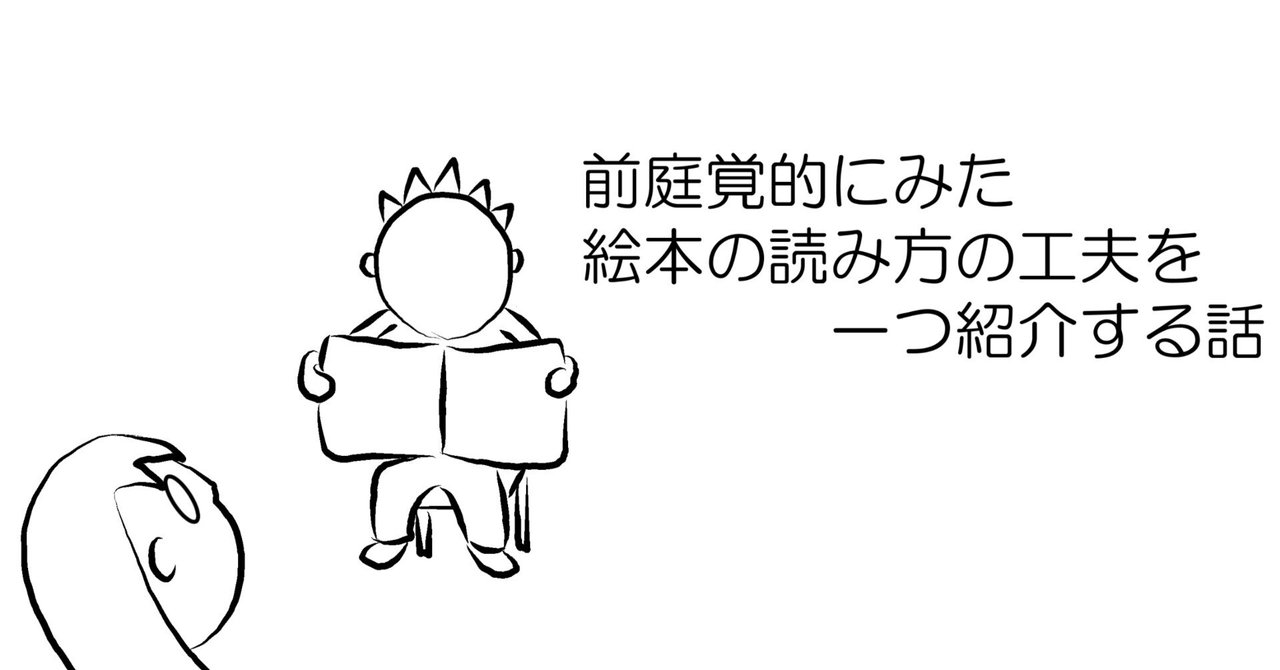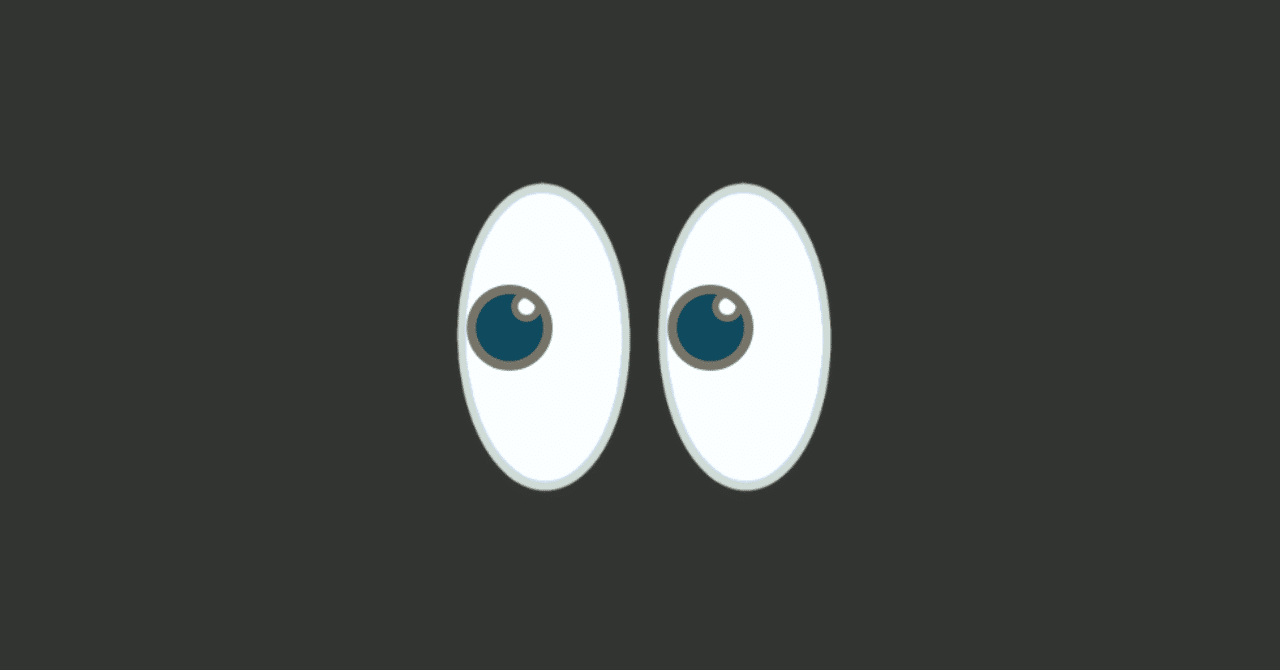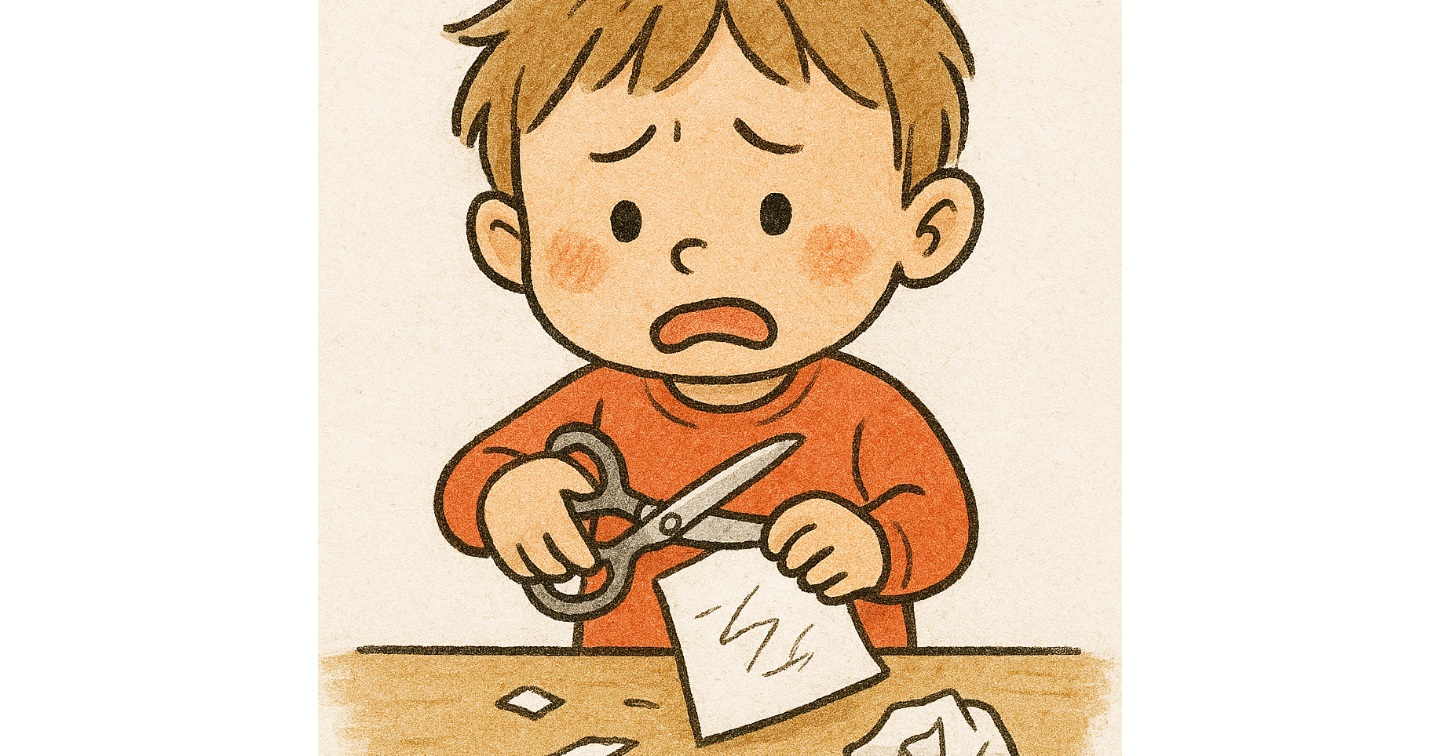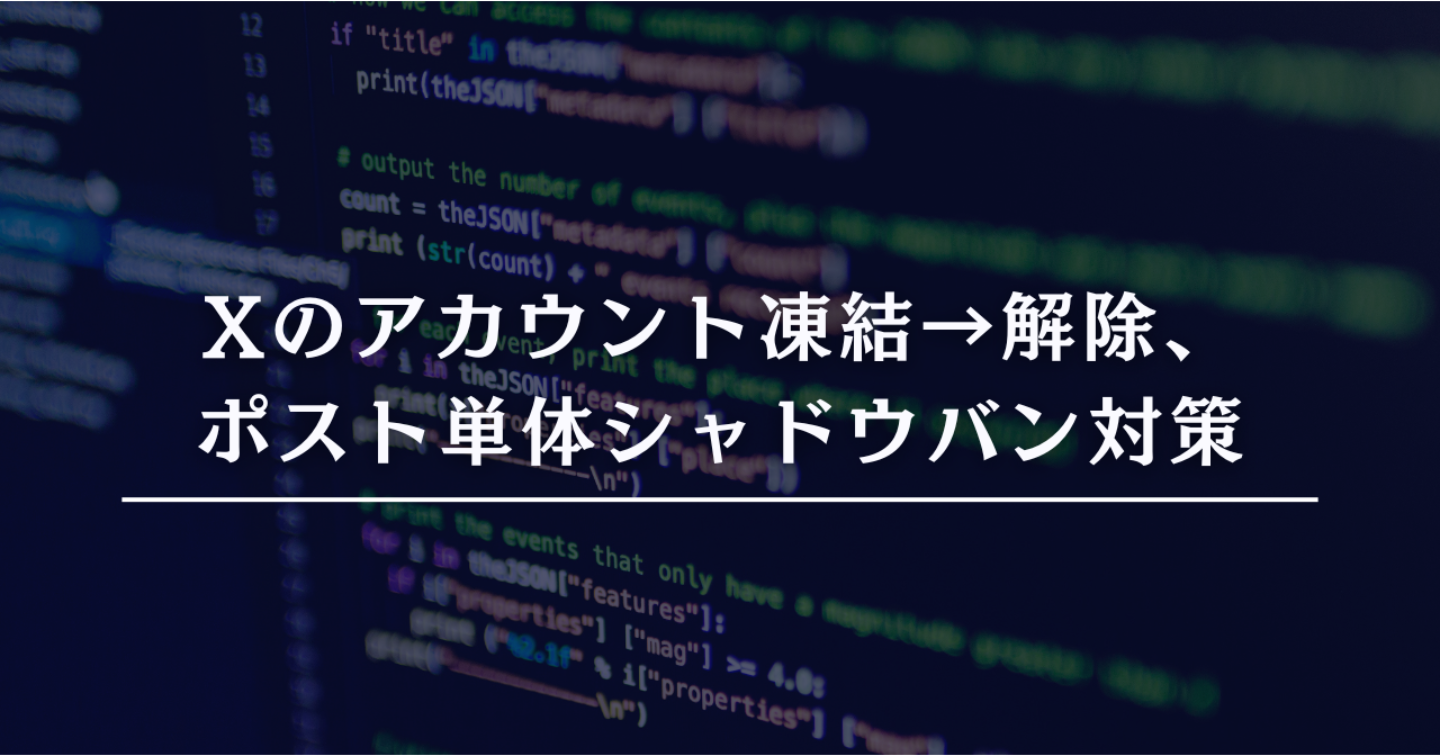お子さんの絵本選び 悩みますよね
ご家族からのご相談の中には、「年齢に合わせた絵本を読んでくれない」というものもありました
ありますよね お子さんの年齢に合わせた絵本が送られてくるサービス
しかし、そういった絵本があるのにお子さんは読まない…
読めよ!
という気持ちも大いに理解できます
私の経験からすると絵本は
「本人が楽しめるもの」を選んだ方がいい
という結論に達しています
無理に年齢に合わせる必要はありません
今回はその理由をまとめていきたいと思います

「楽しい」と思えるということは…
「楽しい」と思えることは脳の構造的に意味があります
感覚統合的に言えば、脳の感覚統合機能が発達し、環境(この場合絵本)からの問題にぶつかってもそれに対応できると
「楽しい」と感じるのです(適応反応と言います)
絵本を視覚的に処理し、それが脳の脳幹へ行き、筋肉や前庭覚と関連付けたり、大脳皮質などにも入力がいき言葉や絵の理解につなげる
こういった流れができることが「感覚統合」なのです
つまり「楽しい」と思えるということは「感覚を上手く処理している」→「次の適応反応につながる」
という成長の過程と言えるのです
逆を言えば、「楽しくない」ということはこの過程がないということ
楽しくないばかりか、お子さんの脳、身体の成長にも影響があると解釈できるのです
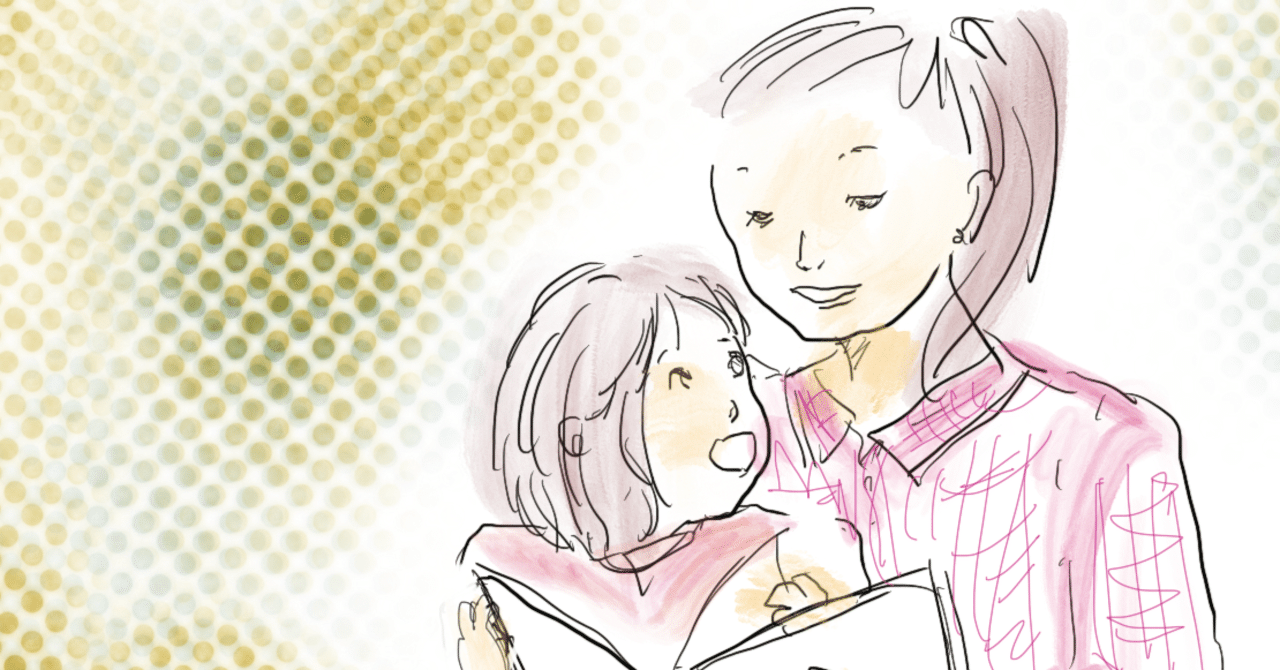
楽しいと思えることを分析、派生を探す
なので、お子さんの楽しめる絵本が「どんなものか」を分析していくことが大切です
例えば
だるまさん
ペンギン体操
こういった絵本は「見て」(視覚)「聞いて」(聴覚)「身体を動かす」(前庭覚、固有覚)
といったお子さんの感覚を引き出す絵本と言えます
これを楽しめるお子さんはその部分の「感覚統合」はできている、「楽しんでいる」と言えます
この絵本だと感覚運動発達メインの感覚統合と言えますね。感覚が育つことで基盤に徐々に心的、社会的なものにステップが上がっていきます
すーべりだい
だめよデイビット
バムとケロ シリーズ
徐々にストーリーやキャラクターの感情や表情なども意識できるようになってきます
心的、社会的な力が伸びてきているということですここまでくると、本人が「こんな本が読みたい」という興味・関心も出てくるので、そこから更に絵本への興味が広がっていきます

私の中では「絵本」はお子さんの
「感覚を育てる遊具」
「お子さんの成長を見極めるツール」
「子どもと関わるコミュニケーションツール」
として活用しています
それは絵本が「楽しい」と思えるからこそですし、「楽しい」からこそ「本当の自分」を見せてくれるのです
関連記事