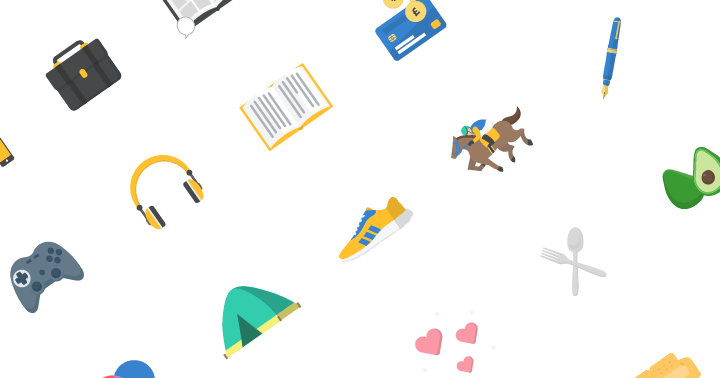今は昔、神話の時代といわれるまで遡るあの頃は空を鳥類が、海は魚類が、地上は人類だけが収めていた。それぞれの領域を侵犯することを恐れながらも、時に戦を交える点でも現代とはなんら変わらない、愚かさと愛おしさと儚さがあった。
鳥類は翼を持ち、魚類は水掻きと尾鰭を有し、人類は目を4つ持っていた。2つの目は物質界を、残りの目は霊界を見ることができた。幾度の戦争の後に、このオリンポス問われた世界は箱に詰められてしまった。箱は小さく、オルゴールのように細工がされており、2022年の現在においてアンティークを思わせる可愛らしいありふれた見た目であった。
この箱をパンドラが管理していた。朝黒い肌、漆黒のロングヘア、いつも誰とも交わらずお屋敷のなかで音楽を奏でている。それは噂の域を脱することはなかった。パンドラは街の人々から見ると異質で、なおかつ、自分達とは関われない別世界の亜種だと判断されていたからだ。実際にパンドラと出会ったことがある人は多くはなかった。
ちなみに、このパンドラが箱を管理していることは世間は知らない。なぜなら、かつてのオリンポスの存在はすでに過去のものであり、歴史に埋もれる以上に神話としてさらに不確かという常識が世に広まっていたからだ。
ひとりの鷹匠がいた。黒尽くめであることを私たちは不思議に思うべきであったのだが、概念がすでに埋め込まれており気づくことさえ操作され気づくことができなかった。「森の中で目立たないようにであろう」。たしかに木々の緑にまぎれやすいといえばそうかもしれないが、ビロードの黒は鷹匠が活動する森では不向きだ。
鷹匠の鷹は犬鷲だ。巨大で獰猛だと私たちはまたひとつが稲園を操作されているのだがそのことにも気づかない。
犬鷲は鷹匠が行けといえば、どこへでも指示通りに任務をこなした。
犬鷲はある日、パンドラの部屋の窓を蹴破り、管理していた箱をひっくり返した。
パンドラは眠りから目覚めていたし、犬鷲の侵入を予見していた。
だから慌てることなく、ガラスの割れる音にも目を見張ってベッドの中でその出来事を静観していた。
「ああ、その時が来たのね」とでも言わんばかりだった。
世界にオリンポスが満ち溢れた。犬も猫も、蛇も象もライオンも羊も、ありとあらゆる地上の生き物が塵に帰された。人々は驚くばかりで、脆弱なメディアもこのとばかりは一致団結し、その一部始終を真剣に報道し、また、一部始終を本物の専門家に分析させた。
鷹匠は犬鷲と同化し、空を統べる王となった。そして高らかにオリンポスの再興を宣言した。
「パンドラたちに世界を背負わせるべきではない」と。
水掻きと尾鰭のある魚類は訝しがる。
「おかしいじゃないか。パンドラはひとりだったはずだ」
「そうだ、浅黒い肌に漆黒の髪、音楽を愛する乙女であるはずだ」
人類の目がふたつだったのは今は昔。昔から見つめたこの今の人類は目が4つある。ふたつはこの世界を見るために、もうふたつは霊界を覗き込むために。
人類は言葉にせずともその霊界を覗き込んで理解した。
ーーーパンドラは姉妹だった。ひとりは肌が黒く、ひとりは肌が白い。髪の漆黒も印象であっただけで、光の加減で変幻自在だった。そして音楽を愛するふたりの乙女が持っていたふたつの楽器はふたつの声だった。
パンドラの姉はパン、パンドラの妹はパンドーラーと言った。
パンは「すべてのもの」を意味し、パンドーラーは「すべての贈り物」を意味する。
犬鷲と鷹匠と同化し空を統べる王となった時、海の中でも時代が変革の時を迎えていた。
パンドラの箱がひっくり返る少し前のことだった。