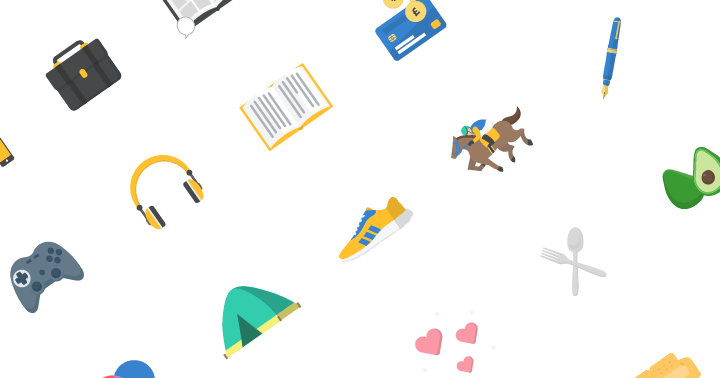前書き
なぜマグダーマ半島に行こうと思ったのか、今となっては思い出せない。日常の何もかもが嫌になったのか、それともただ、地図の端に突き出たその名も知らぬ場所の、乾いた響きに惹かれただけなのか。人々が「灼熱と風の牢獄」と呼ぶその場所へ、僕はほとんど衝動的に飛び込んだ。肌を刺す砂、息苦しいほどの熱波、そして文明の理不尽さを洗い流してくれるかのような、絶え間ない風。この旅は、何かを求める旅ではなかった。むしろ、何かを捨てるための旅だったのかもしれない。これは、僕が砂と風にまみれ、人間という生き物の原点に触れた数日間の記録である。
1章 熱砂の洗礼
風の街への道
空港の扉が開いた瞬間、ドライヤーの熱風を顔面に叩きつけられたような衝撃があった。これがマグダーマの洗礼か。湿度のない熱が肺を焼き、一瞬で全身から汗が噴き出す。乗り合いの古いワゴン車に乗り込むと、車内はすでにむせ返るような熱気と、香辛料の匂いで満ちていた。
舗装路はすぐに途切れ、車は赤茶けた荒野の轍を跳ねるように進み始めた。窓の隙間からは容赦なく砂が入り込み、数十分もすれば髪も服も、そして口の中までもがザラザラになった。窓の外には、風によって奇妙な形に削られた岩と、どこまでも続く砂の海が広がるだけ。同乗している地元の人々は、この過酷な環境に慣れきった様子で、時折僕を見ては白い歯を見せて笑う。その表情には、同情でも嘲笑でもない、ただ「ようこそ」という響きがあった。
2章 風の街、ザラハでの一夜
迷宮の路地裏
数時間後、土壁の家々が密集する街「ザラハ」に到着した。ここは、絶えず吹き付ける強風から身を守るために作られた迷宮のようだった。建物は低く、道は迷路のように入り組んでいる。ゴーゴーと唸りを上げる風の音だけが、この街の支配者であることを示していた。
宿を見つけ、部屋の扉を閉めると、ようやく風の轟音から解放された。まずはシャワーを浴びる。ぬるい水が、皮膚にこびりついた砂と汗を流していく。排水溝に溜まる泥水を見ながら、まるで自分の中の澱のようなものまで一緒に流れ落ちていくような、妙な爽快感を覚えていた。
3章 闇市の饗宴
サソリとバッタ
陽が落ちると、街の中心にある広場に闇市が立った。裸電球の薄暗い光の下、人々がひしめき合い、得体のしれない活気が渦巻いている。その一角で、ひときわ香ばしい匂いを放つ屋台を見つけた。串に刺して焼かれているのは、紛れもなく黒光りするサソリだった。隣の大皿には、素揚げにされたバッタが山盛りになっている。
一瞬ためらったが、旅の恥はかき捨てだ。屋台の親父に指をさすと、彼はニヤリと笑い、熱々のサソリ串を手渡してくれた。恐る恐る口に運ぶ。カリッとした殻の食感のあと、中からエビの味噌のような濃厚な旨味が広がった。意外にも、うまい。勢いに乗ってバッタも注文する。こちらはスナック菓子のように軽く、塩気と香ばしさが後を引く。ビールを呷り、異国の味を胃に収めると、この不毛の土地で生き抜く人々の力強さを、少しだけ理解できた気がした。
4章 月夜の出会い
乾いた肌
その夜、宿の屋上で一人、ぬるい酒を飲んでいた。空には満月が浮かび、風の音だけが響いている。不意に隣に人の気配がして、振り向くと一人の女性が立っていた。日に焼けた肌と、風に吹かれても動じない強い瞳が印象的だった。彼女は地元民なのか、それとも僕と同じ旅人なのか。
「風が強い夜ね」
彼女は僕の国の言葉で、静かにそう言った。どこで覚えたのか、そんな無粋な質問はしなかった。僕たちは言葉少なに酒を酌み交わした。互いの名前も、どこから来たのかも聞かない。ただ、この灼熱の地の、孤独な夜に寄り添う魂がそこにあった。彼女の部屋で、僕たちは体を重ねた。汗と砂の匂いが混じり合う。それは情熱というより、もっと乾いた、生きていることを確かめ合うような行為だった。
翌朝、目を覚ますと、隣に彼女の姿はなかった。シーツに微かに残る彼女の匂いだけが、昨夜の出来事が夢ではなかったことを告げていた。不思議と寂しさはなく、むしろ心と体が軽くなったような、すっきりとした感覚だけが残っていた。
5章 半島の果てへ
風が生まれる場所
ザラハでヒッチハイクしたトラックの荷台に揺られ、僕は半島の最先端を目指していた。道なき道を進む。遮るもののない平原では、風はさらに勢いを増し、立っていることすらままならない。運転手は「風が生まれる場所だ」と教えてくれた。
数時間後、トラックは巨大な断崖絶壁の前で止まった。ここがマグダーマ半島の果て。眼下には、紺碧の海が白波を立てて荒れ狂っている。陸から吹き付けた砂が、滝のように海へと流れ落ちていた。僕は崖の縁に立ち、全身で風を受けた。それは、あらゆる思考や感傷、後悔を吹き飛ばしていくような、暴力的なまでの浄化だった。大声を張り上げても、すぐにかき消されてしまう。ここでは、人間の存在などあまりにちっぽけだった。
結び
帰りの空港で、僕は鏡に映る自分を見た。肌は焼け、髪はゴワゴワになり、数日前より少し痩せたようだった。だが、その目は妙に澄んでいた。
マグダーマの旅は、何も与えてはくれなかった。美しい景色も、心温まる出会いも、あったのかもしれないが、それらは全て風と砂に削り取られていった。サソリの味。闇市の喧騒。彼女の乾いた肌の感触。そして、すべてを吹き飛ばす風の音。僕の中に残ったのは、そんな断片的な五感の記憶だけだ。
それでよかった。余計な荷物をすべてあの半島の砂漠に置いてきたような気分だった。飛行機が離陸し、赤茶けた大地が遠ざかっていく。僕の心は驚くほど軽やかだった。旅は終わった。そして僕は、すっきりとした気持ちで、また日常へと戻っていく。