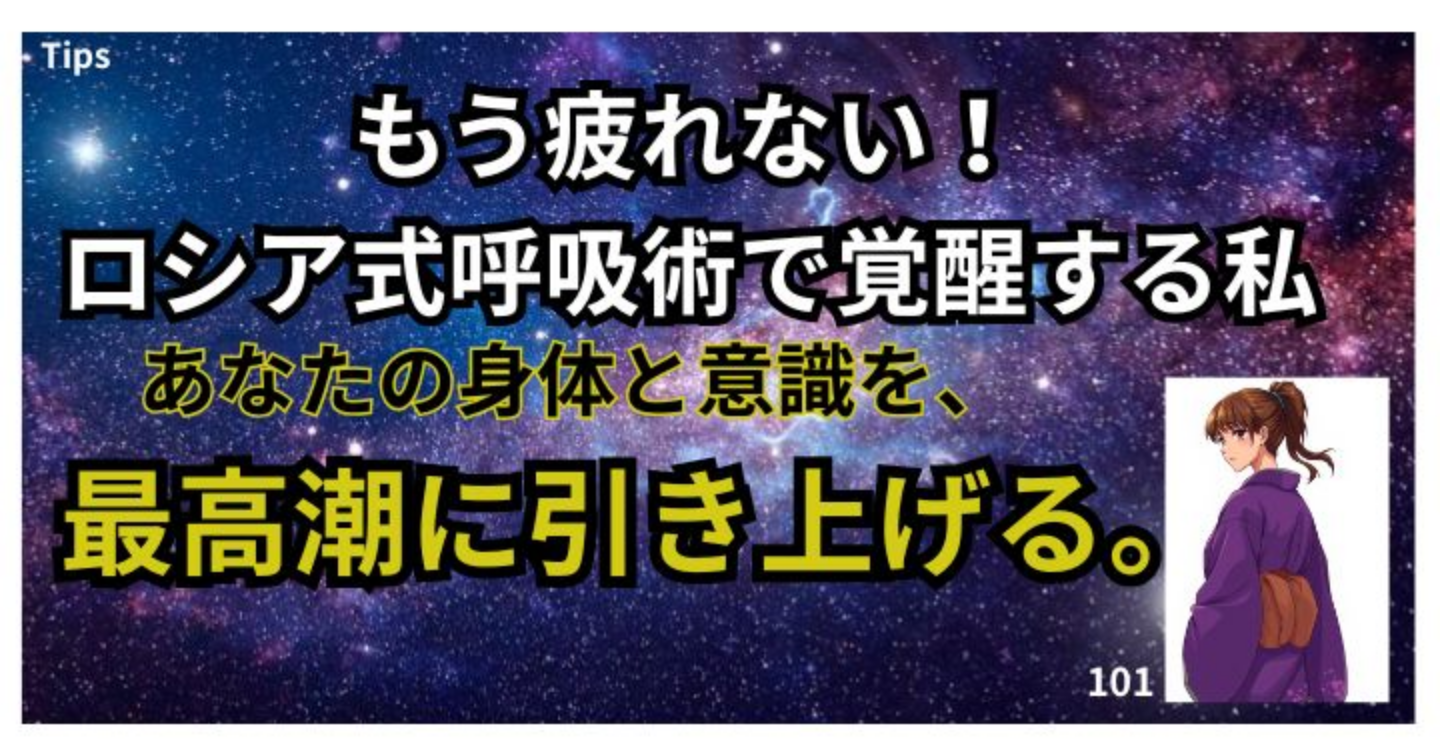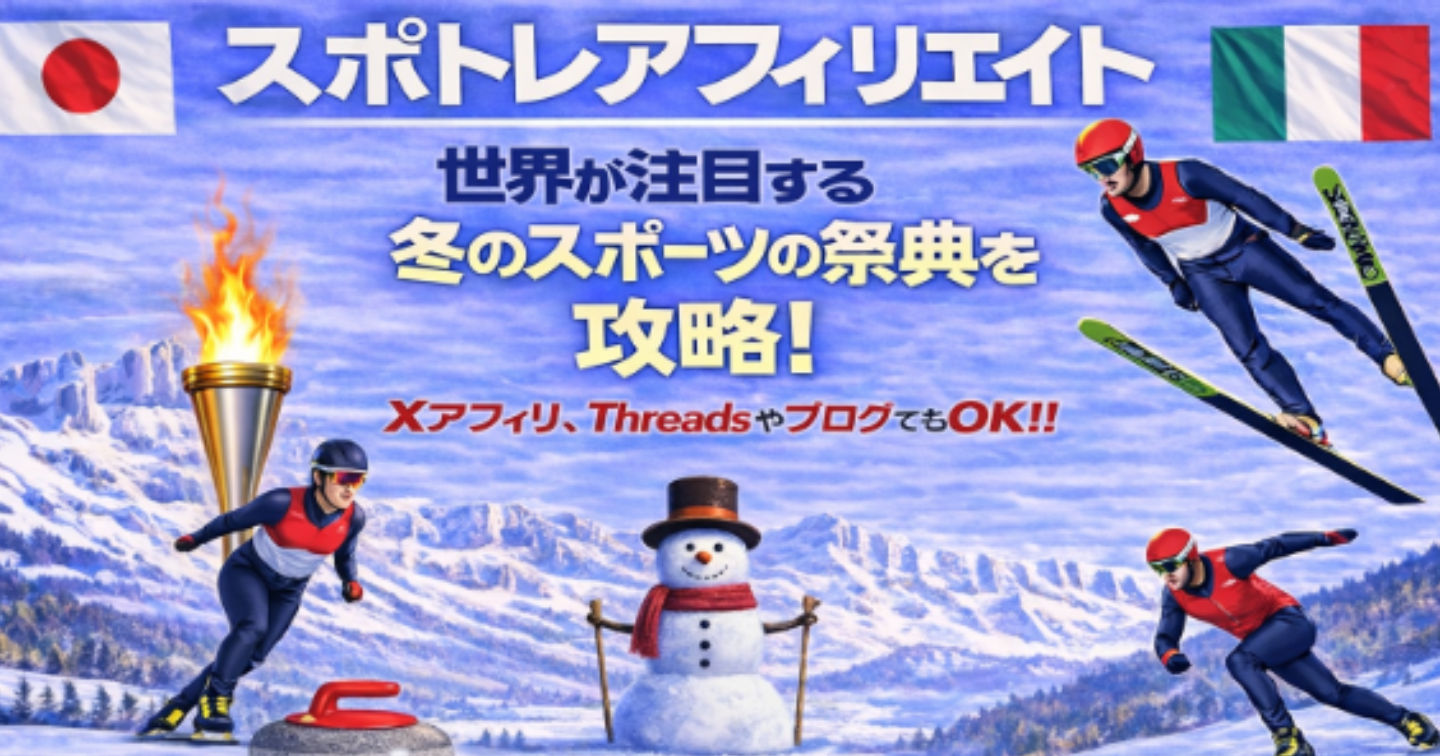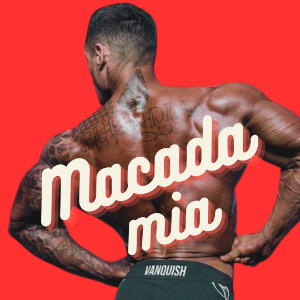はじめに:なぜ今、システマを学ぶのか?
現代社会は、私たちに多くの緊張とストレスをもたらします。仕事のプレッシャー、人間関係の複雑さ、情報過多なデジタル環境。私たちは常に何かに追われ、知らず知らずのうちに心身に不必要な負荷を蓄積しています。その結果、肩こりや腰痛、原因不明の倦怠感、集中力の低下、そして何よりも「生きづらさ」を感じている人も少なくないでしょう。
こうした現代の課題に対し、ロシアの伝統的なマーシャルアーツである「システマ」は、驚くほど普遍的で実践的な解決策を提示します。システマは単なる格闘技ではありません。それは、人間本来の自然な状態を取り戻し、いかなる状況下でも快適に、そして効果的に機能するための心身のシステムであり、哲学です。
本書は、システマの核心にある「4つの原則」と、その土台となる「呼吸法」に焦点を当て、私自身の修行の中で得た気づきを基に、その深遠な智慧を紐解いていきます。多くの格闘技や自己啓発書が「頑張り」や「努力」を強調する中で、システマが提唱するのは「無理をしない」「力を抜く」という、一見すると逆説的なアプローチです。しかし、このアプローチこそが、私たちの心身に潜む真の可能性を引き出し、日々の生活、仕事、人間関係、そして有事の際にも役立つ、揺るぎない基盤を築き上げる鍵となるのです。
本書にはイラストは含まれませんが、言葉の力によってシステマの世界を鮮やかに描き出し、読者の皆さんが自身の心と身体でその原則を「感じる」ことができるよう、丁寧な描写を心がけました。システマの原則は、武術の練習場だけでなく、デスクワークの合間、満員電車の中、プレゼンテーションの最中、あるいは大切な人との会話の中など、あらゆる場面で応用可能です。この本を通して、皆さんが自身の心身と向き合い、より快適で、より自由な生き方を発見する一助となれば幸いです。さあ、システマの智慧を探求する旅に出かけましょう。
第1章 システマの「4つの原則」を理解する
システマの学習を始めるにあたり、まず理解すべきは、その根幹を成す「4つの原則」です。この原則は、システマの複雑な教えを分かりやすく伝えるために整理されたものだと理解していますが、このシンプルな4つの言葉には、システマの哲学のすべてが凝縮されており、これらを深く理解し、実践することで、私たちは自身の心身を根本から変えることができます。
この4つの原則とは、「呼吸」「リラックス」「姿勢」「動き続ける」です。これらはそれぞれが独立した要素ではなく、互いに密接に結びつき、常に同時に存在することが求められます。どれか一つが欠けても、システマが目指す「快適な状態」は実現しません。
1. 「快適な状態」の追求:システマにおける理想的な心身の状態
システマが最終的に目指すのは、「快適な状態」です。この言葉を聞いて、皆さんは何を想像するでしょうか? ふかふかのソファに身を沈め、温かい飲み物を片手にくつろぐ姿でしょうか? それもまた一つの快適さでしょう。しかし、システマにおける「快適な状態」は、単なる肉体的な安楽さや精神的な平穏さだけを指すのではありません。それは、どんな状況下にあっても、私たちの心と身体が最大限に機能し、変化に柔軟に対応できる、無理のない、最高のパフォーマンスを発揮できる状態を意味します。
偉大な師範が「四原則」という言葉をあまり使わないと聞いたことがあります。それは、彼がより本質的なことを伝えているからだと私は解釈しています。その本質とは、「この四つの状態が揃った状態」こそが、すなわち「快適な状態」であるということです。この快適な状態では、私たちは快適に動け、快適に生きられ、そして快適に戦うことができます。
「快適な状態」とは、具体的にどのような状態でしょうか? それは、身体に不必要な緊張がなく、精神的にも無理をしていない状態です。例えば、私たちは日々の生活の中で、様々な形で緊張を強いられています。パソコンに向かう際の肩の力み、プレゼンテーション前の胃の痛み、あるいは単に「ちゃんとしなければ」という内なる声が作り出す心のこわばり。これらはすべて、私たちを「不快な状態」に陥れ、本来持っている能力を制限してしまいます。
システマの教えは、こうした不必要な緊張を手放し、心身を解放することによって、人間本来の自然な動きと感覚を取り戻すことを促します。まるで、風に揺れる柳の木のように、しなやかで力強く、どんな方向からの力にも対応できる、そんな状態がシステマの目指す「快適さ」なのです。それは、ただ受け身であることとは違います。常に準備ができており、どんな困難にも冷静かつ効果的に対処できる、内なる平静と力強さを兼ね備えた状態です。
この「快適な状態」は、漠然とした抽象的な概念だと感じるかもしれません。「快適って何? とりあえず寝てればいいの?」と思う人もいるでしょう。しかし、システマの実践を通して、私たちはこの「快適さ」を具体的な感覚として捉え、自らの心身にその状態を作り出す方法を学んでいきます。それは、無理をせず、緊張を手放し、常に自分自身を観察し、調整し続けることで到達できる、深く満たされた状態なのです。
2. 4つの原則の相互作用:なぜ全てが同時に必要なのか
前述したように、システマの「4つの原則」は、それぞれが独立しているのではなく、常に同時に機能することが求められます。一つでも欠けてしまえば、その効果は大きく損なわれ、望む「快適な状態」から遠ざかってしまいます。
例えば、私たちは「呼吸」の重要性をよく理解しています。深呼吸をすることでリラックス効果があることも知っています。しかし、単に呼吸をすることだけでは不十分です。もし呼吸を一生懸命しすぎるあまり、身体に余計な緊張が走ってしまったらどうでしょう? 深い呼吸はできているかもしれませんが、身体がこわばり、リラックスできていない状態になってしまいます。例えば、呼吸に意識を集中しすぎて肩が上がり、顔に力が入るような状態では、身体全体が硬くなり、動きは制限されてしまいます。これでは「リラックス」と「動き続ける」という他の原則が阻害されてしまうのです。
また、深い呼吸をしようとするあまり、大きく身体を動かして深呼吸をする場合があります。これは確かに心地よい呼吸法ではありますが、もしその呼吸の動きが大きすぎるために、他の動きができなくなったり、動きづらくなったりするとしたらどうでしょうか? この場合、「動き続ける」という原則が守られていません。突然の動きに対応したり、素早く姿勢を変えたりすることが困難になってしまうのです。
あるいは、「リラックス」をしようと意識しすぎるあまり、身体がグデグデになってしまうケースも考えられます。「はい、リラックスしています」と言って、腕の力が抜けているかもしれませんが、その結果、姿勢が崩れてしまっている。これでは、身体の軸が定まらず、いざという時に素早く動くことができません。この状態は、「姿勢」という原則が失われていることを意味し、「動き続ける」ことも困難になります。
このように、4つの原則はどれか一つだけを切り離して考えることはできません。「呼吸」「リラックス」「姿勢」「動き続ける」の全てが、常に同時に、かつ調和して存在している状態こそが、システマが目指す理想的な心身の状態なのです。あたかもオーケストラの各楽器が、それぞれ独立した音を奏でながらも、全体として美しいハーモニーを織りなすように、私たちの心身の各要素も、互いに支え合い、響き合うことで、最高のパフォーマンスを発揮できるのです。
どれか一つに偏ることなく、常にこれら全てを意識し、バランスを取ることが、システマの実践においては非常に重要になります。この相互作用を理解し、自分の心身で体現していくことが、真の快適さと機能性を手に入れるための道筋となります。
3. システマにおける「居つかない」哲学:動き続ける意識
「動き続ける」という原則は、システマの哲学の中でも特に重要な要素の一つです。これは単に物理的に身体を動かし続けることだけを意味するのではなく、意識や思考の柔軟性をも含んだ、深い意味を持っています。日本の武道における「居つかない」という言葉が、この「動き続ける」という概念を非常によく言い表しています。
「居つく」とは、例えば相手の攻撃に対して身構えたり、次の行動を決めかねて一瞬立ち止まったり、あるいは特定の場所に意識が固定されてしまったりする状態を指します。このような「居つき」は、身体の動きを止め、反応を鈍らせ、さらには思考の硬直を招きます。システマでは、この「居つき」こそが、最も危険な状態の一つであると見なされます。
まず、身体の「動き続ける」ことについて考えてみましょう。私たちの身体は、常に流動的であるべきです。しかし、日常生活やスポーツの練習、あるいは精神的な緊張によって、私たちは無意識のうちに特定の部位を固定したり、動きを制限したりしがちです。例えば、恐怖を感じたときに呼吸が止まる、あるいは肩に力が入って硬直する。これらはすべて、身体が「居ついて」いる状態です。システマでは、このような身体の固定化を避け、常に柔軟で、あらゆる方向からの力に対応できる準備が整っていることを目指します。それは、まるで水のように、どんな器にも形を変え、どんな隙間にも流れ込むことができる、そんな自由な状態です。
次に、意識の「動き続ける」こと、すなわち「居つかない」哲学についてです。私たちはしばしば、一点に集中することや、一つの考えに固執することを美徳とします。確かに、集中力は物事を成し遂げる上で不可欠な能力ですが、その裏にはネガティブな側面も存在します。一点に意識が固定されてしまうと、その周りの情報がすべて意識から抜け落ちてしまうことがあります。例えば、特定のタスクに没頭しすぎるあまり、周囲で何が起こっているか全く気づかない、といった経験はないでしょうか?
この状態は、意識が「居ついて」しまっていることを意味します。システマでは、意識もまた、常に「動き続ける」ことを重視します。それは、集中しつつも、同時に周囲全体を意識できている状態です。視野が広く、どんな情報にもオープンであり、特定の思考や感情に囚われることなく、自由な精神状態でいられることです。
さらに、考え方や既成概念についても「動き続ける」ことが求められます。私たちは育ってきた環境や経験から、様々な先入観や固定観念を形成します。これらは時に私たちの思考を硬直させ、新しい意見を取り入れたり、新しい発想を生み出したりすることを妨げます。システマでは、こうした思考の「居つき」もまた、動きを阻害する「緊張」の一つと捉えます。常に思考を柔軟に保ち、既成概念にとらわれず、状況に応じて考え方を変化させられること。これもまた、「動き続ける」という原則が私たちに求めることです。
要するに、「動き続ける」とは、身体の流動性、意識の広がり、そして思考の柔軟性のすべてを含む、包括的な概念なのです。何かがうまくいかないと感じた時、システマの修行者は自問します。「どこか止まっていないか?」「足が止まっていないか?」「身体のどこかが固定されていないか?」「意識が一点に囚われていないか?」「考え方が凝り固まっていないか?」この問いかけこそが、閉塞した状況を打破し、再び流れの中に身を置くためのチェックポイントとなるのです。