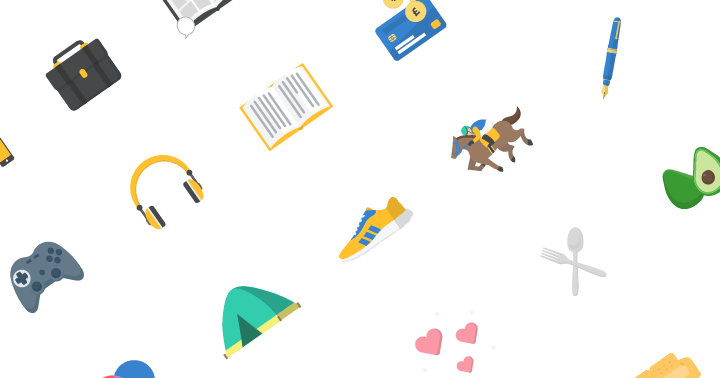第1章 エースの不在
プールサイドに立ったとき、私はいつも髪の重さを意識していた。 腰まで伸びた黒髪は、私の唯一の自慢であり、同時に練習のたびに邪魔になる存在だった。ゴーグルのベルトに絡み、クロールをすれば肩にまとわりつき、ターンのたびに水を含んで鉛のように重くなる。だけど私は切る気になれなかった。 水泳部の仲間から「切っちゃえば?」と言われても、私は笑ってごまかすだけだった。髪は私のアイデンティティ。切ったら自分じゃなくなる気がしたのだ。
そんな私たち水泳部が、一番大きな試練に直面したのは、六月のある雨の日だった。 県大会を目前に控えた放課後、顧問の先生から告げられたのは、信じられない言葉だった。
「……綾瀬が、交通事故にあったそうだ。命に別状はないが、しばらく入院になる」
部室の空気が凍りついた。 綾瀬は、私たち女子水泳部の絶対的なエースだった。背泳ぎと自由形の二種目で全国大会常連、部員全員が彼女に憧れていた。 その綾瀬が、県大会を目前にして離脱する。衝撃で誰も言葉を発せなかった。 重苦しい沈黙の中で、唯一、短く「うそ……」とつぶやいたのは私だった。
その日の練習は、誰も集中できなかった。プールサイドに座り込む者、泣き出す者、ただ水を眺める者。 私もスタート台に立ちながら、どうしても足が動かなかった。エースを失ったチームに、自分は何ができるのだろう。ロングヘアを背にまとったまま、水面を覗き込む自分の姿が、どこか場違いなものに思えた。
帰り道、雨に濡れたガラスに自分の顔が映った。 長い髪が肩に張りつき、重く垂れ下がっている。私はそれを指先でつまみながら、ふと考えてしまった。(もし、私がこの髪を切ったら……なにか変わるのだろうか)
もちろん、そんな単純なことじゃないと分かっている。髪を切ったって綾瀬は戻ってこない。私が突然速くなるわけでもない。 でも心のどこかで、髪を落とすことで何かが変わる気がしていた。 それが勇気なのか、責任感なのか、自分でも分からなかった。
翌日の部室。空気はまだ重かった。 顧問は「今いるメンバーで戦うしかない」と言ったけれど、誰も返事をしなかった。 綾瀬がいなければ勝てない。そんな気持ちが皆の顔にありありと出ていた。 私も同じだった。プールバッグの中に忍ばせているタオルを握りしめる。濡れた髪をいつも包んできたそのタオルの感触が、やけに重く思えた。
そのとき、隣に座っていた佐伯がぼそりとつぶやいた。「……私、髪、切ろうかな」
私は思わず顔を向けた。 佐伯は肩までのセミロングで、女の子らしさを大事にしているタイプだ。その彼女がそんなことを言うなんて想像もしていなかった。「どうして?」と問いかけると、佐伯は震える声で答えた。「だって……このままじゃ、綾瀬がいないってだけで、私たちの気持ちまで負けてるみたいじゃん。何か変えなきゃ。髪、切ったら気合い入るかなって……」
その言葉に、部室の空気が少し揺れた。 皆が一斉に佐伯を見た。何人かは驚いた顔をして、何人かはうつむいた。 私の心臓も高鳴っていた。(本当に、髪を切るの……? そんなことで何か変わるの……?)
でも、どこかで羨ましかった。佐伯には迷いを断ち切る勇気がある。それに比べて私は、まだ長い髪を背に抱えて、ただ震えているだけだ。 雨に濡れた窓ガラスに映る自分の姿が、頭にちらついた。
その日、部室を出るとき、私は決めていた。 ――私も、何かしなきゃいけない。 まだ答えは見つかっていなかったけれど、その思いだけは胸の奥で燃えていた。