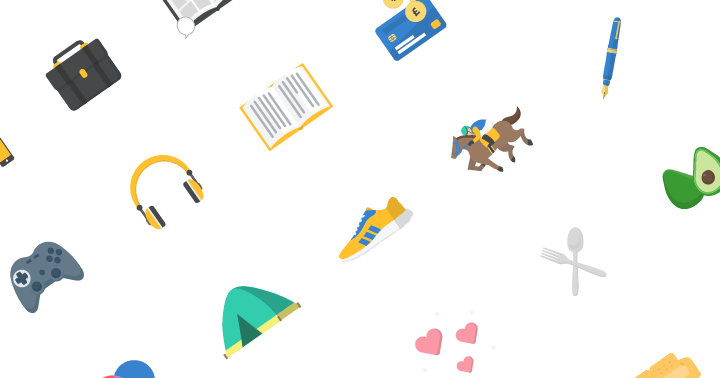ある年の夏に、じいちゃんが亡くなった。九○歳を超えて一○○歳が見えてきた頃だった。
「じゅうぶん生きたよ。大往生だ」
目の周りを赤くした父さんが言っていた。
じいちゃんが亡くなったと聞いて残念だったが悲しいという感情にはならなかったんだ。一六年、飼っていた猫が死んだ時も同じだった。僕にとっては、お気に入りの鞄が壊れたのに近い感覚しかなかったんだ。
「っあ、そうなんだ」
意識しなければそう言っていたかもしれない。それくらい、死、に対して興味がないんだ。狂っているんだろうね。それに気付いたエピソードがあるんだ。
それは、葬式が終わった後、棺桶の中で眠るじいちゃんの隣に花を入れていた時のことなんだけど。人形のように眠るじいちゃんを見て、本当に死んでしまったのだ、と実感すると同時に、触れたらどんな感触なのだろうか、と思っちゃったんだよ。
不謹慎な話だろ。普通そんなことを考えないよね。だけど、あの時、思ってしまったんだ。死者に触れるってどういう感覚なんだろうかって。昔、犬の死骸を抱えたことがあるけど、その時は死後硬直していて、生きている状態のを持つより重かったよ。
「剥製です」
そう言われたら信じてしまうくらいカチカチだった。
花を入れ終わった後、そんなことを考えながら棺桶の横で立ち、静かに眠るじいちゃんの顔を見詰めていた。
「触っちゃダメよ」
後ろから誰かの声が聞こえた。
じいちゃんに触ろうとしていたのを見透かされたのかと思い、顔を上げて声の方を見たよ。焦ったね。どう言い訳をしようか考えたよ。
声の主は叔母さんで、言われたのはその息子だった。僕の隣にいたので自分が言われたのだと勘違いしたんだ。隣に従兄弟がいることに気付かないくらい集中して目を閉じたじいちゃんの顔を見ていた。
最低な孫だよ。
全員が棺桶の中に花を入れ終わった。最後にばあちゃんが一輪、そっと入れた。
「おとうさん」
そう言って、ばあちゃんが涙を流しながらじいちゃんの頬に手を当てていたよ。それを見て申し訳なくなった。
誰かとの別れを惜しみ悲しむ人の姿を見て、自分は普通の人の心を持っていないのだと気付かされたね。
どうして僕はこんなに感情が歪んでしまったのだろうか。今でも原因が、分かっているような、分かっていないような感じだよ。
葬儀など全てが終わり、夜、ささやかな食事会が開かれたんだ。そこで喪主である伯父さんが挨拶をした。
「本日は父のためにお集まり頂きありがとうございました」
決められた文言を読み上げるように丁寧な挨拶だった。
「父はとても優しい人でした。怒られたという記憶がありません。そんなに裕福な家庭ではありませんでしたが、やりたい、と言ったことの殆どをやらせてもらいました。今、考えると、すごく負担をかけていたことが分かります。それでも父は、やりたい、と言ったらやらせてくれました。おかげで私は三浪した後、医学部に合格することができました。あの時、父が、ダメだ、と言っていたら滑り止めで受けていた大学で社会学を勉強することになったでしょう。今の私があるのは父のおかげです。本当に父には感謝しかありません」
涙混じりだけど晴れやかな表情を見せながら伯父さんが話していたよ。それを聞きながら、全くそのとおりだ、と思ったね。僕もじいちゃんは人格者だったと思っているんだ。尊敬しているよ。
タバコの話を聞いてから、ずっとね。