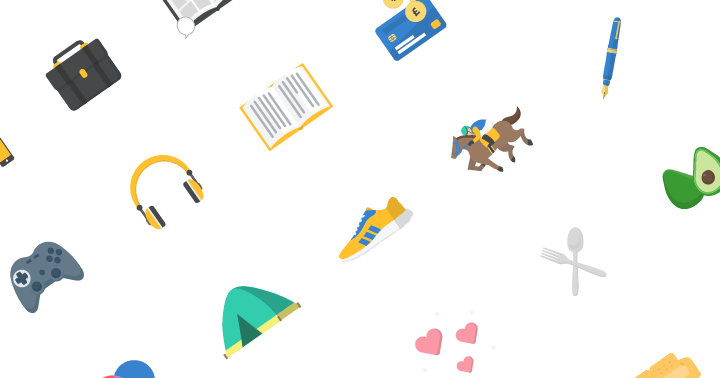窓越しに映る彼女がボタンをひとつひとつ外していく。今夜は彼女を独り占めできる。俺はそれだけで酔っぱらっていた。喝采をあびるように優雅を心がけ玉座に座りながら酒を飲もうとした。でも、
「ねえ、ワイン、持ってきて?」
彼女は顔を真っ赤にした。小さな声ではい、と言ってキッチンに向かった。彼女はとても優秀だ。脱ぎかけたシャツを再度着直すのではなく、脱ぐ選択をした。彼女は優秀だと思う。
お盆に乗せられたグラスはひとつ。3割だけ注いで俺に手渡す。彼女は優秀だと思わないか?
玉座を前にひざまづいた彼女は俺を見上げる。俺は見下す。永遠の時間がふたりを抱きしめている。愛が飛び交っている。ヒリヒリしながら、ぼやけていく視界の中には彼女だけがいる。幸せだと思った。
うまくいっていた。彼女はとても献身的だし、男に従うことが好きな良妻賢母だった。時々わがままを言うところも面白かったし、俺を満たした。自慢をすることが増えていった頃からだった。彼女が精神的に不調を抱えるようになった。それと同時に仕事の依頼がバカみたいに舞い込むようになっていった。彼女は全部請け負ってしまう。そして死ぬ直前まで自分を追い込みながらもすべてをこなしてしまう。優秀だとますます自慢したくなった。反比例するように精神が蝕まれていかなければ。
俺だって仕事がある。それなりの地位も役職もあるから、彼女の介護を専任するわけにはいかなかった。
でも彼女の仕事はそれ以上に重要な仕事だった。仕事に序列はないとは思うが、彼女が背負うものは仕事というくくりで俺と比べるには次元が違いすぎた。
彼女が精神を崩すと世界が動かなくなる。すべてのインフラがストップする。そんな想像が一番容易いだろう。
俺は頭を抱えた。友達からも文句を言われるようになった。
彼女も俺を拒絶するようになった。俺は俺で他の女に誘われることが増えていった。
36年間生きてきてはじめて死にたいと思った。彼女に拒絶されているのに他の女には色目を使われる。毎日嘔吐したし、精神科にも通うはめになった。
「他の男に預けてみたら」
簡単に言うなあと呆れた。藁をもすがる思いだったから、俺の親友と彼女の同郷の友人に声をかけてみた。ふたりとも彼女に恋をしていたことは俺もなんとなく感じていたからだ。彼女もこのふたりには酷いわがままを言えていた。つまり、気を許せる相手だったのだ。
作戦は成功した。彼女は復調した。今まで以上に大きな仕事ができるようになった。相乗効果で俺たちの仕事も巨大になっていった。年商換算するのが恐ろしいほどに仕事が舞い込むようになった。
彼女を社長に据えようとした。
彼女は泣いた。
「私は、恋がしていたい。何者かになんてなりたくない!あなたといるだけがいい」
収入はいらないと言った。報酬は3人で分割してくれてかまわないから、私はただあなたたちの恋人でいたいと言い続けた。半年粘ったが、彼女の意思は変わらなかった。
彼女の名前は翠
俺の名前は白瀬
親友の名前は青嶋
同郷の彼は黒井
俺たちはただ俺たちが生きるためだけに一緒に暮らしている。
<<<<続く>>>>>>>