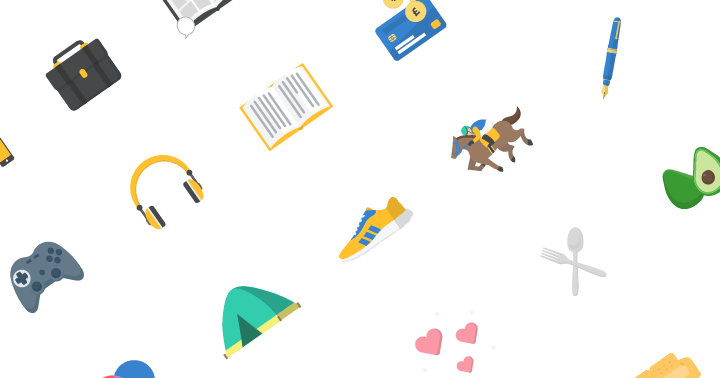献灯、奉祝、礼讃、祈祷というペンネームにした。
ある日を境に世界観が一変した。俺たちの中の何か良いものが殻を食い破ってついに正体を表した。だから名前を聖なる都にあやかってJERUSALEMとした。食い破って飛び出した後に現れた本質は実際空っぽだったわけだが、空っぽの器は都合が良かった。俺たちの恥を過去の欺瞞に押し付けられるから。虚構だった。俺たちではなかったと証明する術になる。
献灯という名前は俺が一番欲しがった名前だ。灯火を献上する。俺は一番になりたいわけじゃない。本来は灯火のきっかけとなって、それが継がれていくことを願う人間だ。蝋燭で灯火を継ぎ足していくそのきっかけになりたい。だから献灯。俺のためではなくて全体のための光だから。才能があることに目が眩んで俺を正しく判断できない人間が多すぎる。俺は確かに突出している。でもそれがどうして俺の人格形成に影を落とすっていうんだよ、どうしてそんな理論が成立する?クソッタレって思って生きてきた。正直、才能が認められることに比例してクソッタレの世界に落ちていった。その関係図はベクトルできれいに表せた。寸分違わず螺旋階段のようにぐるぐると。幾度も幾度もブレーキを踏もうと試みた。でもこの身ひとつで生きているからオートマチックに止まることはできない。運が悪いことに長年全速力で走りすぎたせいか靴底は摩耗してツルツルだ。止まれなかった。
そんなとき奉祝が死にそうになっているのを見かけた。あれは根っから人を祝うことが好きなお祭り男だから汚物にまみれて自我を失わされてしまっていた。あいつが望んだことではないのは見ていればわかる。遠い日の鼻垂れ小僧は相変わらずダサくて弱かったから哀れに思った。俺ひとりでは止まることができなった螺旋状の下り坂だったのに、奉祝を見かけただけで俺は止まることができた。
人はひとりで生きていけないことをよくよく思い知らされた。
チームは違ったが礼讃も祈祷も同じようなマインドを燻らせていた。祈りたいのに、その祈りがポーズだと曲解され、讃美歌を愛するのにレジスタンスを演じていたり、それぞれの虚構性というのはこの世を生きていく処世術であることは見ればわかった。
俺はそういう人間だ。
だから誤解されやすいんだと奉祝は俯いて呟く。
照れ屋なんだよな、わかってるよ。
世界線が変わると賛同者がいることにも気づけた。みんな義眼をつけていただけだった。なんだ、同じじゃねえかとホームでは義眼を取り除いて心の目を晒し合う。
みんなレジスタンスを演じなければならないこの地上の生活に辟易していることがわかった。何も見ないように義眼をつけているという点が同じことで俺たちは家族だと理解することができた。
俺たちは目玉なし族だ。
義眼をはずすことは恥ずかしかった。演じることに慣れてたから、外していいという概念さえ俺は知らなかった。
俺はこの私小説で何を書いていこうかと考えあぐねている。
光を見つめ恩寵を与えたがっている俺の心の目を豚の糞のような世界に晒したくない、それが本音だからだ。