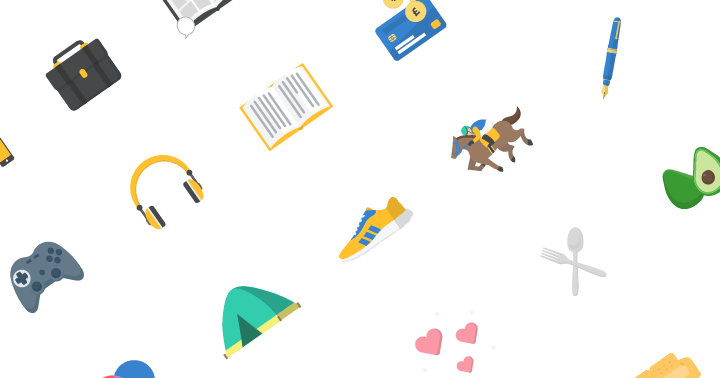第1章 真夏の水音
真夏の午後。 プールサイドのタイルは、裸足で立っているとじんわりと熱を吸い上げ、皮膚の奥まで温かさが届いてくる。照り返す光が水面をまぶしくきらめかせ、時折吹く風がプールの表面をさっと撫でるように揺らす。夏休みの自主練とはいえ、午前中のハードなメニューで部員たちはすっかり消耗していた。
私は、日陰に置いた長椅子に腰かけ、タオルで髪をざっと拭きながらペットボトルの水を口に含む。髪はまだ水をたっぷり含んでいて、肩や首筋に雫が落ちるたび、ひやりとした感覚が走る。湿ったタオルの匂いと、漂う塩素の匂いが混ざり合って鼻をかすめる。
男子部員たちはキャップを外して、額に貼りついた前髪を指先でかき上げていた。髪の長さや色は人それぞれだが、陽射しを受けてどれも濡れた宝石みたいに光っている。ふと視線を向けると、短髪の一年生が、額の汗と水を手の甲で乱暴にぬぐいながら、にかっと笑ってこちらに手を振った。
そんなときだった。 背の高い三年の先輩――副キャプテンの中野さんが、ぽつりとつぶやいた。「なあ……これ、髪切ったらもっと涼しいんじゃね?」
その声は、冗談半分のようにも聞こえたし、本気で言っているようにも聞こえた。暑さでぼんやりしていた空気の中、その一言が水面に小石を投げ入れたように波紋を広げた。
「確かに、帽子かぶるしな」 「短い方が乾くの早いし」 近くにいた数人がすぐに同調し、笑いながら自分の髪を引っ張って見せ合う。
そこから話は、自然と昔話に移った。 二年前、合宿中に当時の三年生たちがプールサイドで互いに髪を刈り合ったというエピソードだ。海水浴に行く予定が雨で中止になり、退屈しのぎに始めたのだという。バリカンとハサミでどんどん刈っていき、最後には半分以上が坊主になったらしい。 「めっちゃ涼しかったし、泳ぐのも楽だった」と誰かが付け加えると、周りから笑い声が上がる。
「そういや俺、バリカン持ってきてるぞ」 別の先輩――声の大きな三年の安藤さんが、部室の隅に置いていた青いプラスチックケースを持ってきた。カチリと留め具を外すと、中には銀色に光るバリカンと、黒い櫛、刃の油、はさみまでそろっている。
「なんでそんなもん持ってきてんすか」 「いや、弟が坊主にしたときに余ったやつ。家に置いとくより面白いかなって」 そう言ってバリカンを手のひらで転がしながら、にやりと笑う安藤さん。
そのときの場の空気が、ほんの少し変わったのがわかった。 笑い声は変わらない。でも、どこかに「本当にやってみようか」という期待が混じっている。
「マジでやんの?」 「やるなら今でしょ!」 「どうせ午後は軽く流すだけだし」
冗談のはずの話が、徐々に現実味を帯びていく。その様子を見ながら、私はペットボトルの水をもう一口飲み、口の中の熱を冷ました。
視線の端に、白いプラスチックの椅子が見える。普段は監督が使う、背もたれのついた簡易チェアだ。そこに腰を下ろし、濡れた髪をタオルで押さえながら、バリカンの刃を首筋に当てられる自分を――ほんの一瞬、想像してしまった。
その瞬間、胸の奥がふっと熱くなる。 金属の冷たさ、振動、髪が軽くなっていく感覚……。あまりに具体的な想像に、自分でも驚く。慌てて頭を振って追い払おうとするが、波紋のようにじわじわと残ってしまう。
ふと、前の方で中野さんが自分の髪をつまんで、「もうだいぶ伸びたし、ちょっと試すか」と笑った。その声に周囲がざわめく。安藤さんがバリカンを持ち上げ、コードを引きずりながらプールサイドを歩く。 コードの先を追うと、延長ケーブルが部室の窓から伸びていた。準備はもう整っている。
「おー、中野先輩からか?」 「やっちゃえやっちゃえ」 からかう声と、わくわくを隠しきれない声が入り混じる。
私はその様子を、タオルで髪を押さえたまま見ていた。何でもない夏休みの練習後が、急に特別な時間に変わっていく。 陽射しが水面で乱反射し、そのきらめきがプールサイドの髪の先にまで届くように思えた。
……このあと、何が起きるのか。 私の胸は、理由もなく高鳴っていた。
第2章 最初のバリカン
中野先輩が椅子に腰を下ろした瞬間、周囲の視線がそこに集まった。 背筋をまっすぐにして座る姿は、まるでこれから記念写真でも撮るかのようだが、手に持ったのはカメラではなく、銀色のバリカンだった。
持ち主の安藤さんが、ゆっくりとスイッチを入れる。 「ブン」と短く高い音がして、すぐに低く安定した唸りに変わった。その低音は、空気を震わせて私の胸の奥まで届く。まるで遠くで雷が鳴っているような、でもすぐそばにあるような――そんな不思議な響き方だった。
濡れた髪に刃が触れた瞬間、音がわずかに変わった。 「ジュルッ」と湿った音が混ざる。水を含んだ毛を押し分け、刃が頭皮をなぞるたび、細かな水滴が飛び散ってタイルに落ちる。陽射しで熱を持ったタイルの上に、冷たい雫がぱちんと弾けて小さな輪を描いた。
最初のひと撫でで、前髪がごそっと削がれる。短い毛と長い毛が混ざった束が肩をすべり落ち、白いプールサイドに濡れた跡を残す。その黒々とした塊が、なぜかやけに鮮明に見えた。 「おー、けっこう落ちたな」 周りから笑い声が上がる。誰かがスマホで動画を撮り始め、カメラのレンズが陽光を受けてきらりと光った。
バリカンは前から後ろへ、ゆっくりと動く。耳の後ろを通るときには、さらに音が変わり、水分を押し分ける感触が一段と強くなる。「ジュリ、ジュリ」という刃の動きに合わせて、中野先輩の首筋の産毛がなびき、また落ち着く。そのたびに黒く濡れた髪束が地面に落ち、やがて風に押されてプールの縁へと寄っていく。
ひと房、またひと房が水面に落ちていく。波紋が静かに広がり、毛先が水中でゆらゆらと漂う。光が屈折して髪の色が少し茶色がかって見えるのが、妙にきれいだった。
「うわ、涼しい! 風が直接当たる」 中野先輩が笑いながら首を振る。その言葉に、周囲がさらに盛り上がる。 「じゃあ俺も!」「次、俺ね!」――男子たちは自然と順番待ちの列を作り始めた。
二人目、三人目と進むうちに、刈る方も刈られる方も慣れてきたらしい。耳の上を丁寧に揃えたり、襟足を少しだけ残してみたりと、遊び心が出てくる。 「お前これ、プロの仕上がりじゃね?」 「いや、ここだけ段ついてるって!」 笑い声と冗談が飛び交う中、バリカンは絶え間なく唸り続けている。
私はその音に、どうしても意識を奪われた。 低い振動が空気を伝って胸に響くたび、体の奥で心臓が早く打ち始める。まるで、その音が鼓動を煽っているかのように。
床に散らばった濡れた髪は、タイルの隙間に貼りついて形を崩さない。短い毛が指先に刺さりそうなくらい尖って見える一方、長めの束は水を含んで重たげに沈んでいる。風が吹くと、乾き始めた髪がふわりと浮いて、また別の場所に落ちた。
誰かが勢いよくプールに飛び込み、しぶきが飛んできた。落ちた水滴が、足元の髪束をさらに濡らす。塩素の匂いと、濡れた髪の匂いが入り混じり、夏特有の湿った空気に包まれる。
そのとき、ふと気づく。 ――私は今、髪が落ちる瞬間から目を離せない。
刈る人の手つき。バリカンの刃が頭皮に沿って動く角度。削られた髪が肩から滑り落ちる速度。落下する途中で陽の光を受けてきらめく一瞬。すべてがスローモーションのように見える。
心臓がさらに速くなる。理由はわからない。暑さのせいにすることもできたが、それでは説明できない種類の高鳴りだった。
「おい、もっと短くいけよ!」 「じゃあ次は全バリだな」 ふざけ合う声に、また笑いが起きる。だがその笑い声の向こうで、バリカンの唸りだけは絶えず、一定のリズムで響き続けていた。
その音に引きずられるように、頭の中で自分の姿を想像してしまう。 白い椅子に座り、濡れた髪をタオルで押さえながら、バリカンの刃を首筋に当てられる。最初のひと撫でで、髪がごそっと軽くなる。耳元を通るときの微かな風と、くすぐったい振動――。
想像の中の私は、なぜか笑っていた。 その笑顔が、自分の中で妙に鮮やかに残る。
バリカンの音、水の音、笑い声。すべてが混ざり合ったこの空気の中に、自分も入ってしまったら――。 そう考えると、胸の奥が熱くなるのを止められなかった。
第3章 女子の番
男子の数人が順番を終えると、プールサイドの空気がわずかに変わった。 バリカンの低い唸りはまだ続いているのに、笑い声に混じって妙なざわめきが生まれる。 「なあ、女子もどう?」 誰かが軽く言ったその一言が、場を一瞬だけ凍らせた。
私を含む女子たちは、最初は笑ってごまかした。 「いやいや、絶対無理!」 「試合前にそんなことできるわけないでしょ」 声に出して否定しながらも、視線は自然とバリカンへ向かう。まだ温もりの残る刃先から、さっき刈ったばかりの短い毛が数本、濡れてくっついている。
「大丈夫だって。すぐ伸びるし」 「ほら、涼しいぞー」 さっき坊主になった男子が、自分の頭を撫でながら笑って見せる。濡れた頭皮に光が反射して、まぶしいくらいだ。
何度も断っていたのに、場の笑いと好奇心が少しずつ混じり合い、ひとりの女子が「じゃあ…ちょっとだけね」と前に出た。 驚きと興奮が同時に湧き上がる。男子たちが「おおー!」と歓声をあげ、その子のために椅子を引き、タオルを肩に掛ける。
私の心臓は、その瞬間からおかしなリズムで打ち始めていた。 見てはいけないと思うのに、目が離せない。
安藤さんが、慎重にバリカンを構える。 スイッチが入ると、低い振動音が空気を揺らす。 刃先が濡れた髪に触れる瞬間――「ジュッ」と小さな音を立て、長い髪がすっと押し分けられる。
最初は耳の後ろから。 耳たぶのすぐ横を刃が通過するとき、その子の肩がわずかに跳ねた。 水滴を含んだ黒髪が、細い束になってタオルの上に落ちる。その毛先が首筋をかすめ、くすぐるように動く。 私は、その一瞬の揺れまで鮮明に見えてしまった。
「うわ…ほんとに短くなってる」 その子が小さく笑い、鏡代わりにスマホのインカメラを覗き込む。 画面に映った耳周りは、ついさっきまでの柔らかな髪の影がなくなり、肌の色が明るく露出している。 「似合うじゃん!」と誰かが声をかけ、拍手が起こる。
バリカンはさらに後頭部へと滑っていく。 耳から襟足へ、まっすぐなラインを描くように刃が動くたび、髪がざっくりと削がれ、下に溜まっていく。 その音、その動き、その落ちていく瞬間が、すべてスローモーションのように私の頭に刻まれていく。
「意外と気持ちいいかも」 その子が笑ってそう言ったとき、私は胸の奥が一段と熱くなるのを感じた。
短くなった後ろ髪を手で撫でながら、その子は立ち上がる。 水滴が首筋を伝い、背中へ落ちていく。 頬はほんのり赤く、目は少し潤んでいるように見えた。 拍手と笑い声が弾け、周囲の空気は完全に「女子もあり」というムードに変わっていた。
別の女子が「私もやってみようかな」とつぶやく。 その声に、場が一気にまた沸き立つ。 男子たちが椅子を空け、タオルを渡し、順番を促す。
私は、その光景をただ見つめていた。 自分の中で、何かが揺れている。 ――自分も、あの椅子に座ったらどうなるだろう。 あの振動音、耳元をかすめる風、首筋に触れる髪の感触を、自分の肌で感じたら。
理性が「やめておけ」と囁く一方で、胸の奥から別の声が強く主張する。 ――やってみたい。
その衝動は、もはや押し込められないほどに膨らんでいた。 けれど私はまだ、その一歩を踏み出せずにいた。 拍手の中、二人目の女子が椅子に座る。 スイッチが入る低い音に、私の心臓はまた跳ねた。
第4章 私の順番
「ほら、次あんたの番だよ」 横から伸びてきた手に、ぐっと背中を押される。抵抗する間もなく、私はプールサイドに置かれた白いプラスチックの椅子へと座らされた。タイルの熱が素足からじわりと伝わってくる。足先がくすぐったくなるくらい、心臓はもう早鐘を打っていた。
周りでは、さっきまで刈られた男子や女子たちが、笑顔で新しい髪型を撫でたり、水をかけあったりしている。その中から、男子の一人が青いバリカンを持って私の後ろへ回った。プールから上がったばかりの手が、まだ水滴をまとっているのが視界の端に見える。
「じゃ、いくよ」 低く笑う声と同時に、耳元で「ブゥン」という低い振動音が立ち上がった。音が近づくにつれて、背筋に電気が走るような感覚が広がる。金属のヘッドが首筋に軽く当たった瞬間、ひやりとした冷たさが走り、同時にその奥から、頭皮全体を震わせるような微細な振動が広がった。
バリカンが後ろ髪を持ち上げるようにして進むと、柔らかな髪が根元から断ち切られ、ふっと軽くなる。その軽さが、頭の内側から抜けていくようで、思わず息をのむ。視界の端、プールの縁へ黒い髪の束が転がり落ち、そのまま水面に触れると、ゆらりと漂い始める。水のきらめきの中で、髪がゆるやかに回転しながら流れていく様は、奇妙に美しくて、目が離せなかった。
「すげー軽くなるでしょ?」 刈っている男子の声が背後からする。私は言葉にならないまま小さくうなずいた。
側頭部に差しかかると、バリカンの音が一段と耳に響く。金属の刃が耳の付け根をかすめるたび、細かな震えが耳の奥にまで届く。耳の後ろの髪が剃られ、そこに風が通り抜ける感覚があった。プールの水面から立ち上る湿った空気と、夏の熱気とが交じり合って、肌を撫でていく。
周囲からは、見守る部員たちの視線が熱のように集まっているのを感じる。誰かが「似合う、似合う!」と笑いながら言った。けれど、その視線の熱と、頭皮に伝わる冷たい刃の感触のギャップが、私の心をさらにかき乱していた。
「前髪もいっちゃう?」 後ろから軽く聞かれ、私は思わず頷いてしまった。額の生え際に金属が触れ、刃が滑るたび、髪が視界を開いていく。前に落ちていく細い毛が頬をかすめる瞬間、くすぐったさと同時に、もう元には戻れないという妙な実感が胸に広がる。
「はい、完成!」 バリカンの音が止まると、世界が急に静かになった気がした。頭は驚くほど軽く、風がどこからでも通り抜けていく。プールの水面に、私の新しい影が映っている。濡れた首筋と耳のラインがはっきりと露わになっていて、思わず手でなぞった。
その感触は、思っていた以上にすっきりしていて――そして、どうしようもなく心地よかった。
第5章 水の中の感触
全員の断髪が終わったころ、プールサイドには黒や茶色の髪の束が、日差しを浴びてまだらに輝いていた。タイルの上を、風がふっと通り抜けるたびに、軽い毛束がふわりと揺れる。その光景は、さっきまで頭にあった自分たちの一部なのだと思うと、不思議な気持ちになった。
「じゃあ、最後に全員で!」 誰かが声を上げると、みんな一斉に水着の肩紐を整え、プールの縁へと並んだ。刈り上げたばかりの首筋や耳の後ろが、陽射しに白く光っている。私も列の中に入り、足先を水面に近づけた瞬間、熱くなったタイルとの温度差にゾクッとした。
「せーの!」 掛け声と同時に、十数人の身体が一斉に水へ飛び込んだ。
ばしゃあっ――。 水が全身を包み込み、刈りたての首筋をするりと撫でていく。今までの長い髪のときには決して感じられなかった感触。髪がないぶん、頭皮や耳の後ろ、うなじの細かな産毛まで、冷たい水の流れを敏感に拾ってしまう。
水中で目を閉じると、頭の表面全体に柔らかな圧力がかかっているのがわかる。それはまるで、指先で優しく撫でられているようで、思わず息が詰まりそうになる。浮力に身を任せながらも、胸の奥からふつふつと湧き上がる快感に、鼓動が早まった。
浮かび上がると、太陽の光が一面に広がっていた。水面に視線を落とすと、黒や茶色の細かな髪がふわふわと漂っている。それらが光を受けてキラキラと反射し、金粉を撒いたみたいに揺らめいていた。
「やばい、気持ちいい!」 すぐ隣でショートになった女子が笑いながら水をかけてきた。彼女の耳も、私と同じようにすっかり露わになっていて、そのラインを水滴がつたう様子がやけに目に焼き付いた。
プールの中では、みんなが笑い合い、髪を撫でたり頭をくしゃくしゃにしたりして遊んでいた。断髪という少し特別な体験を、同じ瞬間に共有したせいか、不思議な一体感が漂っている。
けれど私は、みんなと同じ笑顔を浮かべながらも、胸の奥に別の感情を抱えていた。首筋を水がすべる感触、その後に残るひんやりとした余韻――それが、どうしようもなく心地よく、癖になりそうだった。
「……また、やりたいかも」 自分でも驚くほど自然に、その言葉が心の中に浮かんでいた。
水中でふと目を閉じる。太陽の光が水越しに揺れて、刈りたての頭皮をやわらかく照らす。耳元で、仲間たちの笑い声が遠く近くに響いている。この感覚を知ってしまったのは、自分にとって秘密の贈り物のようだった。
私は顔を上げ、空を見た。真夏の青さがまぶしくて、思わず目を細める。その中で、胸の鼓動がまたひとつ跳ねた。