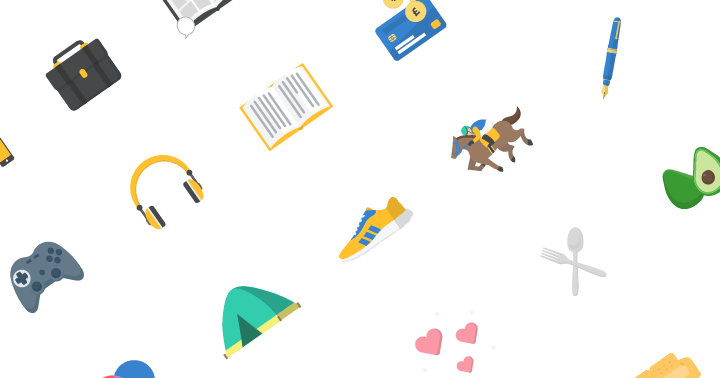井上彩花(19)は、看護専門学校の2年生。肩下まであるセミロングの髪には、ゆるくウェーブがかかっている。淡い茶色の髪が、制服の白さに映える。友人の間でも「彩花の髪、綺麗だよね」と言われることが多かった。
だが、看護学実習を控えた最近──その髪は、彼女にとって“煩わしさ”の象徴となっていた。実習の規則で「耳が出る髪型」「襟足が見えること」「まとめ髪は崩れないように」など細かな制約がある。朝は髪を結ぶ時間に追われ、ピンで留めても乱れる。制帽に押し込むたび、ウェーブの毛先が不自然に跳ねた。
そのうえ……2ヶ月前、長く付き合っていた恋人に別れを告げられた。
「おまえの将来って、髪より大事だよな」
そう言われた言葉が、ずっと頭を離れなかった。彼に褒められていた髪も、いまは鏡の中で重たく見えた。
「……リセットしたい」
声に出すと、胸が少しだけ軽くなった。
その日、親友の沙耶が「気分変えるなら、美容院付き合うよ」と言ってくれた。繁華街の路地裏にある、理容併設型のユニセックスサロン。カフェのように落ち着いた内装に、彩花は少し緊張しながら受付に立った。
「今日は、どうされますか?」
美容師が問いかける。彩花は、鏡越しに自分の髪を見た。
「……ショートに。思い切って切ってください」
「けっこう長さありますけど、大丈夫ですか?」
「はい。実習もあるし……全部、切ってしまいたいです」
美容師が笑みを返し、ハサミを持つ──その瞬間、隣の理容ブースから青年が顔をのぞかせた。控えめに声をかける。
「看護学実習ですか? ……あの、うち理容もやってて。実習用の刈り上げモデル、よかったら体験してみます?」
彼の名札には「柊 翔真(くすのき しょうま)・理容見習い」と書かれていた。
彩花は一瞬、息を飲んだ。「刈り上げ……ですか?」
「うなじ周りだけです。バリカンとハサミで仕上げて、清潔感が出ます。耳も出せるし、実習には便利ですよ」
バリカン──その響きに、彩花の胸がざわめいた。今まで経験したことのない髪型への誘惑。でも、少し興味が湧いた。
「……お願い、してもいいですか?」
「はい、ぜひ。じゃあこちらの席へ」
柊がケープを肩にかけると、彩花は背筋を伸ばした。鏡に映る自分の髪が、もうすぐ失われると思うと、不安と期待が入り混じる。
「バリカン、ちょっと冷たいかもです」
そう言って、彼は彩花の後頭部に指先を添えた。その優しい手の感触に、彩花の心臓が跳ねた。
キュイイイイイ──小さな駆動音が空気を震わせる。
うなじに触れた刃が、細かな振動とともに、彩花の毛先をなぞった。ふわりとした毛がケープに落ちる。刈られた部分は露になり、肌が風を感じ始める。
「毛流れ、綺麗ですね。ほんとに、理容向きかもしれません」
彼の声は静かで、温かかった。彩花は、今まで“髪を切られる”ことがこんなに心地よいとは知らなかった。
耳の後ろまで刈られた髪は、インナーショートのように自然に馴染みながら、実習用の清潔な印象へと変わっていく。柊は丁寧に仕上げながら、最後にハサミで毛先を整えた。
「……できました」
彩花が鏡を見ると、そこには見知らぬ自分がいた。軽やかで、凛としていて、涙を浮かべていない。まるで生まれ変わったようだった。
「背中が……涼しいです」
思わず呟いた言葉に、柊がふっと笑う。
「それ、刈り上げあるあるです」
実習が始まって1週間。彩花は、白衣の袖に腕を通すたびに、襟足の“涼しさ”を感じるようになっていた。
バリカンで刈られた部分は、髪が伸びる気配もなく、毎日の支度が格段に楽になった。寝癖もない。結ばなくていい。何より、鏡を見たときの違和感が、次第に“似合ってるかも”に変わっていく。
でも──自分でも不思議なほど、あの日の感覚が頭をよぎる。
バリカンの音。刃が肌をすべっていく微細な震え。柊の手が、静かにうなじを支えてくれていたこと。
なぜ、あれほど印象的だったのか分からない。でも思い出すたび、胸がすこし熱くなる。
実習先の病院が運営する高齢者施設にて、看護学生による整髪ボランティアが行われた。
「理容師さんも来てるから、手伝いは任せていいよ」
指導教員がそう言った瞬間、彩花の視線がその“理容師”に吸い寄せられる。
「あ……」
刈り上げてくれた、あの青年──柊 翔真だった。
彼はあの日と同じ、落ち着いた表情で年配の利用者に挨拶している。白衣の代わりに理容用エプロンを着て、軽やかにハサミを動かす。
彩花が手伝いにまわったとき、彼も気づいたようで、静かに会釈をしてきた。
休憩室で、二人は短く言葉を交わす。
「実習、順調ですか?」
「はい……髪、すごく楽になりました。すぐ動けて、気が散らなくて」
「よかったです。あのとき……実は、ちょっと緊張してました」
「え?」
「刈るとき、彩花さんの髪がすごく柔らかくて。毛流れが綺麗だから、刃が引っかからないんですよ」
彼の言葉が、なんだか嬉しくて──でも恥ずかしくて、彩花はほんの少し、耳が熱くなるのを感じた。
「……あの感触、すごく、気持ちよかったです」
言ってから、思わず自分で驚く。
柊は、少し照れたように微笑んだ。
白衣に袖を通すことに、慣れてきた頃。彩花は、自分の髪が“仕事の妨げ”ではなくなったことに、心から安心していた。
髪をまとめなくていいだけで、動作が早くなる。手元に集中できる。患者の表情を察する余裕も生まれた。刈り上げた襟足が、帽子の下でまったく乱れないのも嬉しかった。
「この髪型、本当に正解だったかも」
思わずそう呟いていたある日、高齢者施設での整髪ボランティアに参加する機会が訪れた。
施設の入口で名簿に記入していると、ふと耳に馴染みのある声が聞こえた。
「おはようございますー。今日はいつもより人数いますね」
その声の主は──柊だった。
彼は理容師見習いとして、施設に派遣されていたのだった。白のシャツにネイビーカラーのエプロン。シンプルだけど、清潔感があって似合っていた。
彼が視線を動かし、彩花に気づく。
「……あっ」
「こんにちは」
言葉が重なる。一瞬、気まずくなりそうな空気に、彩花が先に微笑んでみせる。
お昼の休憩中、ホール横のウッドデッキで二人きりになる時間ができた。
「実習、どうですか?」と柊が言う。
「快適です。髪、全然崩れないし、帽子の中で動かないし」
「それなら良かったです」
少し間を置いて──彩花が、ぽつりと呟いた。
「……あの日、刈ってもらった時。なんか、すごく気持ちよかったんです」
柊が目を丸くする。
「バリカンって、もっと荒っぽいイメージだったのに、音とか、振動とか……心地よくて。あと、手が──優しかったです」
「……え」
「手が、って。柊さんの」
言い終えた瞬間、彩花は顔が熱くなるのを感じた。けれど、言わずにいられなかった。
柊は少し戸惑ったようだったが、柔らかな笑顔で応えた。
「……彩花さんの髪、刈りやすかったです。毛の流れも良かったし、うなじの形も綺麗だったから」
その言葉に、彩花の心が静かに高鳴る──断髪の“感触”が、単なる便利さではなく、誰かと共有した記憶になっていく。
実習も終盤を迎え、彩花の意識は“ただこなす”から“自ら動く”へと変化していた。
ナースステーションで記録を書いていると、ふと手術担当の看護師長が話していた言葉が思い出される。
「手術室に立つ人間は、髪が帽子から出るようではいけない。何が起きるか分からないからね。完璧に収める、もしくは収めなくても済むような髪型が理想」
その言葉が、胸の奥に静かに響いた。
帰り道──駅のホームで彩花は無意識に自分の襟足を撫でていた。
刈り上げた部分は伸び始めている。毎日が便利だった。でもそれ以上に、あの“感触”が恋しい気持ちになっていた。
「坊主になりたいかも」
呟きは、風に消えたはずだった。でも、心の中では確かに灯がともった。
週末。彩花は、柊がいる理容ブースを再び訪れた。彼は驚いた顔をしていたが、すぐに笑みを浮かべた。
「今日は、メンテナンスですか?」
彩花は、まっすぐ目を見て言った。
「……坊主にしてください。完全に、バリカンで丸刈りに」
空気が一瞬、静まる。
「……え? 本当に?」
「はい。手術室に立つなら、髪に気を取られたくない。それに……また、あの感触を感じたいから」
柊はしばらく黙っていたが、彼女の瞳の意志を受け止めるように、ゆっくりとケープをかけた。
静かなバリカン音が再び空気を揺らす。今度は、首元からではなく、頭頂部から。
ジョリ……ジョリ……。
振動が頭皮に広がる。髪がごっそりと剃られていくのが分かる。鏡には、徐々に変化する自分の姿。
柊の指先が、丁寧に彩花の頭を支えていた。手はいつも通り優しく、でも確実だった。
耳まわり、うなじ、額の生え際まで──髪がなくなるたび、風の通り道が増えていく。
仕上げに、T字カミソリが登場する。
「少し冷たいかも。……痛くないように、優しく剃りますね」
泡立てたクリームが頭に乗り、鋭くも優しい刃が肌をなぞる。
彩花の目は閉じられていた。呼吸はゆっくり。彼の手と刃の感触が、まるで静かな儀式のように自分を包む。
ジョリ……。最後の一筋が落ちる。
「終わりました」
鏡の中、坊主頭の自分。
驚くほど違和感がなかった。むしろ、瞳が強く見える。輪郭が美しく映える。表情に迷いがなくなっていた。
「……軽い。頭が、風に触れてる」
彩花がそう呟くと、柊がそっと頭に手を添える。
「ほんとに、綺麗です。強さって、こういう形なんですね」
手術室シミュレーションの日。
彩花は、坊主頭に白衣とキャップをかぶり、鏡の前でゆっくり深呼吸をした。髪のない頭は、帽子の中にぴたりと収まり、違和感ひとつない。
実習チームが集まったとき、一瞬の沈黙が流れた。
「……井上さん、坊主?」
驚きと好奇心が混ざる視線に、彩花は微笑みで返した。
「髪がない方が、集中できるんです。動きに余計な迷いがなくなるから」
周囲はざわめいたが、看護師長だけが「よく決断したわね」と言って、軽く頷いた。
実習が始まると、彩花はまるで別人のようにキビキビと動いた。器具の配置、指示の確認、動線の管理──無駄がなかった。坊主頭の彼女が誰よりも“看護師らしい”と、誰もが認める空気になっていた。
その日の午後、施設からの訪問者が来ていた。見学席の後方に、柊の姿があった。
白衣姿の彩花を見つけると、静かに目を見開き、次第に優しい笑みを浮かべた。
実習の終了後、廊下でふたりは再会する。
帽子を外し、彩花は自分の坊主頭を指でそっと撫でた。
「恋も失って、髪も全部失って……でも、今が一番前を向いてる気がする。髪がないと、重くない」
静かな言葉が、柊の心に染み入っていく。
彼はためらいながらも、そっと彩花の頭に手を添えた。
温かく、優しい掌。
「……今の彩花さん、とても綺麗です」
彩花は目を伏せ、少しだけ照れながら微笑んだ。
数週間後。髪はわずかに伸び始めていた。
朝の光が部屋に差し込むなか、彩花は鏡を見てバリカンを手に取る。
「また、剃ろうかな」
それは、「変わり続ける自分」と「恋を続ける勇気」の形。
柊はその隣で、静かに微笑んでいた。