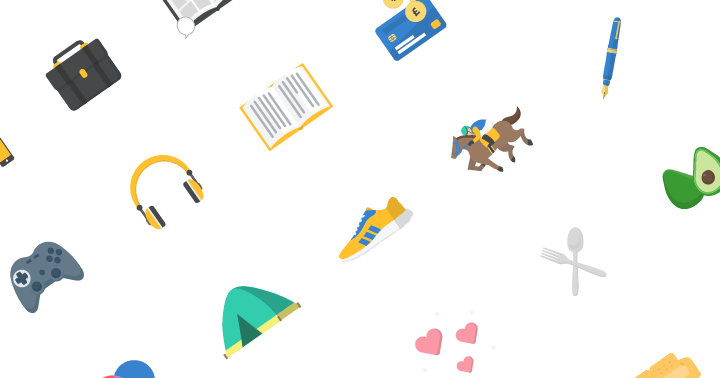第1章「妹の決断」
「ただいま〜」
梅雨明け間近の湿った空気のなか、久々に実家に帰省した私は、玄関の匂いに懐かしさを感じながらスニーカーを脱いだ。廊下の奥から、母と祖母、そして妹の声が重なって聞こえてくる。
「お姉ちゃん、おかえりー!」
弾けるような笑顔で、妹の紗季が台所から顔を出す。髪を後ろで軽くまとめ、すっきりとした顔立ちの印象。あれ、少し雰囲気が変わった?と思ったけど、ただの気のせいかもしれない。
「美沙、夕飯までちょっと休んでなさいな。今、お刺身切ってるから」と母。
「ありがとう。じゃあ、ちょっと二階で荷ほどきしてくるね」
それから数時間。夕飯を囲んで、笑いの絶えない久々の団欒。祖母は相変わらず私たち姉妹の小さい頃の話を持ち出しては、みんなで顔を見合わせて笑った。
食後、お茶をすすりながらのんびりしていたそのとき——。
「ねえ、わたし明日、髪切ってくる」
ふと、紗季が口にしたその一言に、空気が少しだけ動いた。
「髪?また整えるの?」
「ううん、バッサリ。……ベリーショートにしようと思って」
一瞬、時間が止まったような空気が流れる。
「えっ……紗季が?」と、母。
「失恋でもしたのか?」と、祖母が笑って言うと、紗季も肩をすくめて笑った。
「んーまあ、そうかも。こないだ、別れたんだよね。3年付き合ってた彼と」
母と祖母は口を揃えて「ええっ」と驚きの声を上げる。私は驚きながらも、どこか心がざわめいた。
ベリーショート。女の子が自分からその言葉を出すときの、あの潔さ。自分の髪を手放すという選択が、胸の奥を刺激する。
「本気なの?結構長いじゃない、今」
母が気遣うように言うと、紗季は軽く結んだ髪をほどいて、肩より少し下まである髪を見せた。
「うん。明日、友達の美容師の子が家に来てくれるの」
「この家で切るの?」と私。
「うん。せっかくだから、見ててよ。お姉ちゃんも、フェチでしょ?」
——ビクッと、心が揺れた。
まさか気づかれていたとは。いや、家族だ。紗季はずっと近くにいた。私が昔、鏡の前で自分の髪をじっと見ていたり、美容室の雑誌で刈り上げ特集を何度も繰り返し読んでいたのを、覚えていたのかもしれない。
「べ、別にそういうわけじゃ……」
「いいから。明日、9時に来てもらうから、ちゃんと起きててよ?」
笑顔でそう言い残して、紗季は部屋へ引っ込んだ。
私は一人、湯呑みに残ったお茶を見つめながら、心臓の鼓動が妙に早いことに気づいていた。
翌朝。
夏の光が差し込むリビングには、鏡台と折りたたみの椅子、そして美容師の友人らしき女性が準備を進めていた。
「じゃ、よろしくね」
紗季が椅子に座る。友人がゴムでざっくりと髪をブロッキングし、バリカンのスイッチを入れる——。
「ウィィィィィン……」
その音が響いた瞬間、私は喉が渇いたような感覚になった。
「じゃ、いくよ?」
友人が後ろ髪の束を軽く持ち上げ、襟足にバリカンをあてた。
「……っ!」
ザリッ、ザリッ……。髪が押し上げられ、床に束で落ちる。断ち切られるたびに、私の中のなにかが熱くなっていく。
「えっ、これ……すごい、感触……気持ちいいかも」
紗季の声がやけに艶っぽく聞こえた。バリカンがこめかみを撫でるたびに、顔がシャープに変わっていく。
数十分後——。
「できたよ。ベリーショート、っていうよりちょっと刈り上げ気味かも?」
友人が鏡を差し出すと、紗季はにこっと笑った。
「うん、すっごくいい。軽い!」
そのとき、背筋を汗が伝った。姉である私、美沙は、ただの見学者のつもりだった。でも、今の紗季は、あまりにも——
綺麗だった。
「お姉ちゃんも、切ってみる?」
そう囁かれたその瞬間、私の中のスイッチが、確かに何か音を立てて入った気がした。
第2章:ショートになった妹
鏡の前に座る妹——紗季は、まるで別人のように見えた。
「すっきりした……!」
美容師の彼女が、最後の整髪剤を吹きかける。紗季の髪は耳のラインで切り揃えられ、後頭部はタイトに刈り上げられていた。襟足は6mmほど、きれいに均一な段差が生まれ、指を這わせたらジョリッと音がしそうなくらい短い。
「うわ……思ったよりバッサリいったねぇ」
母が驚いたように言い、祖母は「まぁまぁ、今どきの子は思い切りがいいわね」と笑っていた。
けれど私は、誰よりも目を離せなかった。
紗季のうなじが、露わになっている。首筋の細さ、耳の裏の肌の白さ、その下で滑らかにカーブを描く丸い後頭部——。そして、その境界線をなぞるように浮き上がる刈り上げのライン。
ショートカットの髪型なのに、色気すら感じさせるその後ろ姿。私は無意識に喉を鳴らした。
「どう? 変じゃない?」
紗季が振り向く。正面から見ると、目元の印象が強まり、大人っぽさと可愛さが共存している。前髪も軽くなり、頬のラインがあらわになることで、どこか小動物のような愛らしさが増していた。
「……うん、似合ってるよ」
やっとの思いで答えた。けれど、声は少し掠れていた。
「やったぁ。よかったぁ……なんかね、自分が自分じゃないみたいで、ワクワクするの」
紗季は頭を振ってみせる。揺れない髪が、風を切ってシャッと音を立てた気がした。
「ねえ、ちょっと触ってみる?」
「えっ」
「うなじのとこ。ジョリジョリしてるから」
差し出されたその後頭部。私の手が、勝手に伸びていた。
指先が、刈り上げ部分に触れる——ジョリッ。確かに、手触りは硬い。だが、滑らかで心地よい。その下にある頭の丸みと相まって、どこか安心感すら覚える感触。
「……どう?」
「……なんか、気持ちいい」
「でしょ〜。クセになるよ、これ」
紗季は無邪気に笑った。けれど私の内心は、決してそんな明るい感情だけじゃなかった。
ざわざわと、心の奥が熱を帯びていく。さっきまでここにあったはずの長い髪、それを失って現れた首筋と刈り上げ。あの音、あの感触。——あれは、私のどこか深いところを刺激していた。
夕飯時。祖母が「暑い日は短いほうがいいわねぇ」と何度も繰り返し、母も「私も切っちゃおうかしら」などと冗談交じりに言っていた。
けれど、私はずっと紗季のうなじばかりを見ていた。テーブルの向こうで、髪を耳にかけたその瞬間、刈り上げのラインがちらりと見える。
一度気づいたら、もう目が離せない。それが羨望なのか、嫉妬なのか、それとも別の何かなのか。自分でもまだわからないまま、私は唇を噛んでいた。
「明日から、髪洗うのもドライヤーも楽になるなぁ」
「そうね。でも……冷えるかもしれないから、首にタオルでも巻いて寝なさいよ」と母。
「うん、そうする」
食後、紗季が部屋に戻るとき、私はふと声をかけた。
「……ねえ、後悔してない?」
「え?」
「そんなに、短くしちゃって」
紗季は立ち止まり、しばらく考える素振りをしたあと、微笑んだ。
「ぜんっぜん。むしろ、もっと短くてもいいかもって思ってる」
その言葉に、私の心はまた騒いだ。——もっと短く?
想像する。もっと刈り上げが深く、うなじの肌が透けるような長さ。バリカンのアタッチメントがもっと短い数字になり、やがてそれすら取り外され、最後には……ツルツルの、何もない肌。
そこまでしてしまったら——私は、どうなってしまうんだろう。
自室に戻っても、心は落ち着かなかった。何度も、スマホで「ベリーショート」「刈り上げ女子」と検索していた。けれどどの写真を見ても、今日の紗季ほど心が動かない。
——それは、あの瞬間を目撃したからだ。長い髪が落ちていく。うなじが露わになっていく。耳の裏にバリカンがあたる、その音と動き。自分の目の前で起きたからこそ、感じたざわめき。
思い出すたび、私は身体の芯から熱くなるのを感じていた。
あの時、妹が「見てて」と言ったのは、ただの気まぐれじゃなかったのかもしれない。
——私の中にも、何かが芽生え始めている。
その夜。私は鏡の前で、自分の長い髪を見つめていた。肩まで届く落ち着いたセミロング。どこにでもいる「普通の髪型」。でも、今はこれが重たく見える。
指先でうなじをなぞる。——ここを、刈ったら。
その妄想だけで、息が浅くなっていく。私はまだ、自分の気持ちに名前をつけられずにいた。
ただひとつだけ確かだったのは——妹の髪が短くなった瞬間から、私の中で何かが動き出してしまったということだった。
第3章:姉の動揺
妹・紗季のベリーショート姿が、私の中でぐるぐると渦を巻いていた。
あの日の夜、夕食の時。うちの食卓はちょっとだけざわざわしていた。
「いやー、あれだけ切るとスッキリするわねぇ」祖母が言うと、母も続ける。
「うん、なんか大人っぽくなったというか、気持ちも変わりそうね。いいと思うわよ、紗季」
「でしょ? もう、髪の毛が邪魔って感覚がなくなって快適すぎて。バリカン、クセになりそう」
「バリカン……」母が口にしたその単語に、私は反応してしまった。
あの時の「ジジジジ……」という音が耳に残っている。あの子のうなじに沿ってバリカンが滑るたび、地肌が露わになっていく光景。産毛のような髪の断面。刈られて落ちた髪の束。そして、見たこともないくらい軽やかで、少年のようなシルエットになった紗季の横顔——。
私の胸は、妙にざわついていた。もしかしたら、嫉妬?いや、羨望……。
「お姉ちゃんは、今の髪型、気に入ってる?」
紗季が私に向かって不意に聞いた。
「え? あ、うん……まあ、慣れてるし」
私は、肩まで伸ばしたストレートを手で触れる。長くもなく、短くもない、可も不可もない髪型。それは無難で、誰にも何も言われない安定のスタイル。
だけど。
——あれを見せられたら、もう、戻れない。
部屋に戻ってから、スマホで「ベリーショート」「女性」「刈り上げ」なんて単語で画像検索をした。似たようなカットを見ながら、うなじのラインに吸い寄せられる自分がいた。
「……私、気になってるんだ」
呟くと、自分の声が妙に響いた。
その夜はなかなか寝つけなかった。背中にまとわりつく髪の感覚すら、煩わしく感じる。汗をかいたせいで髪が首に貼り付いて、思わずゴムで結ぶ。
鏡の前。結んだ髪の下から覗くうなじ。そこに、もしバリカンを当てたら——。
その想像に、ゾクリと背筋が震えた。怖い。でも、試してみたい。私にも、あの感覚を味わう権利があるはずだ。
次の日の朝、洗面所で髪を乾かしていると、背後から声がした。
「お姉ちゃん、ちょっと髪、重そうだね」
振り返ると、紗季がいた。昨日より、さらにその刈り上げが堂々と見える。彼女は髪を耳にかけて、後頭部のラインを惜しげもなく晒していた。
「うなじ、風が通って気持ちいいよ」
そう言って、手で自分の刈り上げを撫でる仕草。その手つきは、明らかに快感に酔っていた。私の中に、奇妙な熱が灯る。
「触ってみる?」
そう囁かれて、思わず手を伸ばしていた。
ジョリ……
「!」
初めて触れる、刈りたての地肌。指先に感じる、柔らかくて鋭い感触。これが、1ミリ……? いや、0.8ミリかもしれない。
「いいでしょ?」
紗季がクスリと笑った。
私はもう、戻れない場所に踏み込みかけていた。
第4章:姉の決意
決意したのは、あの日の夜だった。
妹・紗季のベリーショートに触れたとき、私はただの姉ではなくなっていた。それは、羨望でも、好奇心でもない。もっと、深くて…熱い何か。——私も、刈られたい。その思いが、心の底からじわじわと湧きあがってきたのだ。
翌朝、鏡の前で、長年連れ添った髪に手を伸ばす。毛先を少しつまんで引っ張ると、細く、軽く、でも私の過去すべてが詰まっている気がした。
「……あんた、ホントに切るつもり?」
居間でテレビを見ていた紗季が、わざとらしく声をかけてきた。私が洗面台で髪をじっと見つめていたのを、気づいていたらしい。
「うん……今日、美容院、予約した」
「へえ。どこまでやるの?」
「……刈り上げ、まで」
すると紗季がニヤリと笑った。
「じゃあさ、うちでやれば?」
「え?」
「私、バリカン買ってるよ。やってあげよっか?」
私は一瞬固まった。家で? 妹の手で?でも——
それは、想像するだけで背筋がゾクゾクするような体験だった。
「……お願い、できる?」
「いいよ。おばあちゃんたちが出かけたら、やろっか」
***
そして昼下がり。母と祖母が買い物に出かけたのを見計らって、私は脱衣所へと足を踏み入れた。
洗面台の前には、紗季が準備していた道具たち。バリカン、櫛、ケープ、鏡——まるで、小さな理容室。
「じゃあ、お姉ちゃん、椅子に座って。先に後ろからいくね」
「……うん」
私は椅子に腰掛けた。紗季が手際よくケープをかけ、私の髪をいくつかの束に分けてクリップで留める。後頭部、耳の下あたりからのブロックがゆっくりと露出していく。
「緊張してる?」
「……ちょっとだけ」
「ふふ、大丈夫。気持ちいいよ」
そして——
「じゃあ、いくね」
ジジジジジジッ——
低く、重く響く音が、私の後ろから始まった。バリカンの振動が、うなじに触れた瞬間。私は息を止めた。
——ぞわっ。
まるで全身が震えるような感覚。振動が伝わって、頭の奥がしびれる。刃が肌を撫でていくたびに、髪がスルスルと落ちていくのがわかる。
「……すごい、落ちてる」
「後ろ、ほとんど地肌だよ。触ってみる?」
紗季の声に、私は手を伸ばした。
ジョリ……。
言葉にならなかった。柔らかくて、でも、力強くて。たった今、私の一部が剥がされ、解放されたことを、指先が知っていた。
「次、横もいくよ」
右耳の下にバリカンの振動が伝わり、髪がざくざく落ちる。耳が露わになると、風の通り道が変わる。頬にかかっていた髪がなくなると、顔がまるごとさらけ出されたような不安と快感が交錯する。
「左も……」
同じ工程が繰り返され、私はどんどん軽くなっていく。まるで、過去の私がどんどん削ぎ落とされていくように。
そして——
「上も刈っちゃう? ちょっとツーブロックっぽく残しても可愛いけど」
私は一瞬考えたが、もう迷いはなかった。
「……全部、いって」
「了解。じゃあ、アタッチメント外すね」
「え?」
「さっきまで6ミリだったけど、今度は……直で、ゼロ」
「直、って……」
「地肌、ツルツルに近くなるよ。覚悟してね?」
その瞬間、私は喉が鳴るのを感じた。
——怖い。けど、どうしてこんなにドキドキするんだろう。
「うん。お願い」
そして、最後の仕上げが始まった。
バリカンの刃が、アタッチメントなしで私の後頭部を滑っていく。髪が根元から消えていくのがわかる。ツルツルになっていく地肌に、風が触れた気がした。
「うわ……見て見て、お姉ちゃん。もう男子より短いよ、これ」
「ふふ……自分でも、信じられない」
紗季が鏡を私に向けた。そこには、見たこともない自分がいた。うなじから後頭部まで、ジョリジョリとした地肌。耳まわりも、ラインが綺麗に整えられ、頬のラインがくっきり浮かび上がっている。
「お姉ちゃん……綺麗だよ。すごく似合ってる」
「……ありがとう」
鏡の中の私は、どこか誇らしげに笑っていた。